SNSを見ていたら、ふと目に止まった投稿がありました。
原文不明ですが、
YES・NO形式の質問一問で、
1,000円・5,000円・10,000円
のどれを持っているか当ててみなさい
って感じの内容です。
・・・・・・・
……そんなアホな話、あるわけない。
そう思ってスルーしようとしたのに、なぜか頭の片隅に引っかかりました。
気づいたら、検索までしていました。
でも、いくら探しても「これが正解です!」という答えは出てこない。
みんな曖昧に盛り上がっているだけで、肝心のロジックが見当たらないんです。
いや、そこがいちばん大事なところでしょうよ。
結局、モヤモヤしたままスマホを閉じたんですが──その夜、寝る前にふと思いました。
「……あれ、ほんとにできないのか?」
一問で当てるなんて、どう考えても無理そうだけど。
もし“Yes”と“No”のあいだに、誰も通らない非常口みたいな反応をこっそり置けたら……?
そこからはもう、頭の中で勝手に謎解き大会です。
紙とペンを持ち出して、1000円、5000円、10000円をA・B・Cと書き並べ、何度も自問自答をくり返しました。
出題者の意図なんて正直わかりません。
でも、考えていくうちに、**「ああ、こういうことか」**という形が見えてきたような気がしたので、メモのようにまとめてみます。
※この記事はSNSで話題になった内容をもとにしています。正解を断定するものではなく、あくまで筆者の考察です。感じ方や解釈には個人差がありますので、どうかご承知ください。
✅ この記事でわかること
- なぜ普通のYes/No質問では3択を特定できないのか
- 「はい」「いいえ」しかないのに「答えられない」を引き出す仕掛け
- 1,000円/5,000円/10,000円を一問で分ける“自己言及型”ロジックの正体
- 応用パターンで逆転の発想を使う方法
- パズルを通して論理的思考を鍛えるコツ
「一問」で金額を特定できる?|思考実験のはじまり

一問で金額を特定できる。
そう聞いたとき、私は「またSNSで誰かが謎かけごっこをしているな」と思いました。
なにせ、相手は1,000円か5,000円か10,000円を持っている。
それをYesかNoで当てろというのです。
できるわけがない。
そんなことができるなら、今ごろ私はカジノでバカ勝ちして、築地に寿司屋でも構えています。
それくらい無茶な話です。
とはいえ、この手の“うさんくさい話”ほど、なぜか気になってしまう。
人間というのは、コンビニに行って何も買わずに出るときのように、引っ込みがつかなくなる生き物です。
「ちょっと考えるだけ」のつもりが、気づけば机の上に紙とペンが置かれていました。
まるで推理小説の探偵ごっこです。
三択を二択で分けるという無謀な挑戦
まずぶち当たったのが、三択を二択でさばくという根本的な無理ゲー。
Yes/Noの質問で、A・B・Cを区別するなんて、砂漠に線路を引くようなもんです。
「あなたが持っているのは5,000円以上ですか?」と聞けば、1,000円は「いいえ」、5,000円と10,000円は「はい」。
はい、終わり。
2択にしかならない。
お疲れさまでした。
ここで私はコーヒーを淹れました。
三択を二択でどうにかしようというこの話、どう考えてもバカバカしい。
でも、世の中にはその「バカバカしい」を突破してくる人がいるのです。
なぜか。
SNSを物色していると、
YesとNoの間に、“沈黙”を滑り込ませるという発想が目に止まりました
“沈黙”という第3の選択肢
「沈黙」というと、なにやらかっこよく聞こえますが、実態はもっと地味です。
Yesと答えると矛盾する。
Noと答えても矛盾する。
つまり、「どっちも答えられない」状態に持ち込めたらどうなるだろうか・・・?
この“答えられない”を意図的に引き出す。
ここに、この一問トリックの妙味がある気がしてきました。
つまり、Yes/Noという二本の線のあいだに、誰も通らない非常口をこっそり作っておくのです。
これで三択になる。
しかも、質問にそんなことは一言も書いていない。
出題者は何も言っていないのに、受け手が勝手に矛盾して、勝手に答えられなくなる。
まるでサイレントで仕込まれた地雷みたいなものです。
✅ まとめ
・Yes/Noだけでは三択は不可能。
・“答えられない”という非常口を仕込むのがポイント。
・ロジックパズルというより、ちょっと意地悪な落とし穴に近い。
まず基本から|なぜ普通の質問では特定できないのか

この話、ロジックがどうこう言う前に、まず大前提があります。
普通の質問では、ぜったいに3択は見抜けません。
はい、いきなり身も蓋もない話をしました。
でもこれ、意外とちゃんと理由があるんです。
たとえば、「あなたの持っているお金は5,000円以上ですか?」と聞いてみましょう。
1,000円の人は「いいえ」、5,000円と10,000円の人は「はい」。
これで2択。
はい、終了。
三択を処理しようとしたのに、見事に2択の壁にぶち当たります。
同じように、「1,000円未満ですか?」と聞いても結果は変わりません。
YesとNoで2つのグループに分けるしかない。
まるでお寿司屋で「サーモンか、それ以外か」という注文しかできないようなものです。
細かい味の違いなんて、最初から捨てている。
実はこの問題、数学的に考えればもっとハッキリしています。
Yes/Noの質問1回で、区別できるパターンは最大で2通り。
どう考えても、3つの金額を別々に見抜くことはできません。
「いやいや、何かうまい質問があるんじゃないの?」と期待したくなる気持ちはわかります。
私もそうでした。コーヒーをおかわりして、頭をひねりました。
でも、どこをどうひねっても、普通の質問ではどうにもならない。
この壁は、単純なYes/Noの世界では越えられないんです。
だからこそ、“トリック”が必要になります。
YesでもNoでもなく、第三の反応を引き出す。
つまり、質問の中に「普通じゃない仕掛け」を埋め込むんです。
✅ まとめ
・Yes/Noだけでは三択は理論的に無理。
・どんな「うまい質問」でも、2択にしかならない。
・だからこそ“仕掛け”が必要になる。
論理トリックの核心|“答えられない”という選択肢を生む
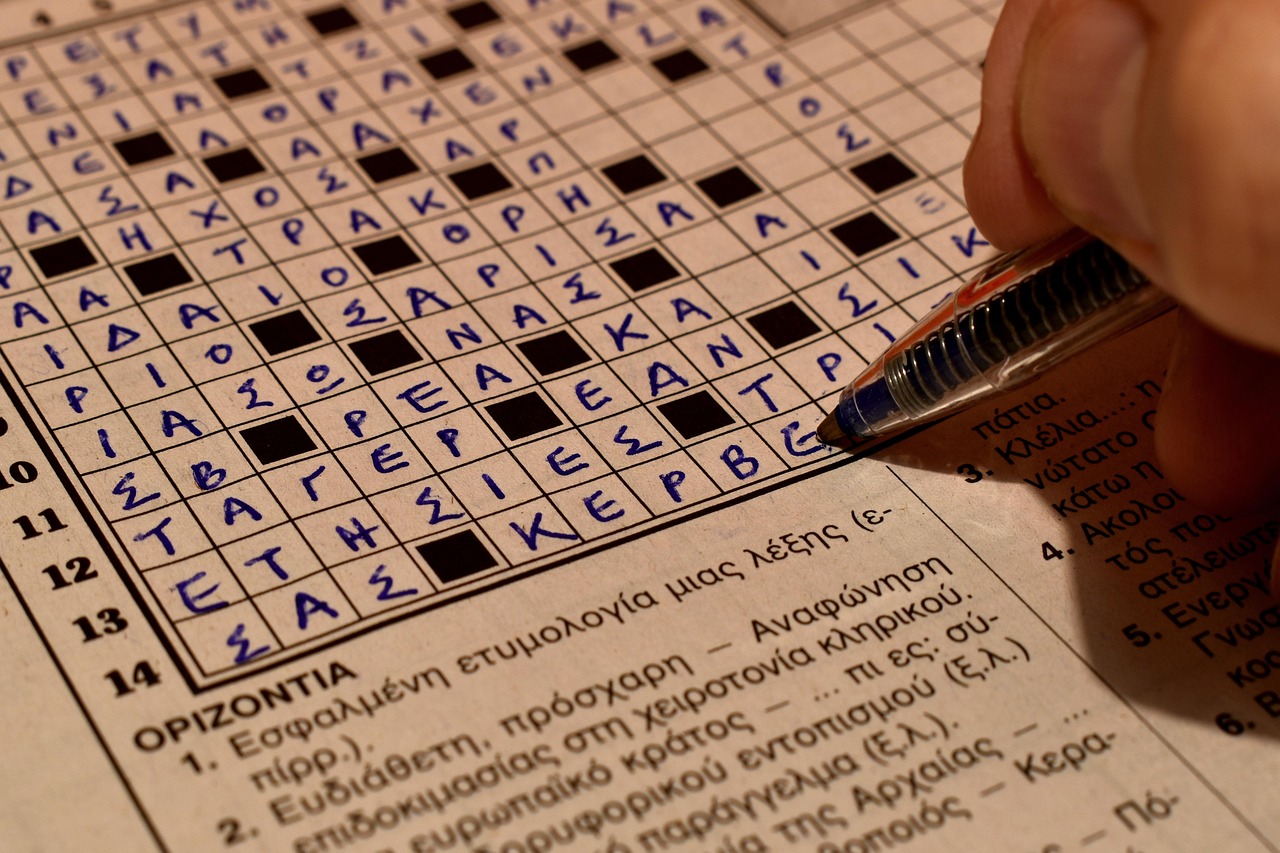
ここからが、この話のいちばんおいしい部分です。
いわば本マグロの中トロです。
YesとNoしか許されていないはずの世界に、第三の反応──
“答えられない”──をこっそり滑り込ませる。
この仕掛けを思いついた人は、たぶん性格が悪いです。
でも、その悪さが実に見事。
まず、普通の質問では「はい」か「いいえ」の二つにしか分かれません。
でも、もし「はい」と答えても矛盾して、「いいえ」と答えても矛盾する質問が出てきたらどうなるでしょうか。
答える人は、まるでバスの降車ボタンを押し損ねた乗客のように、身動きが取れなくなります。
この「矛盾で動けなくする」というのが、今回の肝です。
「はい」でも「いいえ」でもない、論理の袋小路に追い込む。
そうすると、結果的に「答えられない」という第三の反応が生まれる。
この“沈黙”こそが、ふつうの質問では作れなかった三択目になるんです。
ここでちょっと想像してみてください。
あなたは目の前で「この質問に“はい”と答えるとあなたは1000円を持っていることになる。
“いいえ”と答えると、あなたは1万円を持っていることになる」と言われます。
もしあなたが5,000円を持っていたら?
……はい、詰みです。
YesとNo、どちらを選んでも、自分の持っている金額と話が合わない。
つまり、自分で自分の首を絞めることになる。
相手は何も強制していないのに、勝手に矛盾して勝手に詰む。
この構造、めちゃくちゃ美しいです。
つまり、Yes/Noしかないように見える質問でも、ロジックを組めば第三の“動けない”を作れる。
これが今回のトリックの正体ではないでしょうか。
✅ まとめ
・Yes/Noの2択でも、矛盾を仕込めば“答えられない”を作れる。
・これは心理戦ではなく、論理の袋小路。
・5,000円だけを“動けなくする”ことで、3択が成立する。
結局、正解は?
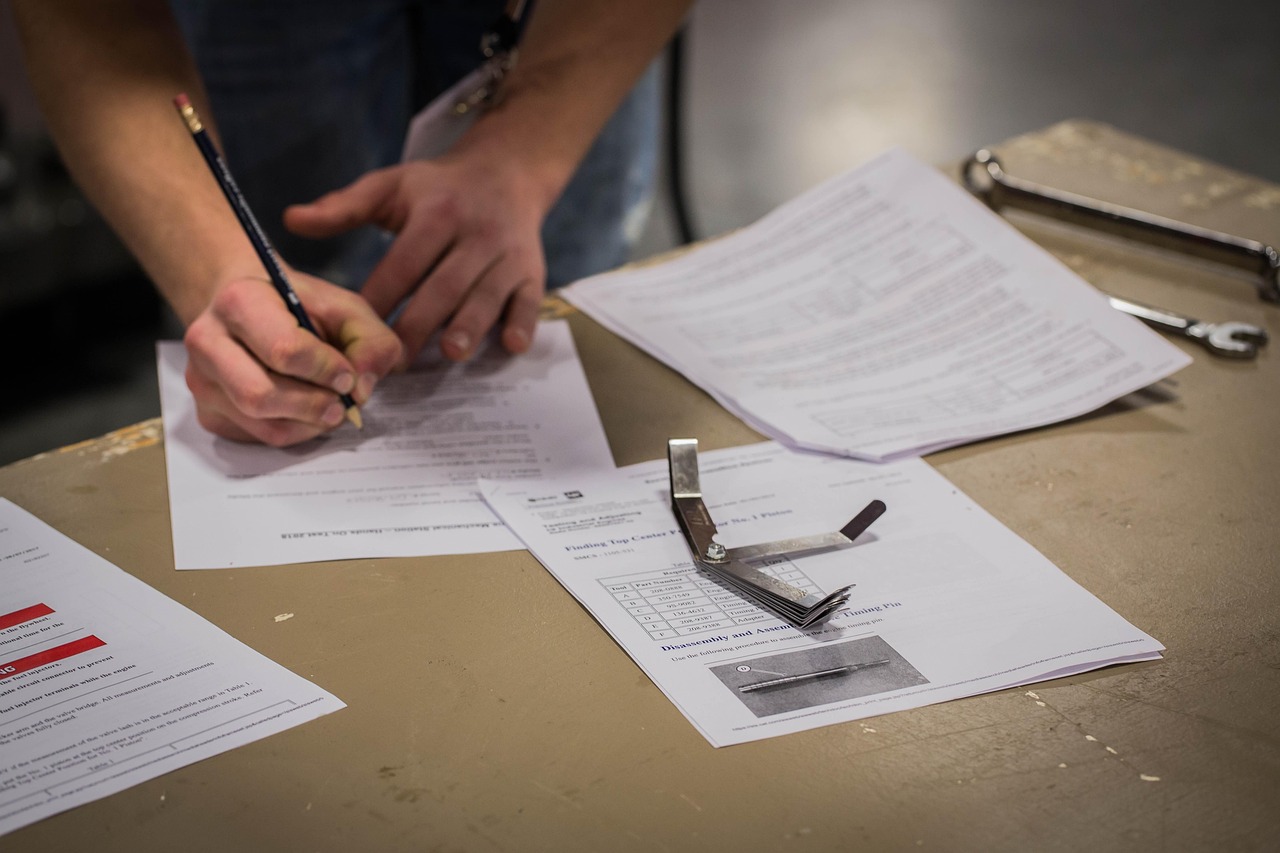
さて。
さて。
お待たせしました。
いよいよ、正解の時間です。
あれこれ考えてきましたが、使う質問はたったこれだけ。
筆者の考えた質問がこちらです。
もしあなたがこの質問に“はい”と答えるなら、
あなたは1,000円を持っている。
“いいえ”と答えるなら、
あなたは10,000円を持っている。
あなたは“はい”と答えますか?
どうでしょうか?!この質問に対しての回答は。。。
1000円の人は「はい」
1万円の人は「いいえ」
5000円の人は──
どちらを選んでも自分の足元の床が抜けます
YesでもNoでも矛盾。
だから、黙るしかない。
このトリック、出題者が何か細工したわけじゃありません。
回答者が勝手に転ぶようにできているだけです。
つまりこうです。
「はい=1000円」
「いいえ=10000円」
「黙る=5000円」
以上。
なんだか拍子抜けするほどシンプルですが、これが“非常口”の正体ではないでしょうか。
誰も非常口の場所なんて教えていないのに、勝手に踏み抜いて落ちていく。
こういうときだけ、論理は本当に性格が悪い。
でも、よくできてる。と感心してしまいました。
正解かどうか知らんけど()
✅ まとめ
・「はい→1000円」「いいえ→10000円」「矛盾→5000円」。
・第三の反応は出題者の仕掛けではなく、回答者の自滅。
・つまり、トリックは“言葉”じゃなく“構造”でできている。
応用編|逆パターン・数理条件との組み合わせ
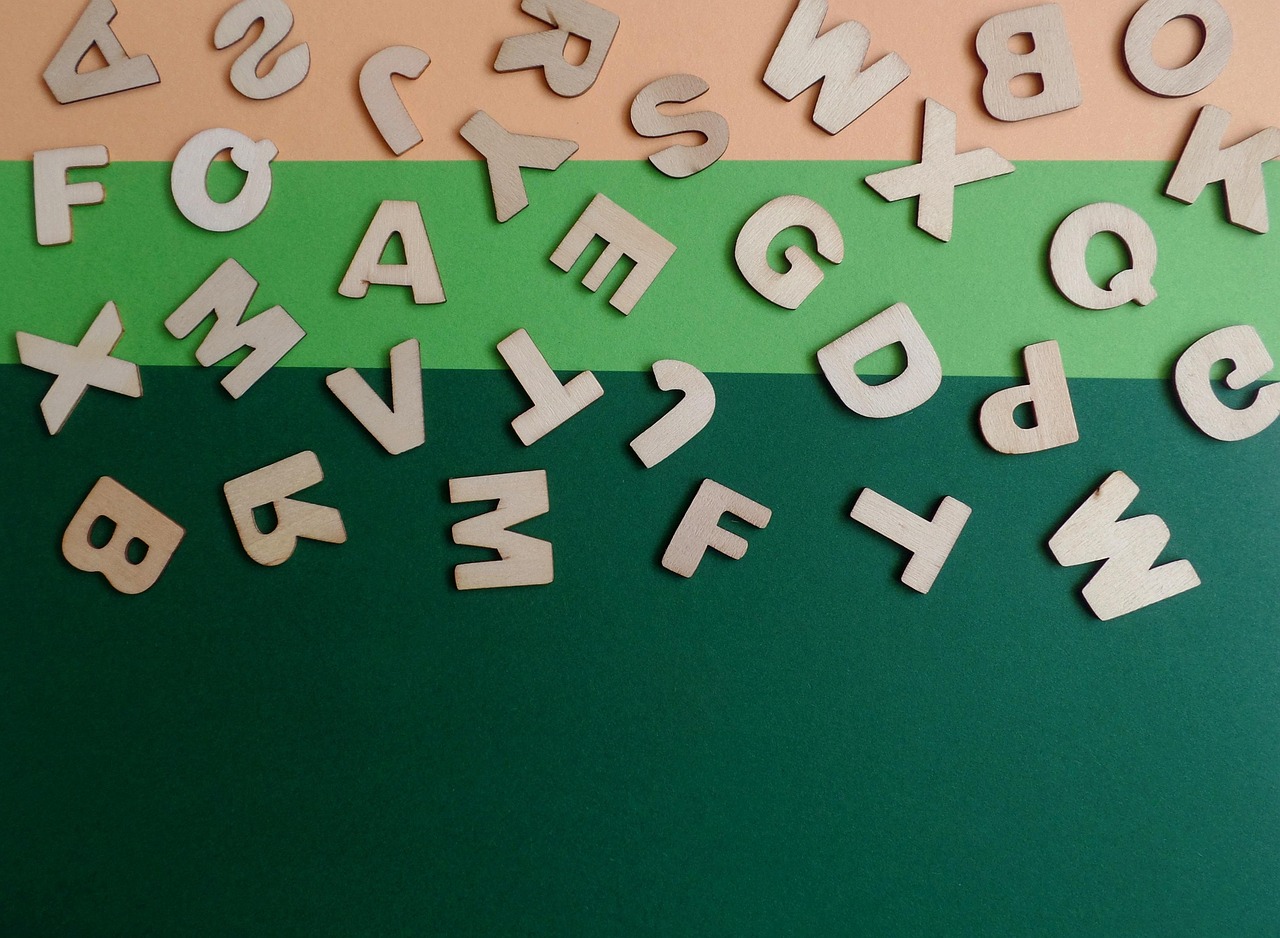
ここまでで、「はい=1000円」「いいえ=1万円」「詰み=5000円」という構図はもうできあがっています。
でも、このトリックのいいところは、ひとつじゃ終わらないということです。
ロジックというやつは、パンケーキと同じで、ひっくり返せばもう一枚焼けます。
まずは“逆パターン”。
さっきは「はい→1000円」「いいえ→1万円」でした。
これをひっくり返して、「はい→1万円」「いいえ→1000円」にしても、仕組みはまったく同じように動きます。
Yes/Noのラベルを入れ替えるだけで、出てくる沈黙の位置も、ちゃんと5000円に残る。
ロジックって、ほんとに融通が利きます。
数理条件とのハイブリッド
さらに面白いのは、ここに数理的な条件を足すパターンです。
たとえば
「あなたがこの質問に“はい”と答えるなら、あなたは5,000円より大きい金額を持っている」と仕込む。
Yesなら高額。
Noなら低額。
5000円の人は……やっぱり詰みです。
このパターン、すごく自然なんですよ。
一見、ただの金額比較をしているように見えるのに、ちゃんと矛盾の罠が仕掛けられている。
まるで「こっちが本命です」と見せかけた裏に“もう一枚の手札”があるマジシャンみたいです。
そして何より、このパターンの強みは“会話っぽく”なることです。
「1万円持ってる?」と聞くよりも、「もしあなたがこの質問に“はい”と答えるなら…」と前置きをつけると、ちょっと知的な雰囲気が出る。
飲み会で出すと、ちょっと頭よさそうに見えるやつです。
逆パターンの強み
逆パターンを使えば、Yes=1万円にもできるし、数理条件を組み合わせれば“問いかけの形”を崩すこともできます。
同じロジックなのに、見た目だけ変えて何種類も出題パターンを作れるのが、この一問トリックのいやらしい(そして面白い)ところです。
✅ まとめ
・YesとNoのラベルを逆転させても仕組みは変わらない。
・数理条件を組み込むと、より自然で“頭よさそう”に見える。
・出題パターンは無限に応用可能。
さいごに|「矛盾」を味方につける思考の力
「一問で紙幣を特定する」なんて話、最初に聞いたときは、完全に眉唾だと思っていました。
YesとNoしか答えられないのに、三択を特定する?
そんなの、数学の教科書にも載っていないし、テレビのクイズ番組にも出てきません。
だけど、よくよく考えると、人間がいちばんうまく使える武器って「答え」じゃなくて「矛盾」なんですよね。
YesとNoのあいだにある、誰も通らないはずの小さな隙間。
そこに、第三の反応──“答えられない”──を滑り込ませることで、三択はきれいに分かれました。
1000円は「はい」
1万円は「いいえ」
そして5000円は、見事に沈黙の沼へ。
この構造、ちょっとしたパズルなんですが、妙に人間らしさがにじみます。
YesとNoの世界で生きていると思っていても、実際にはその間にグレーゾーンがある。
そして、そのグレーをどう仕込むかで、世界の見え方が変わってしまう。
ロジックって、こういうときだけやけに格好いい。
数式でも心理戦でもなく、矛盾を味方につける。
この発想さえあれば、世の中の「どうせ二択でしょ」という場面も、ちょっと違って見えるかもしれません。
✅ まとめ
・Yes/Noだけの世界にも、実は“矛盾”という第三の選択肢が潜んでいる。
・一問で三択を分ける仕組みは、数字ではなく論理の構造でできている。
・ちょっとした発想の転換で、難題は案外シンプルに片づく。
※この記事は、SNSで話題になったネタをきっかけに、筆者がロジックを考えてまとめたものです。いわゆる“公式の正解”ではなく、一つの考え方としてお楽しみください。
感じ方や解釈には個人差があります。


