
「それ、僕もネットで見たけど本当なの?」

そう問われて、ハッとしたことはありませんか?
私たちは日々、インターネット上で膨大な情報に触れながら暮らしています。
しかし、うっかり信じたその情報――
実は「デマ」かもしれません。
2025年に総務省が行った調査では、過去に拡散されたインターネット上の虚偽情報について、回答者の約半数が「正しい情報だと思った」と誤認していたことが明らかになりました。
参照:Yahoo!ニュース「イワシ大量漂着は地震の前兆」ネットのデマ聞いた2人に1人信じる
SNSやニュースアプリを開けば、驚くような話が次々と飛び込んできます。
しかし、その中に紛れているのが――「デマ」や「誤情報」です。
実際、総務省の調査によると、インターネット上で拡散された誤情報を「本当だ」と信じてしまった人は全体の約半数にも上るといいます。
驚くべきは、その多くが意図的な悪意によるものではなく、誰かの「親切心」や「興味」から自然に広がってしまったという点です。
たとえば、地震の直後に拡散された「偽の救助要請」。
あるいは、「コロナウイルスはお湯で死滅する」といった医学的根拠のない話。
さらには、「地震兵器」「プラスチック米」「AIで作られた偽写真」など、信じがたい噂の多くが、一部のSNS投稿から広まり、私たちの判断力を惑わせてきました。
私は過去に、そうした情報に振り回された経験があります。自分が信じて広めたことが、実はまったくの嘘だったと知ったときの恥ずかしさと悔しさは、今でも忘れられません。
この記事は、そんな苦い失敗を繰り返してほしくないという思いで書いています。
本記事では、実際に2025年までにネット上で広まった「信じたら危ないデマ15選」を具体例とともに紹介し、その裏にある仕組みと心理、見抜くための視点を丁寧に解説していきます。
この記事でわかること
- SNS・ネットで実際に信じられたデマの具体例15選
- なぜ人は嘘を信じてしまうのか?その心理的背景
- デマを見抜くために必要な「情報リテラシー」の考え方
- 子どもや高齢者を守るために家庭でできる予防策
- 情報発信が当たり前の時代に求められる“たった一つの姿勢”
※この記事はSNS情報を中心に書かれていますが、意見や感じ方は人それぞれです。推測の域を出ず、異なる意見や見解があることも理解しておりますので、どうかご了承ください。本記事を通じて、少しでも多くの方に伝えられれば幸いです。
デマに踊らされる多くの人たち
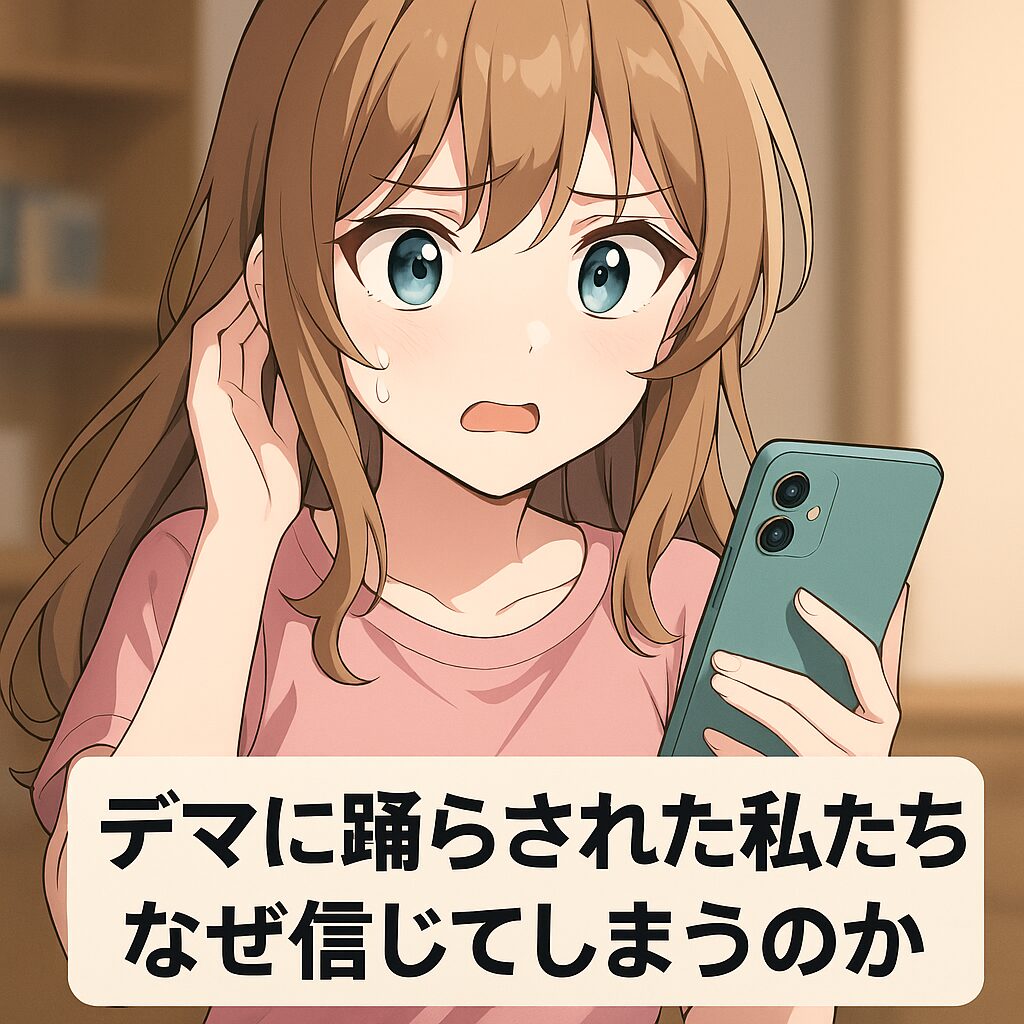
なぜデマに踊らされてしまうのか
私が初めてネット上のデマに引っかかったのは、ほんの些細な情報からでした。
「この食品を食べるとガンになる」といった見出しに驚き、家族にも「気をつけて」とLINEでシェアしてしまったのです。けれど後から調べてみると、その“情報源”は匿名のブログ。
根拠はなく、信頼できる研究も存在していませんでした。
なぜ、こんなにも簡単に「嘘」を信じてしまうのでしょうか。
答えは意外にも単純です。
それは「驚き」や「共感」が人の判断力を鈍らせてしまうからです。総務省の調査によると、デマを信じてしまった理由として「驚いた」「話のネタになると思った」「興味深かった」などの反応が挙げられています。
しかも、その拡散者の多くに“悪意”はありませんでした。自分でも「面白いからつい…」という感覚でリツイートや引用をしてしまった経験、あるのではないでしょうか。
特にSNSは、情報の「速さ」と「軽さ」が混在する場です。短文で表現された印象的な内容、拡散された数(リツイートやいいね)が信頼性に見えてしまい、冷静に裏取りをする余裕を失いがちです。
また、誰かに教えたくなるような内容や、「あの人も言っていたから」と信じる傾向が強くなることで、個人の感情や共感が先行してしまいます。
情報があふれる今、「知った気になる」ことの怖さと、「すぐ信じること」の危うさを、まず私たちは自覚する必要があるのです。
✅ 信じてしまう理由は、「驚き」「共感」「共有欲」などの感情に由来
✅ 拡散者の多くは悪意がないが、それが結果として誤情報を広げてしまう
✅ SNSの仕組みそのものが“思い込み”を助長しやすい環境を生んでいる
【事例で学ぶ】ネットで信じられた危険なデマ15選

「嘘みたいだけど本当らしいよ」――そんな言葉とともに、SNS上で信じられないような話が広まっていく。けれどその多くが、後に“デマ”として判明したケースでした。
ここでは、2025年までに実際に多くの人に信じられ、拡散された15の代表的なデマを、分野別に紹介していきます。
災害関連のデマ
災害時は情報が錯綜し、真偽の確認が困難になるため、特に誤情報が広まりやすい状況です。
- 能登半島地震での「偽の救助要請」
2024年の能登地震では、存在しない住所での救助要請がSNSで拡散。実在しない情報に救助隊が振り回されました。 - 熊本地震で「ライオンが逃げた」
2016年、動物園から猛獣が脱走したとの投稿が出回り、多くの人々がパニックになりました。 - 地震兵器説
阪神淡路大震災や東日本大震災に際して「人工地震」「陰謀論」などの投稿が拡散。科学的根拠は一切示されていませんでした。 - 静岡県の豪雨被害で別地域の画像が使用
他県の水害写真が「静岡の現状」として拡散され、混乱を招きました。
健康・医療に関するデマ
不安や恐怖心が先行する医療分野は、もっとも信じやすく、広まりやすいジャンルです。
- 「28度のお湯でコロナウイルスが死滅する」説
新型コロナの初期、「ぬるま湯で予防できる」という嘘が、LINEやSNSで広まりました。 - 「プラスチック米」騒動
栄養補助食品であるフォーティファイド・ライスが「プラスチックで作られた偽物」として紹介され、不安を呼びました。 - 「ワクチンは効かない」発言の誤解
WHO関係者が“ワクチンは無意味”と発言したかのようなデマが流れましたが、実際には発言の文脈が全く異なっていました。
社会・政治関連のデマ
信条や立場が絡むことで、感情的な拡散が加速します。
- 兵庫県知事選の候補者に関する誤情報
出所不明の情報が選挙前に拡散され、候補者の評判に悪影響を与えました。 - 専門家の発言が「切り抜き」で誤解を生む
テレビでのコメントが部分的に切り取られ、意図とは違う形で伝わった事例が多数あります。 - 「クジラやイワシの漂着=地震前兆」説
科学的な裏付けのない自然現象の解釈が、地震不安と結びつけられて拡散されました。
AI・技術関連のデマ
近年急増しているのが、AI関連の誤情報です。
- 生成AIによる「偽の白黒写真」
まるで過去の歴史を写したような画像が、実はAIによって創作されたものだったという例も出てきています。 - 偽の音声・映像が「本物」として拡散
有名人の発言に見せかけたフェイク音声や動画が「証拠」として信じられた事例も存在しました。
その他の生活関連デマ
意外にも、日常的なテーマのなかにも数多くの誤情報が紛れています。
- 「トイレットペーパーがなくなる」
コロナ初期にSNSで広まったこの噂は、実際の買い占めを引き起こす結果となりました。 - 「特定の食品が体に悪い」説
明確なエビデンスがないまま、食材への不安が拡散されることもしばしばあります。 - 「地震予知ができる」という誤情報
“この日付に地震が来る”というような投稿が拡散され、不安や混乱を煽ることがありました。
✅ 災害・医療・政治・技術などあらゆるジャンルにデマは存在
✅ 多くは信じたくなる心理を突いた内容で、信憑性を装っている
✅ 「出所」「根拠」「検証可能性」の3点で見直す習慣が必要
なぜ間違いに気づけなかったのか|デマに気づく力をつけるには?
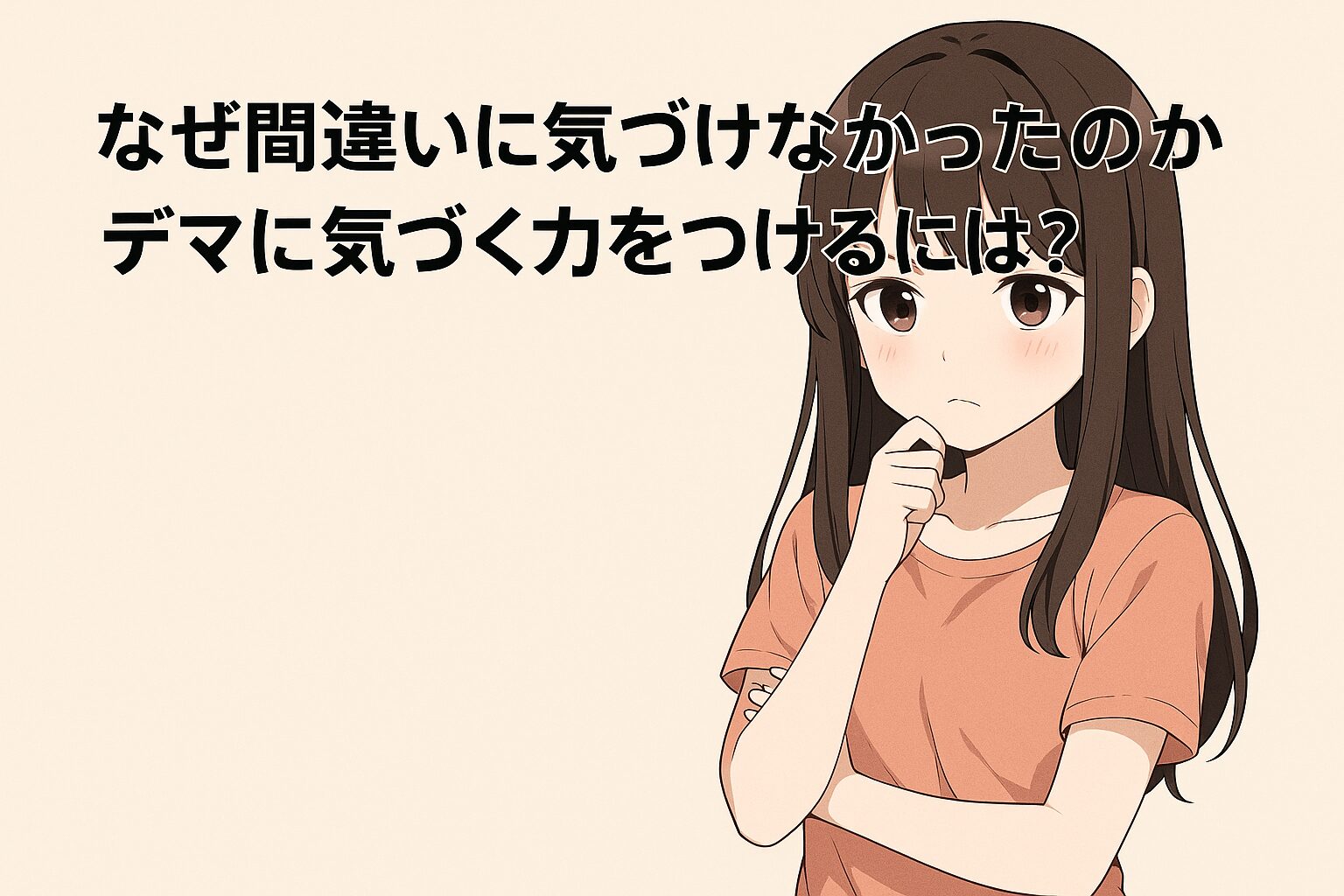
「おかしいとは思った。でも、みんな信じていたから…」
過去の私も、そう言い訳しては心のどこかで不安を打ち消していました。
けれど、その「なんとなくの空気」が、一番危険なのです。
私たちは日々、膨大な情報にさらされています。テレビや新聞だけでなく、SNSやYouTube、ブログなど、誰でも発信できる時代です。情報の入り口が増えた一方で、「正しいかどうかを自分で判断する力」は、後回しにされがちです。
しかも、意見の偏りや切り取りによる“印象操作”も珍しくありません。例えば、テレビでの専門家のコメントが意図的に編集されたり、一部だけが抜粋されて拡散されることもあります。
さらに、「その話、どこで見たの?」と聞かれても答えられないことはありませんか?
ネット上の情報の多くは、出所があいまいなまま拡散されてしまうのです。
では、どうすれば見抜けるようになるのか?
ポイントは3つあります。
- 情報の出所を確認する
公式な機関か?報道媒体か?それとも個人のSNSか?
信頼性の高い情報かどうかを見極める第一歩です。 - 複数の情報源で照合する
1つのアカウントやメディアだけを信じず、他の媒体でも同じ情報があるかを確認するクセをつけましょう。 - 「今すぐシェアしなきゃ」と思ったときほど、立ち止まる
感情が動いたときこそ、冷静な判断ができなくなる瞬間です。
こうした“リテラシー”は、大げさなスキルではなく、日々の情報の受け取り方を少し変えるだけで誰にでも身につけることができます。
デマに気づくことは「疑うこと」ではなく、「守ること」なのです。
✅ 情報は「出所・根拠・照合」でチェック
✅ SNS・テレビ・ブログも含めて偏りや誤解が起きることを前提に
✅ 感情が動いた瞬間こそ「立ち止まる勇気」が必要
子どもや高齢者こそ要注意|リテラシー教育の必要性
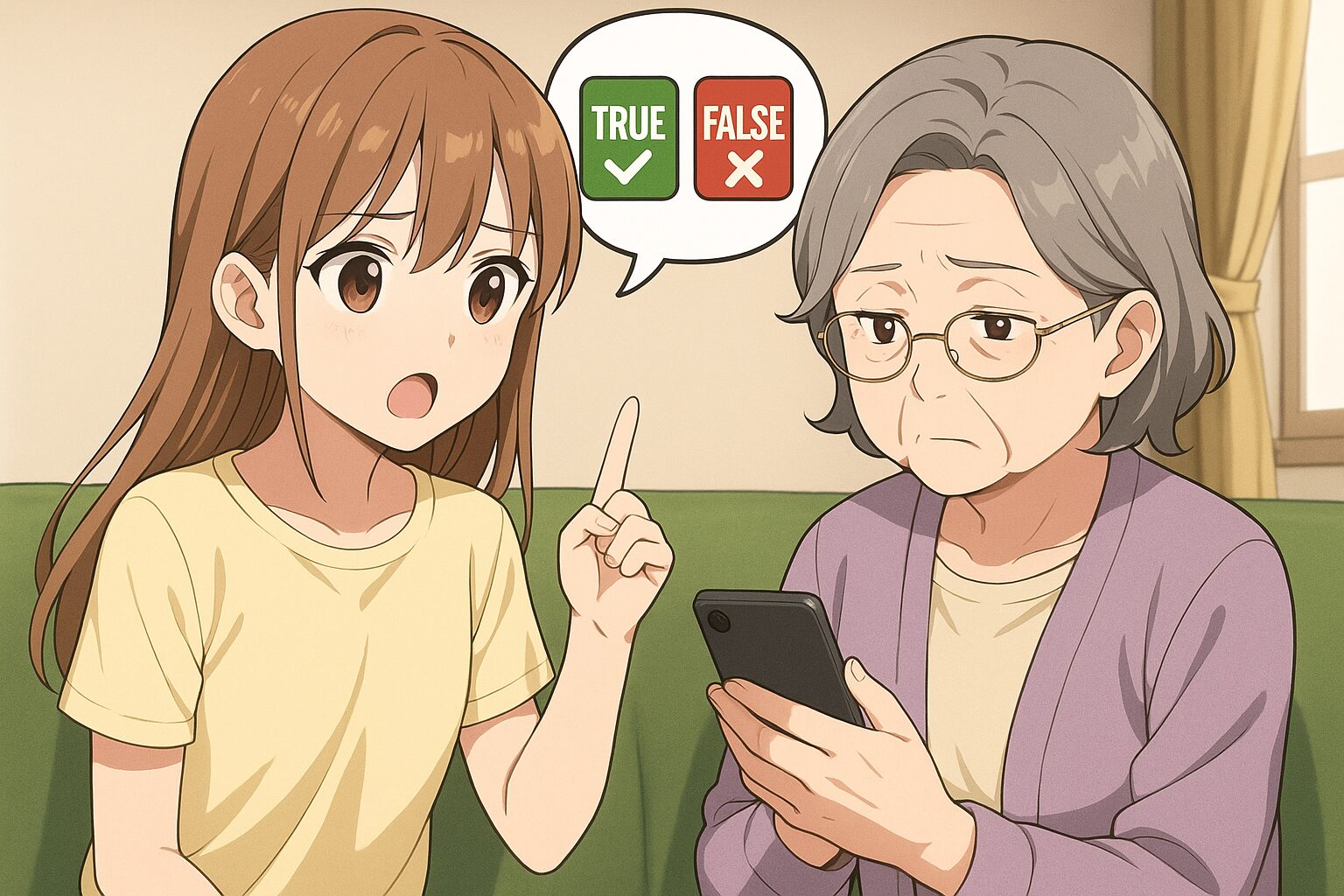
「おばあちゃん、それ信じちゃダメだよ」
そう言いながら、スマホの画面を覗き込んだ瞬間、私は自分自身も“信じやすい人間”だったことに気づきました。
ネットリテラシー――それは、いまや年齢に関係なく必要な「防御力」です。
中高年層がSNSに慣れていないという話はよく聞きます。たしかに、LINEで回ってくるチェーンメッセージや、「◯◯を食べると病気になる」といった健康情報を、親がそのまま信じて送ってくることもありました。
けれど、問題はそれだけではありません。
今や小学生でも、スマートフォンでYouTubeやSNSに触れ、情報の海に放り出されています。
そのときに「どれが正しくて、どれが嘘か」を見極める術がなければ、どうなるでしょうか?
すでに一部の大学では「情報リテラシー」の講義が設けられ、ファクトチェックの方法や誤情報の見分け方が教えられています。しかし、それは“遅すぎる”のです。
本来、スマホを持つタイミング――つまり小学生のうちから、基本的なリテラシー教育は始まるべきです。
家庭でもできることはあります。たとえば:
- 「この情報、誰が言ってるんだろうね?」と会話する
- 「テレビの情報が絶対正しいわけじゃないんだよ」と教える
- 一緒に“調べる”習慣をつけることで、信じやすい癖を防ぐ
そして重要なのは、「信じること」を責めないこと。
信じたという行為よりも、そこから「本当だったのか」を一緒に考えることが、次につながるリテラシーになるのです。
✅ 高齢者と子どもは、とくにデマの影響を受けやすい
✅ リテラシー教育は、スマホ使用の前から始めるのが理想
✅ 家庭内でもできる「情報を疑う会話習慣」が鍵となる
さいごに:誰もが情報発信者になる時代に必要な“たった1つの姿勢”
今や、誰もがスマホ一つで「情報発信者」になれる時代です。
ブログを書くまでもなく、リツイート、リポスト、引用、ストーリー――
一瞬の指先の操作で、情報は広がっていきます。
けれど、広める責任について考えたことはありますか?
私が過去に拡散してしまったのは、ある政治家に関する“疑惑”の投稿でした。
「これはひどい」と感じて、何も考えずに拡散。後にそれが完全な誤報だったと知ったとき、消せない恥と後悔に苛まれました。
私たちの「シェア」は、誰かの信頼を傷つけ、誰かの選択を左右し、時には命にすら関わることがあります。
情報リテラシーとは、知識や用語の暗記ではありません。
必要なのは、「疑う」姿勢です。
もしあなたが、ある投稿を見て「これは本当かもしれない」「みんなが言ってるから」と感じたとき。
その瞬間にこそ、立ち止まって自分に問いかけてください。
- その情報、誰が発信しているのか?
- 出典は明記されているか?
- 別の角度からも見てみたか?
「疑う」は悪ではありません。それは“正しさを探す”という誠実な行為です。
そして、これからも情報がどんどん増えていく中で、私たち一人ひとりが「鵜呑みにしない」「見抜く目を育てる」ことが、社会全体の質を高める力になります。
ほんのひと呼吸。ほんのひと手間。
その小さな判断が、きっと誰かを守ることにつながると、私は信じています。
最後に、この記事の情報を鵜呑みにしている方へ。
少しでも、、、疑いの姿勢を持ちましたか?
✅ SNS時代の情報発信には“責任”が伴う
✅ 疑うことは無責任ではなく、自分と他者を守る行動
✅ 「誰が言っているのか」を意識することが、情報リテラシーの第一歩


