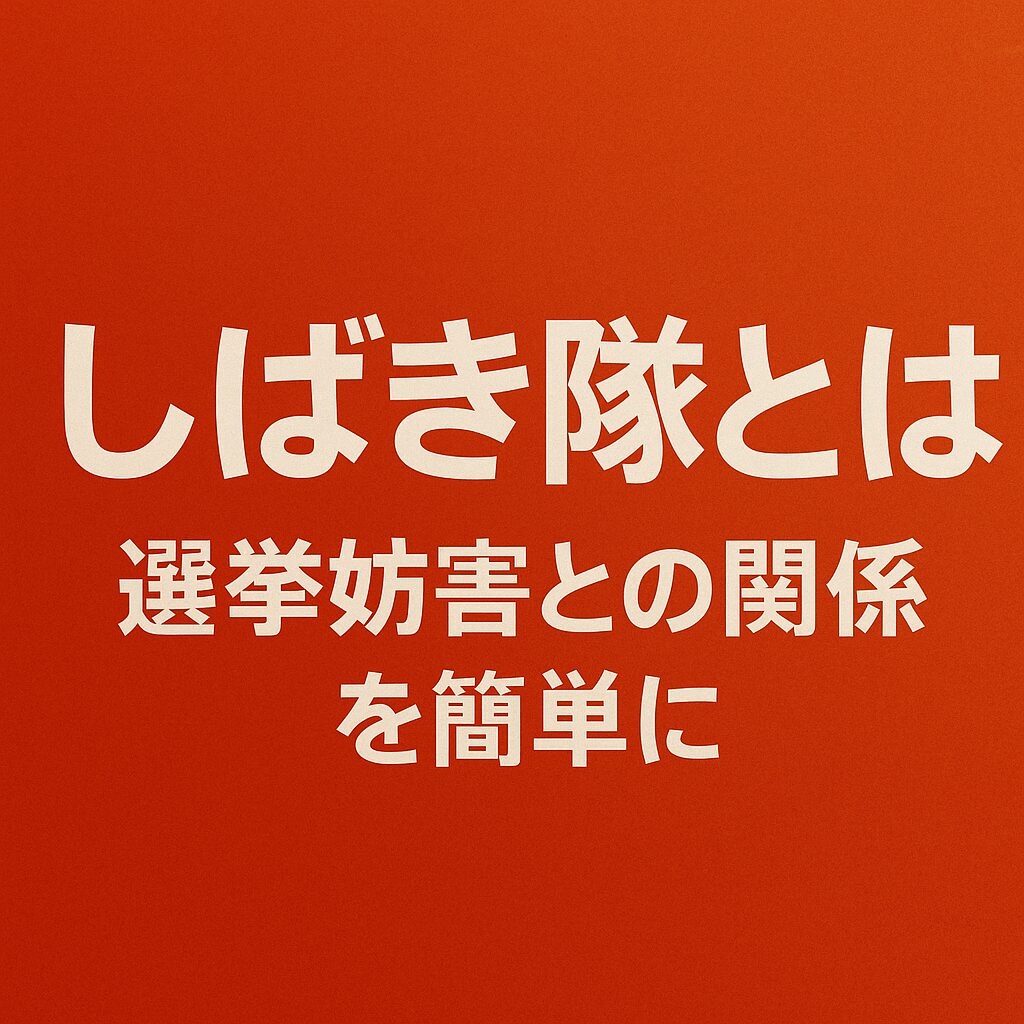2025年7月、「選挙妨害」というワードが再びSNSでトレンド入りしました。
きっかけは、ある政治団体による過激な街頭行動が、演説中の候補者や聴衆に対して過度な圧力をかけたのではないかと批判された出来事。
拡声器、怒号、追尾──そのやり方を見た多くの人が、「これはもうヤジの域を超えているのでは」と違和感を抱いたのです。
このタイミングで再注目されているのが、「しばき隊」やその後継団体である「C.R.A.C.」と呼ばれる存在です。
もともとは差別的な言動に抗議する市民運動から始まった彼らですが、SNS上では「彼らのやっていることも選挙妨害では?」とする声が強まりつつあります。
一方で、しばき隊を擁護する立場からは「これは表現の自由だ」「むしろ差別的な候補者への正当な抗議だ」との主張もあり、ネット上では議論が分断状態に。
果たして、「しばき隊」とは何者なのか? 彼らの活動は“表現の自由”なのか、“選挙妨害”なのか?
──本記事では、法的な視点と社会的反応を踏まえながら、誤解の多いこのテーマをできるだけ丁寧に整理していきます。
この記事でわかること:
- しばき隊とはどういう団体なのか?
- しばき隊の活動と選挙妨害は何が違うのか?
- ヤジと違法行為の境界はどこか?
- 2025年の最新トレンドに見る世間の受け止め方
本記事は、報道情報およびSNS上の公開投稿内容をもとに構成されたものであり、特定の団体・個人・思想を支持または否定する意図は一切ありません。記載された内容には、社会的議論のあるテーマや意見が含まれる場合がありますが、中立的な立場から、あくまで事実や論点の整理を目的として執筆しています。また、記事内で言及した団体や行動については、一般に知られた情報や過去の事例をもとにしており、すべての主張は特定の立場を代表するものではありません。もし内容に誤認や不適切な表現等がございましたら、速やかにご連絡いただけますと幸いです。読者の皆さまにおかれましても、多様な視点と冷静な理解をもってご覧いただけますようお願い申し上げます。
しばき隊とは?その成り立ちと目的
ヘイトスピーチへのカウンターとして生まれた
「しばき隊」は、2013年に突如として現れた市民運動です。
正式名称は「レイシストをしばき隊」
当時、社会的に問題視されていた在特会(在日特権を許さない市民の会)などの排外主義的なデモ活動に対し、「それに黙っていては社会が腐る」として対抗運動を展開しました。
名前こそ過激でしたが、初期には「非暴力での対抗」を掲げており、正義感を武器に世論の一定の支持を得たのも事実です。
野間易通さんの思想と過激化する行動
この運動の象徴的存在だったのが野間易通さん。
「差別は社会の毒であり、見過ごしてはいけない」という強いメッセージを持ち、拡声器やプラカードによる街頭行動、SNSでの抗議活動を通じてカウンター運動を先鋭化させていきました。
ただし、「しばき隊」という名前の“暴力的”な響きや、実際の行動が怒号や囲い込みに発展する場面も多く見られ、批判も次第に増加していきます。
現在はC.R.A.C.へと移行
しばき隊は2014年に「発展的解散」を発表。その翌日には「C.R.A.C.(クラック)」という後継団体が生まれ、現在に至るまで“しばき隊的な行動様式”はネットや街頭で散見されます。
組織というより、思想やスタイルが引き継がれているといった方が正確かもしれません。
✅ しばき隊は差別に抗議する市民運動として出発した
✅ しかし「しばく」という言葉や手段の過激さが物議を醸した
✅ 現在はC.R.A.C.や“しばき隊界隈”として形を変えて存在している
選挙妨害との違いはどこにあるのか?
法律が定める「自由妨害罪」とは?
公職選挙法 第225条(選挙の自由妨害) 4年以下の懲役または100万円以下の罰金 行為の具体例: 候補者への暴力・脅迫・つきまとい 演説妨害(ヤジ、拡声器などで妨害) 警察の目の前なら現行犯逮捕させれば良い 選挙は民主主義の根幹であり、選挙妨害はその土台を揺るがす行為として、厳しく取締れ
https://x.com/NeoMiroku/status/1941357460700397963
公職選挙法では、「候補者の演説や有権者の聴取を妨げる行為」は明確に禁じられています。
とくに225条では「自由妨害罪」として、意図的に妨害した場合に刑事罰が科される可能性があると定められています。
たとえば、拡声器を使って候補者の演説をかき消すように叫ぶ行為や、街宣車で演説を追いかけながら妨害する行為などは、妨害とみなされやすい行動とされています。
重要なのは、「言った内容」ではなく、「どのように」「どれくらいの影響を与えたか」なのです。
しばき隊の行動はなぜ誤解されやすいのか?
しばき隊やその後継団体による行動は、しばしば「カウンター」として正当化されています。
しかし、その手段が拡声器による怒号、演説現場への張り付き、囲い込みなどに及ぶ場合、結果的に候補者や有権者の自由を奪っていると見なされかねません。
また、活動が「集団」で行われることも大きな特徴です。人数が多く、声も大きく、行動が近距離であるほど、周囲への“威圧感”や“封じ込め”の印象が強くなってしまいます。
このように、「表現の自由としての抗議」と「選挙妨害としての圧力」の境界は、行動の“手段”によって容易に越境してしまうのです。
意図ではなく「手段と影響」で判断される
裁判例などでもたびたび語られているのは、「妨害かどうかは“意図”ではなく“手段と影響”で判断される」ということです。
たとえば「正義の抗議だった」と本人が主張していても、それが聴衆の妨げになり、候補者の演説が成り立たなくなるほどの行動であれば、妨害と見なされます。逆に、小声で一言ツッコミを入れる程度の“ヤジ”であれば、違法にはならないケースもあります。
✅ 公職選挙法では「候補者の演説を妨げる行為」が禁止されている
✅ しばき隊の行動は“集団・拡声器・近距離”という面で誤解を招きやすい
✅ 妨害かどうかは「手段の強度と影響の度合い」で判断される
ヤジと妨害の境界線:どこまでが“表現の自由”なのか?
判例から見えてくる「ヤジの許容範囲」
すみません。頭が悪すぎて引きますね。 シバキ隊とかネーミングもセンスないわ。 警察は、この人達の身元と誰に雇われてるのか調べ上げて公表するべきです。
https://x.com/ba0530/status/1941363806145479144
日本の司法においても、ヤジは一定程度「表現の自由」の一部として認められています。
たとえば北海道警による「ヤジ排除訴訟」では、原告勝訴の判決が確定しました。このとき、裁判所は「市民による肉声での短い批判」は公共の場における言論として保障されるべきだと判断しました。
つまり、政治家に対して不満を口にすること自体は違法ではなく、「聞こえる場所で、一定の節度を持って行われる限りにおいては許される」というスタンスが示されたのです。
しかし拡声器・追尾は“別物”
一方で、「つばさの党」が行ったように、拡声器で演説をかき消すような怒号を繰り返す、候補者を追尾して演説の場を転々と妨害する、こういった行為は「もはや一言のヤジではない」として、公職選挙法違反に問われました。
このように、“音量”“距離”“持続性”がポイントとなります。単なる感情の発露でなく、意図的かつ継続的に候補者の伝達行為を遮る形になれば、それはもはや表現の自由の範疇から逸脱してしまうのです。
「聞く権利」とのバランスが問われる時代に
忘れてはならないのが、表現の自由には「双方向性」があるという点です。候補者が政策を伝える自由と、聴衆がそれを静かに聞く権利。どちらも民主主義においては同等に守られるべきものです。
つまり、誰かが“自由に発言する”という権利を過剰に行使すれば、それは他者の“自由に聞く”という権利を踏みにじることにもなりかねません。SNSや街頭での抗議活動が可視化される現代だからこそ、このバランスをどこで取るかがますます難しくなっているのです。
✅ ヤジは「肉声・短時間」であれば表現の自由として守られる傾向
✅ 拡声器や追尾、継続的な妨害は“ヤジ”とは区別され、違法となる可能性
✅ 演説する自由と、聞く自由。その両方を守るための線引きが重要
世間の反応と今後の課題
「正義のはずが…」分かれ始めた評価
かつてしばき隊が登場した当初、「差別を許さない」というスタンスは一定の市民から歓迎されていました。とくに、ネットや街頭で横行していたヘイトスピーチに対する“実力行動”は、「黙っているよりはましだ」と肯定される空気もあったのです。
しかし、彼らの抗議活動が次第に激しさを増すにつれ、評価は大きく分かれるようになります。拡声器で怒鳴る、相手を囲む、SNSで晒すといった行動が、まるで「逆のヘイト」になっているのではと感じる人が増えはじめたのです。
特に近年は、選挙期間中の過激な“抗議”が「聞く側の自由を脅かしている」という批判も多く、彼らの存在そのものに冷ややかな視線を向ける人も増えてきました。
SNS社会が「怒り」を加速させる
SNS時代の大きな特徴は、「敵を強く叩くほど共感が集まる」という構造です。「いいね」や「リポスト」で評価されやすいのは、穏やかな対話よりも断定的で激しい言葉。それが、抗議の手段をエスカレートさせやすくしています。
しばき隊的な言動も、そうした“怒りの可視化”という現代の傾向と無関係ではありません。集団で声を張り上げたり、相手を言葉で囲い込んだりする行為が“正義”として称賛される構図が、ネット上ではしばしば見られます。
しかしそれは、民主主義的な議論の場を委縮させたり、多様な意見が交差する機会を減らしてしまったりするリスクも伴っています。
法では裁けない“倫理”の問題へ
しばき隊の行動は、すべてが違法というわけではありません。むしろ、法の枠内でギリギリを狙った行動が多く、「表現の自由」として成立するケースも少なくないのです。
ただ、その一方で「周囲がどう感じるか」という“空気の倫理”においては、徐々に否定的な目が向けられてきているのも事実です。
候補者の話が聞き取れない、子どもが泣き出す、有権者が足早に立ち去る──そうした“副次的な影響”を無視してしまえば、たとえ法に触れなくても「妨害に等しい」と見なされる空気が生まれます。
✅ かつては正義と見なされたが、今は過激すぎるという声が増加
✅ SNS時代の“怒りの可視化”が行動をエスカレートさせている
✅ 法をすり抜けても、社会的評価では“妨害”と見なされることも
さいごに
「しばき隊」という言葉が再び注目される今、私たちが本当に考えるべきなのは、“何を言ったか”ではなく、“どう言ったか”です。
差別に対する抗議や社会的不正への声は、民主主義社会において決して否定されるべきものではありません。しばき隊が掲げていた「ヘイトには声を上げるべきだ」という原点には、多くの人が共感したはずです。
しかし、時代が進み、言葉が暴力に、正義が威圧に変質しはじめたとき、その運動は本来の意義を見失ってしまいます。
演説の自由、聞く権利、抗議の表現──すべてが同時に成り立つことは、時に難しい課題です。しかしだからこそ、「どちらが正しいか」ではなく、「どのように両立させるか」が問われるべきではないでしょうか。
SNS時代における過激な言論の加速は、民主主義の根幹である“対話の場”を奪いかねません。今、必要なのは怒鳴り声よりも、静かな言葉で問いかける姿勢。しばき隊という存在がその是非とともに投げかけた課題に、私たちは冷静に向き合っていく必要があるのです。
✅ 表現の自由と選挙の自由は、どちらも守られるべき価値
✅ 強い言葉が全てを制する時代は、対話の危機でもある
✅ しばき隊という存在を通して、私たちは自由の在り方を問われている