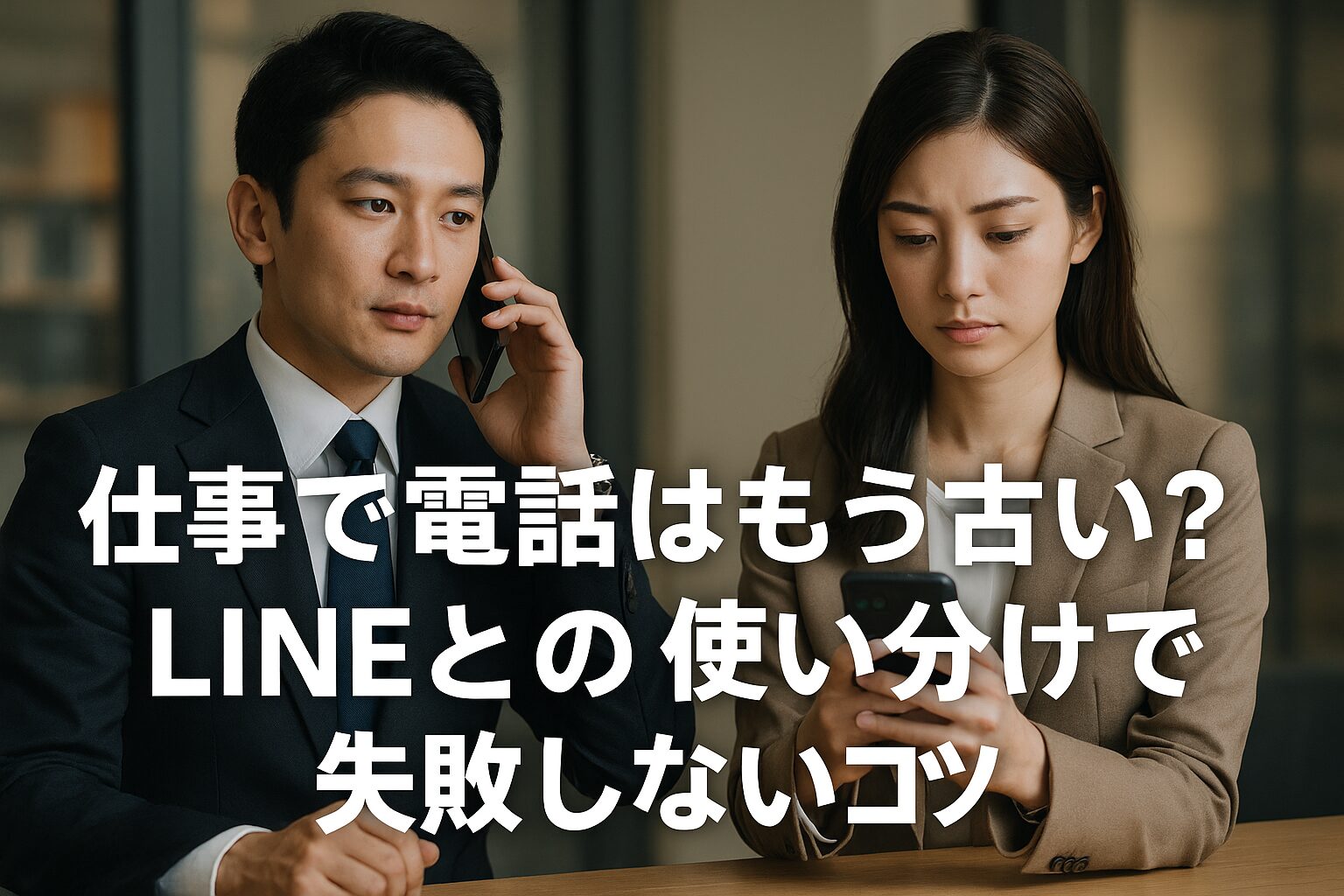なんでLINEで済む案件をわざわざ電話してくんのかね。
https://x.com/takapon_jp/status/1965696868257783962
仕事でのやり取りにおいて、
「電話を使うべきか、それともLINEやメールで十分か」
というテーマは、世代や立場を超えて議論を呼び続けています。
新人時代の私は、上司からの突然の電話に慌てて応じた経験がありました。
その一方で、集中していた作業を中断させられ、効率を大きく落としたこともあります。
こうした経験を重ねる中で、
「電話は即時性に優れるが相手の時間を奪う」
「LINEやメールは記録が残るが緊急時には不向き」
という二面性を強く意識するようになりました。
近年はSNSでも「なぜ電話をするのか」という疑問や不満が目立ちます。
一方で
「声でしか伝わらないニュアンスがある」
「確認が早い」
という電話擁護の声も根強く残っています。
つまり、どちらが正しいかではなく、状況に応じて最適な手段を選べるかどうかが重要なのです。
この記事でわかること
- 電話が嫌われる理由と、それでも支持される背景
- LINEやメールが仕事で選ばれる利点と弱点
- 若者世代と上司世代で分かれる「電話観」の違い
- TPOに応じた電話とLINEの使い分け方
※この記事はSNS情報を中心に書かれていますが、意見や感じ方は人それぞれです。推測の域を出ず、異なる意見や見解があることも理解しておりますので、どうかご了承ください。本記事を通じて、少しでも多くの方に伝えられれば幸いです。
電話が嫌われる理由と根強い支持の背景
電話の即時性と「時間を奪う」デメリット
ビジネスの現場で「電話は迷惑だ」と言われるのはなぜでしょうか。
最大の理由は、電話が相手の時間を強制的に奪うからです。
会議中や移動中、あるいは集中して作業をしているときに着信が鳴ると、どうしても対応を迫られます。
わずか数分の会話で済んだとしても、いったん集中が途切れると再び作業に戻るまでに長い時間がかかることもあります。
特にクリエイティブな仕事やIT業界の現場では「電話が一番の生産性の敵」とまで言われるほどです。
また、突然の電話は心理的な負担も大きいです。
内容が予測できないため、受ける側は身構えたり、予定外のタスクを抱えることになったりします。
その結果「電話=迷惑」というイメージが強まっていくのです。
電話を好む人が挙げる効率面での利点
一方で、電話が完全に不要かといえばそうではありません。
支持派が強調するのは「即時性」と「ニュアンスの伝達力」です。
テキストでは誤解が生じやすい場面でも、声のトーンや抑揚で感情を伝えれば一瞬で誤解を解消できます。
また、複数の事項をまとめて確認する場合や、選択肢を瞬時に比較検討する場面では電話が圧倒的に効率的です。
さらに、災害や緊急事態のように「すぐに相手の安否や意向を確認したい」ときには、テキストよりも電話の方が確実だと考える人が多いのも事実です。
つまり電話は「相手の都合を無視すれば迷惑」ですが、「状況をわきまえて使えば合理的」な手段でもあるのです。
LINE・メールが選ばれる理由
非同期コミュニケーションの安心感
LINEやメールが支持される最大の理由は
「非同期でやり取りできる」という点にあります。
相手が自分の都合の良いタイミングで読めるため、時間を強制的に奪うことがありません。
たとえば、忙しい会議中や移動中であっても、後で落ち着いたときにメッセージを確認すればよい。
受け取る側にとってはこの“猶予”が安心感につながり、心理的負担を大きく減らしてくれるのです。
また、送る側も「後で読んでもらえばいい」と考えられるため、相手に遠慮しすぎることなく連絡を取れる点も大きなメリットです。
お互いにストレスが少ないやり取りが可能になるのです。
証跡が残ることによるトラブル防止
もう一つの大きな強みは「記録が残る」ことです。
電話では、会話の内容が曖昧になったり、「言った」「言わない」で食い違いが起きたりするリスクがあります。
その点、LINEやメールならメッセージがそのまま履歴として残るため、後から見返して確認することができます。
特にビジネスの現場では、この証跡が大きな安心材料になります。
例えば納期や金額のやり取り、依頼内容の細かい条件など、誤解が致命的なミスにつながる場面では、必ずテキストを残すべきだと考える人も多いのです。
電話だけではカバーできない部分を補完する意味で、LINEやメールが重宝されているのです。
世代間で異なる価値観と「電話離れ」
若者世代が電話を避ける背景
いまの若い世代にとって、
電話は必ずしも「便利な連絡手段」ではありません。
小さな頃からSNSやチャットアプリに慣れ親しんできたため、文章でのやり取りこそが自然であり、非同期型のコミュニケーションが当たり前になっているのです。
突然の電話は、予定を崩される「不意打ち」として受け止められることも多く、心理的な抵抗感が強いと言われています。
さらに「電話に出たら、その場で即答しなければならない」というプレッシャーも、苦手意識を助長する要因です。
こうした背景から、「大切な連絡であっても、まずはテキストで送ってほしい」というのが若者世代の本音だと考えられます。
上司世代が電話を重視する理由
一方で、上司世代や長くビジネスの現場で経験を積んできた人々は
「直接話す方が早い」
「ニュアンスを正確に伝えられる」
という価値観を持ち続けています。
彼らにとって電話は「当たり前のコミュニケーション手段」であり、むしろテキストでのやり取りは「回りくどい」「誤解を生みやすい」と感じることも少なくありません。
この価値観の違いは、単なる世代間ギャップというよりも「育ってきた環境の差」が大きく影響していると考えられます。
結果として、職場では「電話をかけるのは普通だ」という上司と、「なるべくテキストにしてほしい」という部下の間で摩擦が生じやすいのです。
TPOで考える、電話とLINEの使い分け方
緊急性・即答が必要な場面は電話
急ぎの案件や、相手の判断をすぐに仰がなければならない状況では、電話が最適です。
たとえば商談中のトラブル対応や、納期直前の確認、あるいは災害時の安否確認などは、即時性が命となります。
このような場面でLINEやメールを選んでしまうと、相手が気づかないまま事態が悪化する可能性もあるため、「相手の時間を奪うことよりも、迅速な連絡を優先する」という姿勢が合理的だと言えるでしょう。
記録・確認重視ならLINEやメール
一方で、やり取りの内容を記録しておきたい場合は、テキストが強みを発揮します。
契約条件の確認、納期のやり取り、依頼の詳細など、後から「言った・言わない」で揉めやすい部分は、LINEやメールに残しておくのが安全です。
また、YES/NOで答えられる簡単な質問や、単純な依頼であれば、わざわざ電話を使う必要はありません。
相手に配慮した「ワンクッション」の習慣
どちらを選ぶにしても大切なのは「相手の都合を尊重すること」です。
例えば、急ぎの要件がある場合でも、まずはLINEで「お電話しても大丈夫ですか?」と確認を入れるだけで、受け手の印象は大きく変わります。

めめめんどくさ・・・

相手次第で応対を決めてもいいかもしれませんね
また、電話をかける際にも「今お時間よろしいでしょうか」と最初に断りを入れるだけで、相手のストレスを大幅に減らすことができます。
つまり、電話かLINEかという二択ではなく、「相手にとってどちらが負担が少ないか」を考えた上で手段を選ぶことこそが、本当のマナーなのです。
さいごに:本質は「相手の時間を尊重すること」
電話とLINEのどちらが正しいのか――この問いに明確な答えはありません。
電話には即時性と臨機応変さがあり、LINEやメールには非同期性と記録性があります。どちらにも強みがあるからこそ、状況に応じた選択が欠かせないのです。
大切なのは「自分にとって便利かどうか」ではなく、「相手にとって負担が少ないかどうか」を基準に考えることです。突然の電話にストレスを感じる人もいれば、テキストだけでは不安に思う人もいます。
だからこそ、ワンクッションを置く姿勢や、状況に応じたTPOでの使い分けが必要になります。相手の立場を思いやることができる人こそ、真のコミュニケーション能力を備えた社会人だと言えるでしょう。