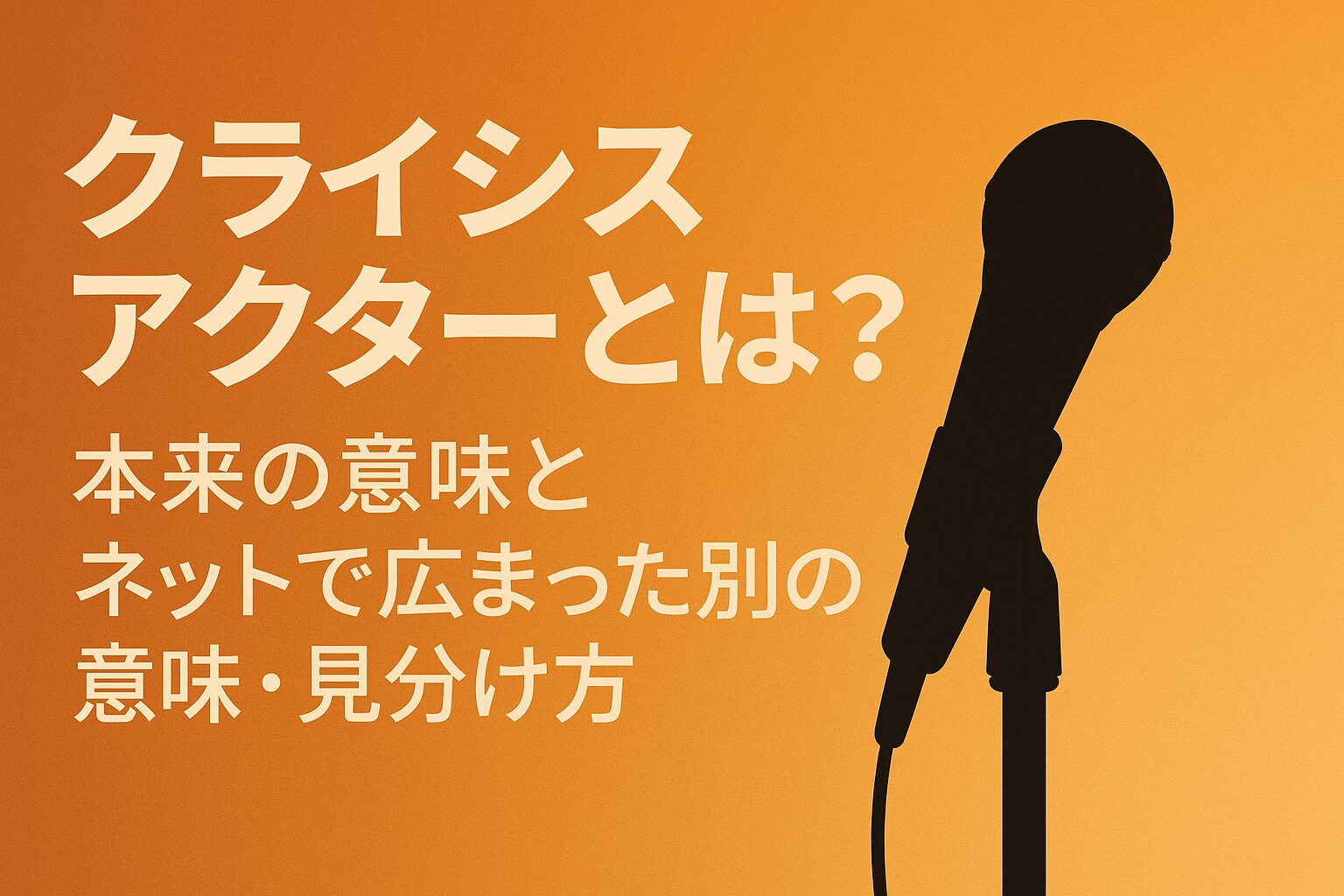近年、ニュースやSNSのコメント欄で「この人はクライシスアクターでは?」という書き込みを見かける機会が増えました。
災害や事件の証言者、街頭インタビューの一般人にまで「仕込まれた役者ではないか」と疑惑が向けられる場面もあり、、、

言葉だけが一人歩きしている印象を受けますが、クライシスアクターって前からある言葉なんですかね?

はい、昔からあったようですね。
しかし、本来まったく別の意味なようです。
クライシスアクターは、
もともとは消防や救急、警察などの訓練で「被災者役」や「混乱する群衆役」を演じる人を指す正規の用語としてあるようです。
クライシスアクター(英語: crisis actor, “actor-patient” または “actor-victim” とも)は、救急隊員や消防隊員、警察官などの訓練のため、災害・事件の被害者役として防災訓練に参加する俳優、ボランティアなどの人物のことを指す。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』クライシスアクター
訓練を実践的に行うための重要な役割として位置づけられており、本来は陰謀論や煽動的な文脈とは関係がない意味もあるそうです。
ところが近年、海外の銃乱射事件や戦争報道などをきっかけに「写っている人は雇われた役者だ」という主張が一部で広がり、そこから日本でも「クライシスアクター=演出された当事者」という意味が定着し始めました。
つまり今のネット上では、ひとつの言葉が「専門用語」と「陰謀論的な別義」の二層構造になっている状態です。
この記事では、その両方を混同しないための視点を整理してみたいと思います。
テレビ局が演者を使って印象操作するのはよくある事です。 街頭インタビューの様子を見れば分かる・・一般人はめんどくさいので近づきもしない・・あらかじめインタビューされるヒトが決まっている・・きっとクライシスアクターだね
https://x.com/TetuwanA/status/1973171973518946598
この記事でわかること
・クライシスアクターの本来の意味
・ネットで広まった別の意味とのちがい
・小泉陣営コメント依頼や奈良の鹿インタビュー論争との関連性
・決めつけやデマに乗らないための見分け方
※本記事は2025年10月時点の公的情報・報道内容に基づいて執筆しています。
また、この記事はSNS情報を中心に書かれていますが、意見や感じ方は人それぞれです。推測の域を出ず、異なる意見や見解があることも理解しておりますので、どうかご了承ください。本記事を通じて、少しでも多くの方に伝えられれば幸いです。
クライシスアクターとは?まずは本来の意味から整理する

クライシスアクターという言葉には、もともと特定の専門分野での定義があります。
消防・救急・警察・自衛隊などの訓練では、より現実に近い状況を再現するために「負傷者役」や「混乱する市民役」を配置する方法が取られています。この役を担う人たちは、訓練に協力するボランティアや、演技ができる俳優、あるいは医療や福祉系の学生など、さまざまです。
英語圏では 「Crisis Actor」や「Actor-Patient」 と呼ばれ、直訳すれば「危機対応訓練の模擬患者役」といった意味になります。
日本の自治体が公開している防災訓練要領にも、「ロールプレイング型訓練」「模擬負傷者」という記載が見られます。
つまり、クライシスアクターという言葉自体は、本来「訓練の精度を高めるための協力者」を指す中立的な用語です。

ここまでが出発点であり、陰謀論やネット論争とは別の領域にある概念のようですね。
なぜネットで別の意味が定着したのか
クライシスアクターという言葉が、日本では本来の訓練用語とは異なる意味で使われるようになった背景には、いくつかの段階があります。
クライシスアクターとは「役者を使い事件を捏造している」という陰謀論で、京王線刺傷事件や安倍元総理銃撃事件の際も顔の似た人物がいるからヤラセと騒がれ、アメリカでは小学生20人が殺害された銃乱射事件を「銃規制のためのヤラセ」と主張したインフルエンサーが約2000億円の賠償命令を受けています
https://x.com/a2487498/status/1973325192383570373
まず、海外の重大事件に関する報道映像が拡散されるたびに、
「この人物は以前にも別の現場で見た気がする」
「同じ泣き方をしている」
などの指摘がSNS上で繰り返されました。
似た顔の人物を並べた画像が投稿されることも多く、そのほとんどは角度や光の加減による錯覚とされています。
しかし、視覚情報は文字情報よりも強く印象に残るため、
「もしかすると演じているのではないか」
という疑念を抱く人が一定数現れました。
さらに、日本では昔から
「街頭インタビューは本当の一般人なのか」
「実は劇団関係者ではないか」
といった半ば都市伝説のような話が流れてきました。
実際に、演出や仕込みの有無が議論になった報道例も存在するようですが、、
こうした「違和感」や「過去の疑惑の記憶」が蓄積されることで、訓練用語であったクライシスアクターが、
いつのまにか「演出された当事者」や「仕込まれた証言者」と同じ意味で使われる場面が増えていきました。
ただし、「映像が似ている」「雰囲気が似ている」だけでは事実の証明にはなりません。
本当に検証するのであれば、登場人物の所属・公表された発言・番組側の説明など、一次資料に当たる必要があります。
疑う姿勢そのものは自然ですが、「印象での断定」と「検証にもとづく判断」は区別する必要があると言えます。
今回の件では沢山のインフルエンサーが疑惑を拡散して無垢の一般人が多くの人の悪意に晒されたにも関わらず加害者達は何ごともなかったかの様に投稿を消してマスコミを叩いている。 怒りが湧きます。
https://x.com/MonstWiz/status/1973338252238336205
クライシスアクターと“ヤラセ投稿問題”は別物
クライシスアクターという言葉は、本来「訓練の被害者役」を指す専門用語ですが、近年では「意図的に用意された発言者」「仕込まれた証言者」という意味でも使われています。

ただし、この二つの領域は明確に区別する必要があります。
訓練におけるクライシスアクター
・目的は「現場対応の精度を高めること」
・協力者は事前に了承のうえで参加している
・公的な訓練要領などにも明記されている安全な枠組み
世論や印象に関わる“演出”の問題
・発言内容を依頼したり、決まった文言を書き込ませたりするケースが存在する
・たとえば、2025年9月には政治関連の討論企画で「特定の人物を称賛するコメントを送るように依頼した」という報道があり、組織的な投稿の問題として批判されました
・これは「オンライン空間での演出」の問題であり、「現場に役者を配置した」という意味でのクライシスアクターとは別の領域にあります
たとえば上記の投稿が事実だとするのならば、
「コメントを依頼する」「発言を指示する」という行為は、意図的に世論の流れを作ろうとするものなので、仕組みとして問題視されます。
しかし、「訓練でケガ人の役をした人」や「たまたま取材に応じた一般の通行人」まで
同じように“演出された役者”と決めつけてしまうと、話がズレてしまいます。
チェックすべきは
「その人が本当に自由に発言しているのか」
それとも
「誰かから頼まれて発言しているのか」という点です。
人ではなく、“仕組み”を疑う──。
この視点を持たないと、本当に問題があるケースと、何の関係もない人を攻撃してしまうケースが混ざってしまいます。
奈良の鹿インタビュー論争
奈良の鹿をめぐるインタビュー論争では、放送直後から
「この女性、本当に現地のガイドなのか?」
「顔が作り物っぽい」
「別の番組でも見た気がする」
といった投稿がSNS上で散見されました。
きっかけとなったのは、「正体が特定できない人物に見えた」という違和感であり、そこから一部では「クライシスアクターではないか」という推測が急速に広まりました。
しかしその後、展開は意外な方向に進みます。
日テレで「奈良の鹿を蹴るような観光客は見かけない」と答えたガイドの女性がクライシスアクターなのではと炎上 ↓ 早速へずまりゅうが現地で調査、ガイドの女性は存在しないとポスト ↓ Z季がガイドの女性の会社のインスタを発見 ↓ それでもクライシスアクターと言い張る 陰謀論者たち←イマココ
https://x.com/sxzBST/status/1973186810735108589
実在を示す情報も出始めた
・ある投稿者が「インスタグラムの会社アカウントを見つけた」と報告
・「ご本人は恐怖を感じている」とする書き込みもあり、過熱を懸念する声が増加
・一方で、「それでも役者だ」と主張を続ける投稿も一部に残った
つまり、この件は 「実在の人物に対して、確証のないまま“役者扱い”が広がってしまったケース」 と言えます。
疑うことと、断定することは違う
違和感を覚えることや、「本当にそうなのか」と検証的に考えること自体は自然な反応です。
しかし、根拠が不十分な段階で
「これは演出された証言だ」
「この人物は役者に違いない」
と “断定口調”で広めると、名誉侵害や二次被害につながります。
今回のように、後から“本人は実在する”という情報が見つかることもあるため、判断を一時的に留保する姿勢が重要ではないでしょうか。

あなたはどう思いますか?
デマや決めつけに乗らないための見分け方
クライシスアクターという言葉が広く使われるようになった背景には、「何かがおかしい」と感じたときに、すぐに確証を求めたくなる心理があります。

しかし、その違和感が“検証”ではなく“断定”に変わってしまうと、無関係な人を巻き込む危険もありますよね

そこで、「疑問を持つこと」と「決めつけて拡散すること」を切り分けるための視点を整理します
1.一次情報が確認できるかを最初に見る
・番組公式ページやアーカイブが残っているか
・当事者や企業・団体が声明を出しているか
・報道機関が裏付けを取っているか
これらが存在せず、「誰かがそう言っていた」だけで進んでいる場合は、判断を保留するのが適切です。
2.「似ている」「それっぽい」は根拠にならない
画像比較や「雰囲気が同じ」という指摘は、視覚的には強い説得力を持ちます。
しかし、後から「別人だった」と判明するケースが多くあります。
似て見えることは“疑問のきっかけ”にはなっても、“証拠”にはなりません。
3.「構造」を疑うのか、「個人」を攻撃してしまっていないかを確認する
・「仕込みや演出の可能性があるのでは?」と考えるのは検証の一種
・しかし「この人は役者に違いない」「なりすましだ」と個人を指す瞬間、それは推測ではなく断定になります
批判する対象が「仕組み」から「人物」に移ったときこそ、立ち止まるサインです。
4.判断できないときは、結論を出さないという選択肢もある
「真実はこうだ」と言い切るスタイルがネットでは支持されやすい一方、
「まだ分からないので保留する」
という態度は一見弱く見えます。
しかし、長期的にはもっとも安全で、もっとも賢明な情報との向き合い方です。
この視点を持つだけで、「疑うべきものを疑いながらも、必要以上に人を傷つけないバランス」を保つことができると思います。
さいごに:疑う前に「立ち止まる技術」を持とう(改訂版)
クライシスアクターという言葉は、本来は防災や医療訓練のための中立的な用語でした。
しかし今では、報道・ネット議論・政治キャンペーンなど、まったく異なる文脈でも使われるようになり、人によってイメージが大きく異なる言葉になっています。
「違和感を抱く」「本当なのかと疑う」こと自体は、むしろ健全な反応だと言えます。
問題は、その違和感が 「検証」ではなく「断定」につながった瞬間 です。
・「似ている」から「同一人物」
・「不自然に感じた」から「やらせに違いない」
・「信じない自分は賢い」から「信じる人は愚か」
こうした連想が一気に流れてしまうと、論点が事実の検証ではなく、誰かを攻撃する方向にすり替わってしまいます。

本当に向き合うべきなのは、「演出があるかどうか」よりも、**「何を根拠に判断しているのか」**ではないでしょうか。
判断できないなら、判断を“保留する”という選択肢がある。
断定よりも保留ができる人のほうが、長期的には情報に強くなります。
クライシスアクターという言葉を見かけたときこそ、
「これは訓練の話なのか?」
「演出や仕組みの話なのか?」
「それとも、まだ何も分からない段階なのか?」
と一度だけ立ち止まれるかどうか。
その一呼吸が、デマを避けつつ、自分自身の思考も守る一番の方法になるはずです。
まとめ
Q1. クライシスアクターは本当に存在するの?
A. 訓練用語としては存在しますが、報道で登場する人物が役者と断定された事例は確認されていません。
Q2. 街頭インタビューは仕込みなの?
A. 過去に演出が疑われた番組もありますが、全てがそうだとは限りません。番組ごとに検証が必要です。