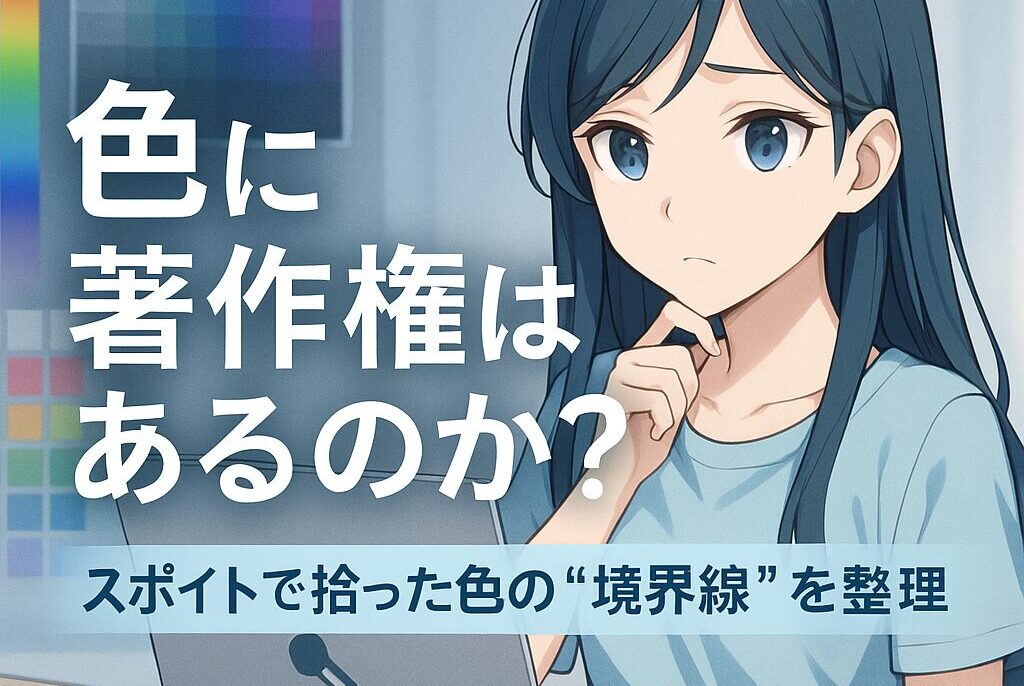夜のSNSで、ひときわ目を引く一文が流れてきました。
「色の使用料なんてあるんだ」
……あるの?
画面を見つめながら、私の脳裏にも“???”が浮かびました。
続くタイムラインでは、誰かが怒り、誰かが笑い、誰かは疲れていました。
「色にも著作権ある!」
「色トレスしたら10万円!」と主張する人が現れ、
それを見た別の人が「いや、ピーチ姫の色パクってるやん」と返す。
炎上です。
しかし同時に、誰もが一度は気になっていたテーマでもあります。
――「色に、著作権はあるのか?」
私も昔、イラストを描いていて、同じように思ったことがあります。
好きなブランドの色をスポイトで拾って、「これ、バレたら怒られるのかな」と。
そのときの私は、著作権法も商標法も意匠法も、何ひとつ知りませんでした。
ただ「この色、きれいだな」と思っただけだったのです。
でも現実はもう少し複雑で。
赤や青そのものは“自由に使える”けれど、
配色の組み合わせが長年使われて「その色=あの会社」と認識されてしまえば、
それは法律の保護対象になることがあるようなのです。ほんとか?
つまり、色は“誰のものでもない”けれど、“誰かの顔になる”ことがある。
この矛盾が、今回のSNS騒動の根っこにあります。
だからこそ、この記事ではその境界線をわかりやすく整理します。
怒る前に、笑う前に、一度立ち止まってほしいのです。
「どこまでが自由で、どこからが“誰かのもの”になるのか」。
デザイナーも、イラストレーターも、そして見ているだけの人も、この“色の法的リアリティ”を知っておくことに価値があります。
この記事でわかること
- 色そのものに著作権があるかどうか
- スポイトで拾った色の使用が違法になる場合とならない場合
- 商標・意匠・不正競争防止法の違いと関係
- 炎上を避けつつ、自分の創作を守るための基本知識
※この記事は、2025年10月時点の一般公開情報をもとにした素人(筆者)のまとめです。こういうのがあるんだ〜程度の方を対象にしています。
SNS上で話題となった議論を整理していますが、特定の個人・事案を断定的に論じる意図はありません。具体的な判断は事実関係や使用実態により異なるため、個別の相談は弁理士さん・弁護士さんにご確認ください。
色は自由財?著作権法から見た「色そのもの」の立ち位置

「赤」にも「青」にも、実は戸籍はありません。
だから、法律の世界では“無主物(むしゅぶつ)”──つまり、誰のものでもない。
これが「色そのもの」の出発点です。
とはいえ、「赤」には歴史があり、「青」には文化があります。
日本で“青信号”と言えば、実際には緑。
つまり私たちは、日常的に「色」という抽象の上で生活しているのです。
では、この曖昧な“色”が、著作権の世界ではどう扱われるのでしょうか。
著作権法はこう定めています。
「思想または感情を創作的に表現したもの」。
この文言に、“単なる赤色”や“青色”が入るかといえば──入りません。
赤は赤でしかなく、そこに思想も感情も宿らない。
つまり、「色そのもの」には著作権が発生しないのです。
“#ff0000”というコードは、世界中どこでも同じ赤。
そこに独自性を主張しても、裁判所は「自然界にある色を独占することは認められない」と判断します。
では、絵画やロゴ、UIのように“色を使った作品”はどうでしょう。
この場合、著作権の主張は「配色全体」や「構成の創作性」に及びます。
たとえば、あるイラストが「柔らかなグラデーションと透明な肌色」で評価されているなら、
その全体の表現が保護される対象です。
ただし、「肌色だけを切り取って“この色の権利だ”」という主張は成立しません。
これはちょうど、料理の世界と似ています。
カレーそのものに著作権はないけれど、
“あのスパイス配合”や“盛り付けの構成”には創作性がある。
つまり、守られるのは「味そのもの」ではなく「味の表現」なんです。
著作権法が守るのは、あくまで**「表現」であり、「要素」**ではない。
赤や青といった“要素”は自由に使ってよい。
でも、それをどう組み合わせ、どう感じさせるか──そこに人の表現が宿る。
✅ まとめ
- 単色(赤・青・緑など)には著作権は発生しない。
- 作品の一部としての色づかいは「全体の表現」の中で守られる。
- 「色」は自由財だが、「配色」は創作物になり得る。
“その色=あの会社”を示す?商標法で守られる配色の世界

「青・白・黒」の3色を見たとき、あなたの脳裏に“あの消しゴム”が浮かぶなら──
それは偶然ではありません。
トンボ鉛筆さんのMONO消しゴム。
その配色は、2017年に**「色彩のみからなる商標」として正式に登録されました。
つまり、単なる色ではなく、“長年の使用によって識別力を持った色の組み合わせ”**として法律に認められたのです。
(参考:特許庁 商標審査便覧「色彩のみからなる商標」
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/index.html)
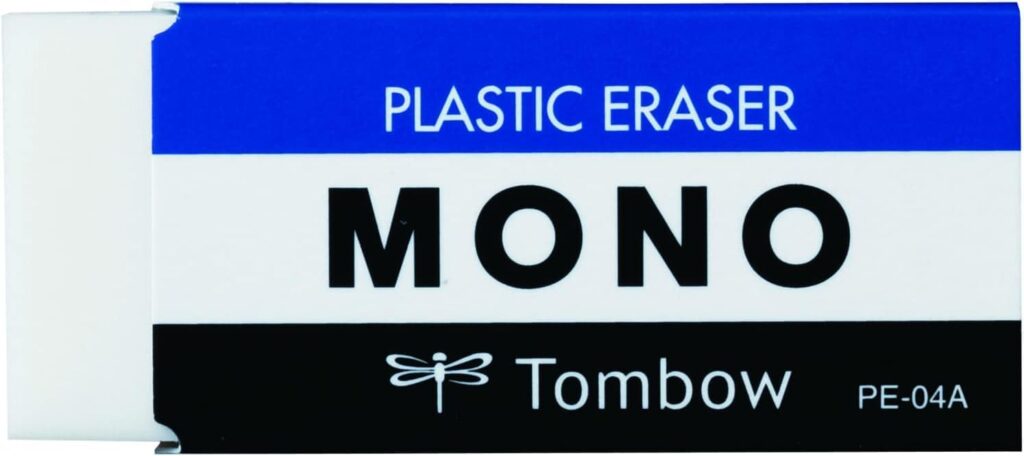
ただし、これは“誰でもできること”ではありません。
むしろ、極めて稀な例外といってよいでしょう。
商標法の目的は、「出所表示」、つまり**“この商品はどこの会社のものか”を識別できるようにすること**です。
2015年の法改正により、色だけでも出願は可能になりましたが、特許庁の審査基準では次のように定められています。
「色彩のみからなる商標は、原則として自他商品・役務の識別力を有しない」
(引用:特許庁 商標審査便覧・第54条第6項関係)
つまり、“ただの赤”や“どこにでもある青”は誰でも使える公共財。
それを「独占」することはできません。
では、どうすれば登録が認められるのか。条件は明確です。
- 長年の継続的使用によって社会に広く認知されていること
- 使用実績やアンケート調査などで“識別力”を客観的に立証できること
この2つを満たしたごく一部の企業だけが、色の商標を取得できるのです。
実例として、MONO消しゴムの「青・白・黒」配色、
セブン‐イレブンさんの「オレンジ・緑・赤」などがあります。
(出典:特許庁 商標登録例一覧
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/todokede/index.html)
ここで勘違いしやすいのが、
「登録された色=その色全体を独占できる」という誤解です。
実際の商標権は指定商品・指定役務の範囲にしか及びません。
たとえばMONO配色は文房具分野での保護に限られ、壁紙や衣類など、まったく別業種で同じ色を使っても侵害にはなりません。
この制度の本質は、「独占」ではなく「信頼の保護」です。
法律は、「色を使う自由」は誰にでもあると認めています。
ただし、その色が“長年の努力で築かれたブランドの象徴”になっている場合に限り、混同や模倣を防ぐための盾を与えているのです。
✅ まとめ
- 商標法は「創作性」ではなく「識別力(出所表示)」を守る法律。
- 「色彩のみからなる商標」は2015年に制度化されたが、登録は極めて難しい。
- 登録が認められるのは、社会的に広く認識された長年の配色のみ。
- 商標権の効力は指定分野内に限られ、すべての使用を禁止するものではない。
- 法の目的は“色の独占”ではなく、“ブランドの信用保護”である。
【一次情報・参照資料】
- 文化庁「著作権制度の概要」
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/pdf/93726501_05.pdf - 特許庁「商標審査便覧:色彩のみからなる商標」
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/index.html - トンボ鉛筆 プレスリリース「MONO消しゴムの配色が商標登録」
https://www.tombow.com/press/170301-2__trashed/ - 日本弁理士会・商標制度の解説(色彩商標)
https://www.jpaa.or.jp/knowledge/trademark-color/
意匠法・不正競争防止法:デザイン全体としての保護領域

デザインの世界において、「色」はスパイスのような存在です。
少し加えるだけで印象が変わるし、入れすぎると誰かの料理に似てしまう。
──そう、あれはまさに「カレーの隠し味理論」。
でも法律の世界では、スパイスの一粒まで記録されるほど厳密です。
たとえば「意匠法」。
これは“見た目のデザイン”を保護するための法律で、
形や模様、そして**「色彩の組合せ」**までをカバーしています。
ただし、“赤だけ”や“青だけ”では対象になりません。
意匠法で守られるのは、あくまで「全体としての外観」です。
特許庁の定義を借りれば、
「意匠とは、物品の形状、模様または色彩、もしくはこれらの結合であって、美感を起こさせるもの」
(引用:特許庁『意匠制度概要』https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/seidogaiyo/index.html)
つまり、デザインとは“赤いだけの皿”ではなく、“赤い皿の曲線と艶”まで含めての話。
色単体ではなく、“組み合わせ+構成”で一つの意匠になるのです。
しかも、2020年の法改正でこの範囲はぐっと広がりました。
これまで「物の形」に限られていた保護対象が、
建築物や内装、さらにはスマホ画面のアイコン配置など**“画像デザイン”**にも拡張されたのです。
これにより、店舗の外観やアプリのUIなど、
**“配色を含む全体デザイン”**にも法的な保護が及ぶ可能性が出てきました。
(参考:特許庁『意匠法改正(2019年施行)』
https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/seidogaiyo/isyou_kaisei_2019.html)
一方で、「不正競争防止法」はもう少し現実的です。
この法律は、“まるごとマネされた外観”から企業を守る仕組み。
たとえば、喫茶店の内装がそっくりコピーされたり、
有名アプリのUI配色がまるごと真似されたときに、
「混同を生じさせる行為」として差止請求ができることがあります。
ただし、“単一色だけ”で訴えるのはほぼ不可能です。
裁判所は「装い全体(トレードドレス)」の一体感を見ます。
つまり、“赤いソール”だけではなく、
「靴の形、材質、ブランドイメージ全体」として判断するのです。
(参考:INPIT「ルブタン・レッドソール事件評釈」
https://www.inpit.go.jp/content/100875850.pdf
要するに、意匠法も不正競争防止法も、
「色そのもの」を守る法律ではありません。
どちらも“色を含めたデザイン全体の印象”を守る仕組みです。
このあたりを誤解すると、
「赤を使っただけで訴えられる!」と慌てる人が出てくるのですが──
それは、カレーを作っただけで「スパイスの著作権だ!」と言っているようなものです。
✅ まとめ
- 意匠法は“形・模様・色彩の組み合わせ”を守る法律。
- 単色ではなく、“全体の美的構成”に保護が及ぶ。
- 2020年改正で、建築・内装・画像デザインにも対象拡大。
- 不正競争防止法は、“店舗やUIなど装い全体”を守る。
- 色単体での訴えは困難で、“トータルデザイン”としての保護が中心。
「色は単独では守られないけれど、“美しさの一部”として守られる」。
この絶妙な距離感こそが、法律のいう“デザインの自由”なんです。
“スポイトで拾う”行為は違法なのか?グレーゾーンを整理

ある夜、デザインをしていて思わず声が出ました。
「この色、天才じゃん!」
──そして、気づけば手は動いていました。
ポインタがそっとその色の上を通過し、
“ピッ”という音とともに、あなたのキャンバスへ。
……そこでふと不安になるわけです。
「これ、もしかして……アウト?」
まず最初に知っておきたいのは、
**「スポイトで色を拾う行為そのものが、直ちに違法とされるケースは確認されていない」**という点です。
ただし、これは「常に問題がない」という意味ではありません。
法律の判断は“状況”で変わります。
拾った色の使い方、文脈、そしてその色に“ブランドの識別力”があるか──
これらが重なった場合、別の法律(商標法や不正競争防止法など)が関係してくる可能性があります。
たとえば、有名企業が長年使い続けてきた配色(例:トンボ鉛筆さんのMONOカラーや、セブン‐イレブンさんの看板色など)。
こうした配色は**「色彩商標」として登録されていることがあり、
同業界で似た使い方をすると、“混同のおそれ”**と判断されることがあります。
ただし、商標権の効力は“指定された分野内”に限られます。
文房具の配色を服のデザインに使っても、
すぐに法的責任を問われるわけではありません。
(参照:特許庁 商標審査便覧)
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/index.html
また、最近増えているのが「偶然似た色」問題。
AIツールやパレット生成サイトが普及した結果、
他人の作品に“結果的に似てしまう”ケースも増えています。
この場合、意図的に似せたと判断されない限り、法的問題に発展する可能性は低いと考えられます。
ただし、SNS上では“似ている”というだけで誤解や炎上が起こることもあるため、
法律上のリスクよりも**「印象のリスク」**の方が実は大きいのです。
つまり、スポイトの問題は、
“違法・合法”という二択ではなく、**「文脈依存のグラデーション」**です。
色そのものは自由。
けれど、その色に誰かの努力や信頼が宿っているとき、
そこには“法律”ではなく“敬意”という線引きがある。
✅ まとめ
- スポイトで色を拾う行為が「直ちに違法」とされる事例は確認されていない。
- ただし、色の使い方によっては商標法・不正競争防止法の判断対象になる可能性がある。
- “意図的に似せた”場合や、ブランド識別性のある配色を同業種で使う場合は要注意。
- 法的リスクだけでなく、「印象面での炎上リスク」にも配慮が必要。
- 判断に迷う場合は、弁理士さんや弁護士さんへの相談が確実。
スポイトツールは悪魔の道具ではありません。
ただ、**「どこからが真似で、どこまでが学びか」**を考えるきっかけにはなる。
それを意識するだけで、創作の世界はずっと自由で、ずっと優しくなります。
さいごに
色の世界は、思っていたよりも広くて、そして静かです。
私たちはその中で、日々ちょっとした“選択”をしています。
赤を使うか、青にするか、どんなグラデーションでまとめるか。
その小さな判断の積み重ねが、作品の「顔」を作っていく。
今回のSNS騒動をきっかけに、
「色にも著作権があるのか?」という問いが一気に広まりました。
けれど、結論として見えてくるのは、
色そのものには著作権は基本的に認められないという原則です。
ただし、色が組み合わさって「配色」になり、
それが長年の使用で“あの会社らしさ”を帯びてくると──
商標法や不正競争防止法がそっと肩を貸してくれます。
つまり、法律は「努力で生まれた色」を守る仕組みを持っている。
けれど、同時に「創作の自由」も奪わないよう、慎重に線を引いているのです。
スポイトツールは、その線を見極めるための“レンズ”みたいなものです。
人の色をそのまま使うこともできるし、
そこから学んで自分の色を育てることもできる。
使い方ひとつで、盗用にも、創造にもなる。
法律は、その行為を“意図”で見ています。
だからこそ、結局のところ「どう使いたいか」を問われているのは、私たち自身なんです。
赤も青も、誰のものでもない。
でも、“誰かが育てた赤”には、努力と時間が染み込んでいる。
それを見つめて、敬意をもって離れていくこと。
その一歩が、クリエイターとしての矜持なのかもしれません。
✅ 本記事のまとめ
- 色そのものは著作権の対象外。
- ただし、配色や外観全体は、商標法・意匠法・不正競争防止法で保護され得る。
- スポイトで拾う行為は違法ではないが、使い方次第で法的・社会的リスクが変わる。
- 一番大事なのは、“法”よりも“リスペクト”。
- 色を「奪う」より、「自分の色を育てる」ほうが、ずっとかっこいい。
本記事の参照情報(出典整理)URL一覧
- 文化庁「著作権制度の概要」
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/pdf/93726501_05.pdf - 特許庁「商標審査便覧:色彩のみからなる商標」
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/index.html - トンボ鉛筆 プレスリリース「MONO消しゴムの配色が商標登録」
https://www.tombow.com/press/170301-2__trashed/ - 特許庁「意匠法改正(2019年施行)」
https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/seidogaiyo/isyou_kaisei_2019.html - INPIT「ルブタン・レッドソール事件評釈」
https://www.inpit.go.jp/content/100875850.pdf
このテーマは、答えが一つではありません。
けれど、「誰かの努力を奪わないように」「自分の色を見失わないように」という心だけは、
どんな時代にも共通するルールだと思うのです。
※
本記事は、2025年10月29日時点で公開されている公的資料や専門家解説をもとに、一般的な情報提供を目的として執筆したものです。
記載内容は、著作権・商標・意匠・不正競争防止法などの概要を整理したものであり、特定の事案に対して法的判断を行うものではありません。
法令の解釈や適用は、個々の事実関係や利用目的によって異なる場合があります。
実際の対応・判断を行う際は、必ず弁理士さん・弁護士さんなどの専門家にご相談ください。
本記事および運営者は、記事の内容に基づいて行われた行動や判断に関して、
いかなる損害・トラブル等についても一切の責任を負いません。
また、本記事内の説明・図版・AI生成画像はすべて参考表現であり、
特定の企業・団体・個人・ブランドを誹謗・中傷・模倣する意図はございません。
内容の正確性・最新性については十分に確認しておりますが、
法改正その他の理由により、後日内容が変更される可能性があります。
最終的な判断および行動は、必ずご自身の責任でお願いいたします。