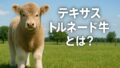芸能人スキャンダルや暴露問題が溢れ賑わう昨今
2025年9月6日、フォロワー40万人超を抱える暴露系アカウント
「DEATHDOL NOTE」さんが
「大手芸能事務所6社と裁判準備に入る」
と宣言し、同日0時をもって鍵アカウントへ移行すると投稿して話題になっています。
瞬く間に2000万を超えるインプレッション
多くの人々が「ついに暴露アカウントが法廷に立たされる時代が来たのか」と注目しているようです。
その一方で、多くのユーザーが口にしたのは
「なぜ週刊誌の暴露は許されるのに、SNSの暴露は危険なのか?」
という素朴な疑問でした。
確かに、どちらも芸能人や著名人のスキャンダルを取り上げている点では共通しています。
しかし、その扱いには明確な差が存在するのです。
本記事では、名誉毀損の法的な枠組みから、週刊誌とSNSの構造的な違い、そして「暴露」が社会的にどう受け止められているのかまでをまとめてみました。
SNS時代における「個人発信の限界」とは何なのでしょうか。
この記事でわかること
- 週刊誌とSNS暴露は法律上どう違うのか
- 週刊誌は続けられてSNSがリスクを抱える理由
- 公益性や真実性が問われる背景
- SNS暴露が「報道」ではなく「ショー」として受け止められる要因
- 発信者がこれから意識すべき責任とリスク管理の重要性
※この記事はSNS情報を中心に書かれていますが、意見や感じ方は人それぞれです。推測の域を出ず、異なる意見や見解があることも理解しておりますので、どうかご了承ください。本記事を通じて、少しでも多くの方に伝えられれば幸いです。
週刊誌とSNS暴露は何が違うのか
法律上は同じ「名誉毀損」
まず押さえておきたいのは、
週刊誌もSNSも法律上の扱いは同じだという点です。
名誉毀損とは「他人の社会的評価を下げる表現」を指し、刑法・民法の双方で責任が問われます。
つまり、発信の場が雑誌であれSNSであれ、相手が訴えれば裁判になる可能性があるのです。
実際、週刊誌が芸能人に訴えられ、敗訴して賠償金を支払った例は珍しくありません。
ここだけを切り取れば「週刊誌が特別に守られているわけではない」といえるでしょう。
名誉毀損とは「他人の社会的評価を下げる表現」を指し、刑法230条1項では「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は処罰される」と定められています。さらに、民法709条の不法行為規定に基づき、損害賠償を請求されることもあります。
実務上の体制と公益性
しかし大きな違いは「リスクを取る体制の有無」です。
週刊誌には編集部、法務担当、校閲部があり、記事化の段階で「この内容は公益性があるか」「真実性を立証できるか」を検討します。
リスクを織り込んだ上で、発行部数や広告収入によって損失を補える体制が整っているのです。
一方、SNSで暴露を行うのは多くの場合が匿名の個人です。
裏付け資料も提示されにくく、公益性を立証することは極めて難しい。
結果として「報道」ではなく「私的な晒し」と判断されやすくなります。これが、同じスキャンダルでも週刊誌とSNSで大きな差が生まれる理由です。
週刊誌には編集部、法務担当、校閲部があり、記事化の段階で 刑法230条の2 に基づく「公共の利害に関する事実」「公益を図る目的」「真実性の証明」――この3要件をクリアできるかを吟味します。
ジャーナリズムとの線引き
週刊誌は調査報道の形式をとり、証言や資料を積み重ねることで「真実性」を証明する準備を整えています。
これはまさに刑法230条の2が要求する立証作業に直結しています。
一方、SNSでは「公益性」「真実性」を主張するだけの裏付けが不十分なケースが多く、社会的にも「報道」ではなく「ショー」として消費されやすいのです。この点が、両者の決定的な違いといえるでしょう。
DEATHDOL NOTEが直面した現実
【ご報告】 この度、大手芸能事務所6社と 裁判の準備に入るため、 本日0:00にXを鍵アカウントにします。 フォロワーの皆様にはご不便をおかけしますが、 何卒よろしくお願いいたします。 DEATHDOL NOTE 代表
https://x.com/DEATHDOL_NOTE/status/1964173602896695429
裁判準備の宣言が示すもの
「暴露系アカウントの代表が自ら裁判準備を宣言する」――この行為自体が異例でした。
通常であれば訴訟に向けた準備は水面下で進めるものです。
しかし「DEATHDOL NOTE」さんは公に宣言。
フォロワーの間では「まるで観客に向けたパフォーマンスのようだ」と受け取る声も少なくありませんでした。
この点は、SNSという舞台の特性を映し出しています。
フォロワー数が多ければ多いほど、情報発信は「報道」であると同時に「コンテンツ」になってしまう。
宣言の真意は定かではないにせよ、「法廷に立つ暴露者」という構図そのものがひとつのエンタメ的消費対象となってしまったのです。
SNS暴露と社会的影響力
かつては、大きな社会的影響を与えるのは新聞社やテレビ局のような組織に限られていました。
しかし今や、SNSの個人アカウントでも数十万規模の拡散力を持てる時代です。
「DEATHDOL NOTE」さんは、週刊誌以上の速さで情報を届ける力を持ちながら、リスクを負うのはあくまで個人一人。
そのアンバランスさこそが今回の問題を象徴しているといえるでしょう。
ここで重要なのは、「影響力を持つ=責任も同等に重くなる」という現実です。
組織ならば法務部や編集部がその責任を分散しますが、個人には逃げ場がありません。
だからこそ、同じ「暴露」であっても週刊誌とSNSの扱いに差が生まれるのです。
暴露が「報道」ではなく「ショー」となる理由
情報の受容のされ方
SNSで拡散される暴露は、単なるニュースとして消費されるのではなく「炎上コンテンツ」として楽しむ形に変化しやすい特徴があります。
今回のDEATHDOL NOTEさんの件でも、「裁判に挑む暴露者」という構図自体が、まるで物語の一幕のように受け止められました。
「本当に訴えられるのか?」
「どんな展開になるのか?」
――ユーザーは事実の真偽よりも、ストーリーとしての面白さを追いかける傾向が強いのです。
そのため、発信内容の社会的意義よりも、スキャンダルが“エンタメ化”されることが多くなります。
ジャーナリズムとの線引き
週刊誌は調査報道という形を取り、資料や証言を集めて「公益性」を前面に出します。
ところがSNSの暴露は、多くが根拠不明の投稿にとどまりやすく、公益目的よりも「話題性」や「注目」を優先しがちです。
その結果、社会的な受け止め方も「報道」ではなく「ショー」として片付けられてしまうのです。
この違いこそが、週刊誌とSNS暴露の最大の差と言えます。つまり、法的な枠組み以上に「受け止められ方」が両者を大きく隔てているのです。
これからの個人発信者が抱える責任
発信力と責任のアンバランス
SNSが広がったことで、かつてはメディア企業にしか持てなかった拡散力を、個人も簡単に手に入れられるようになりました。フォロワー数十万人という規模は、もはや小さなテレビ番組や雑誌に匹敵します。
しかし、影響力に比例して責任も大きくなるのが現実です。週刊誌ならば法務部や編集部がリスクを分担できますが、個人の場合は訴えられればすべてを自分一人で背負うしかありません。今回の「DEATHDOL NOTE」さんの裁判準備は、そのアンバランスさを象徴する出来事だったといえるでしょう。
今後の発信に必要な姿勢
もし自分が発信者として情報を広める立場になったとき、何を意識すべきでしょうか。大切なのは「裏付け」と「公益性」です。どんなに衝撃的な情報でも、証拠や正確な調査なしでは単なる噂や私怨とみなされてしまいます。逆に、資料や信頼できる証言を基にすれば、報道としての説得力が増します。
SNSの民主化は、多くの人に発信の自由を与えました。しかし同時に、「誰もが責任を負う時代」を開いたのです。暴露という行為に限らず、発信力を持った個人は常に「この情報を届けることが社会的に正しいのか」を自問する必要があるでしょう。
さいごに
「DEATHDOL NOTE」さんが示した裁判準備の宣言は、単なるSNSの一幕ではありませんでした。それは、個人発信が社会に与える影響力と、その背後に潜む責任の重さを可視化する出来事だったのです。
週刊誌とSNS暴露は法律上は同じ土俵に立っています。しかし実務上の体制、公益性の立証、そして社会からの受け止められ方に大きな違いがあることで、結果的に「週刊誌は許され、SNSは危険」という構図が生まれています。
本質的な問いは、「発信力を持った個人がどこまで社会的責任を背負えるのか」という点に尽きます。誰もが情報発信者になれる時代だからこそ、その一言が誰かの人生を変える可能性を常に意識しなければなりません。
あなたがもし数万人、数十万人に届く言葉を持ったとしたら――その瞬間、週刊誌の記者と同じ責任を負えるでしょうか? この問いこそが、今回の出来事が私たちに残した最大の課題なのだと思います。