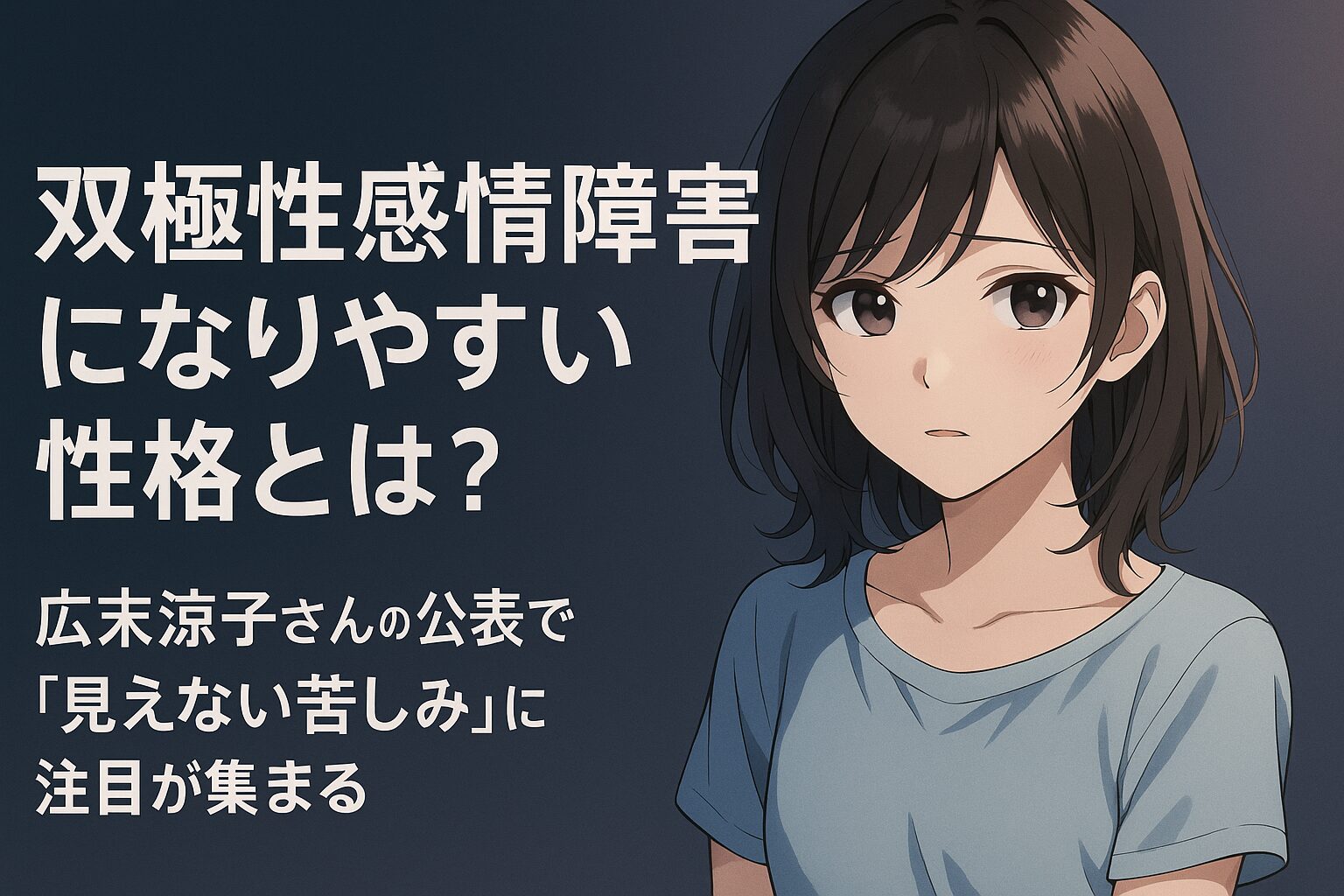双極性感情障害──
かつて「躁うつ病」とも呼ばれていたこの精神疾患は、社会的な誤解や偏見の影響を受けやすく、見た目では判断できない“見えない苦しみ”を抱える病気です。2025年5月、女優の広末涼子さんが自身の診断名としてこの病名を公表したことで、注目が一気に高まりました。
広末さんのような著名人が病を公表する背景には、多くの勇気と覚悟があります。しかし一方で、その公表を「責任逃れだ」「言い訳ではないか」と決めつける声もネット上にあふれました。ですが、本当に注目すべきはそこではなく、「これを機に理解が進むかどうか」ではないでしょうか。
双極性感情障害は、単なる気分の波ではありません。躁状態では活動的で明るく見える一方、自尊心の肥大や攻撃性、判断力の低下なども伴います。そしてその反動として、深刻な抑うつに陥ることもあります。「なりやすい性格傾向がある」と語られることもありますが、それは決して“弱さ”を意味するものではありません。
本記事では、広末さんの公表をきっかけに、双極性感情障害の基本情報、なりやすい性格傾向、社会との関わり方などを、経験者の視点から丁寧に解説していきます。
この記事でわかること:
- 双極性感情障害とは?うつ病との違いや特徴
- なりやすい性格傾向にある人とは?自己チェックの視点
- 広末涼子さんの診断公表が話題になった背景と影響
- 社会がこの病気とどう向き合うべきか
※この記事はSNS情報を中心に書かれていますが、意見や感じ方は人それぞれです。推測の域を出ず、異なる意見や見解があることも理解しておりますので、どうかご了承ください。本記事を通じて、少しでも多くの方に伝えられれば幸いです。
双極性感情障害とは?うつ病との違いと社会的な誤解
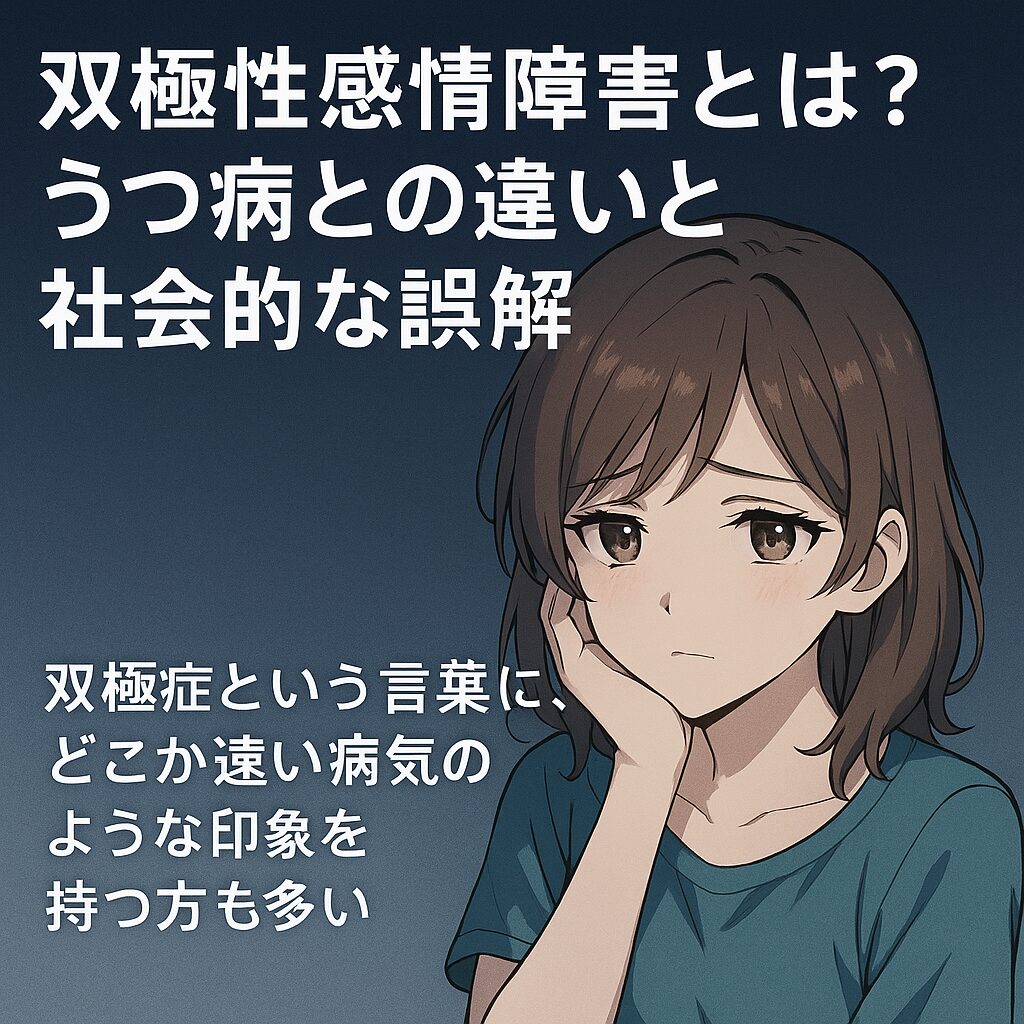
双極性感情障害という言葉に、どこか遠い病気のような印象を持つ方も多いかもしれません。しかし、これは決して他人事ではない精神疾患のひとつであり、現代社会を生きる私たちにとって、理解が急務となっているテーマのひとつです。
この病気の特徴は、気分が極端に高揚する「躁状態」と、深い落ち込みに沈む「うつ状態」を交互に繰り返すことにあります。多くの人が知っている「うつ病」が“落ち込んだ状態”のみを指すのに対し、双極症では“過活動”に見える躁の時期も存在します。ここが大きな違いであり、また誤解を生む要因でもあるのです。
たとえば、躁状態の時には、本人は非常に元気そうに振る舞い、次々と物事をこなしたり、極端に外向的になったりします。睡眠時間が極端に減っても疲れを感じず、自己評価が過剰になったり、過度な買い物や人間関係のトラブルを引き起こすこともあります。これだけ見ると、「元気で活動的な人」と思われることすらあり、実際に病気だと気づかれにくいのが現実です。
筆者もかつて、ある人のあまりにエネルギッシュな行動に憧れのような気持ちを抱いていた時期がありました。ところが、その人は後に深刻な抑うつ状態に陥り、全ての活動を中断せざるを得なくなったのです。私はその時、ようやく「躁」と「うつ」の関係性の重さを知りました。
こうした「好調に見える時期」が存在するからこそ、周囲も本人も治療の必要性を見逃してしまう──それがこの病気の怖さであり、見えにくさなのです。そしてその見えにくさが、「甘え」や「気の持ちよう」といった心無い言葉につながり、本人をさらに追い詰めていきます。
双極性感情障害は、医学的にしっかりと認識されている疾患であり、適切な治療とサポートによって、安定した生活を取り戻すことは可能です。まずは「誤解しないこと」「正しく知ること」──そこから始めるのが、支える側の第一歩になるのではないでしょうか。
どんな性格の人がなりやすい?──経験者の声から見えた傾向
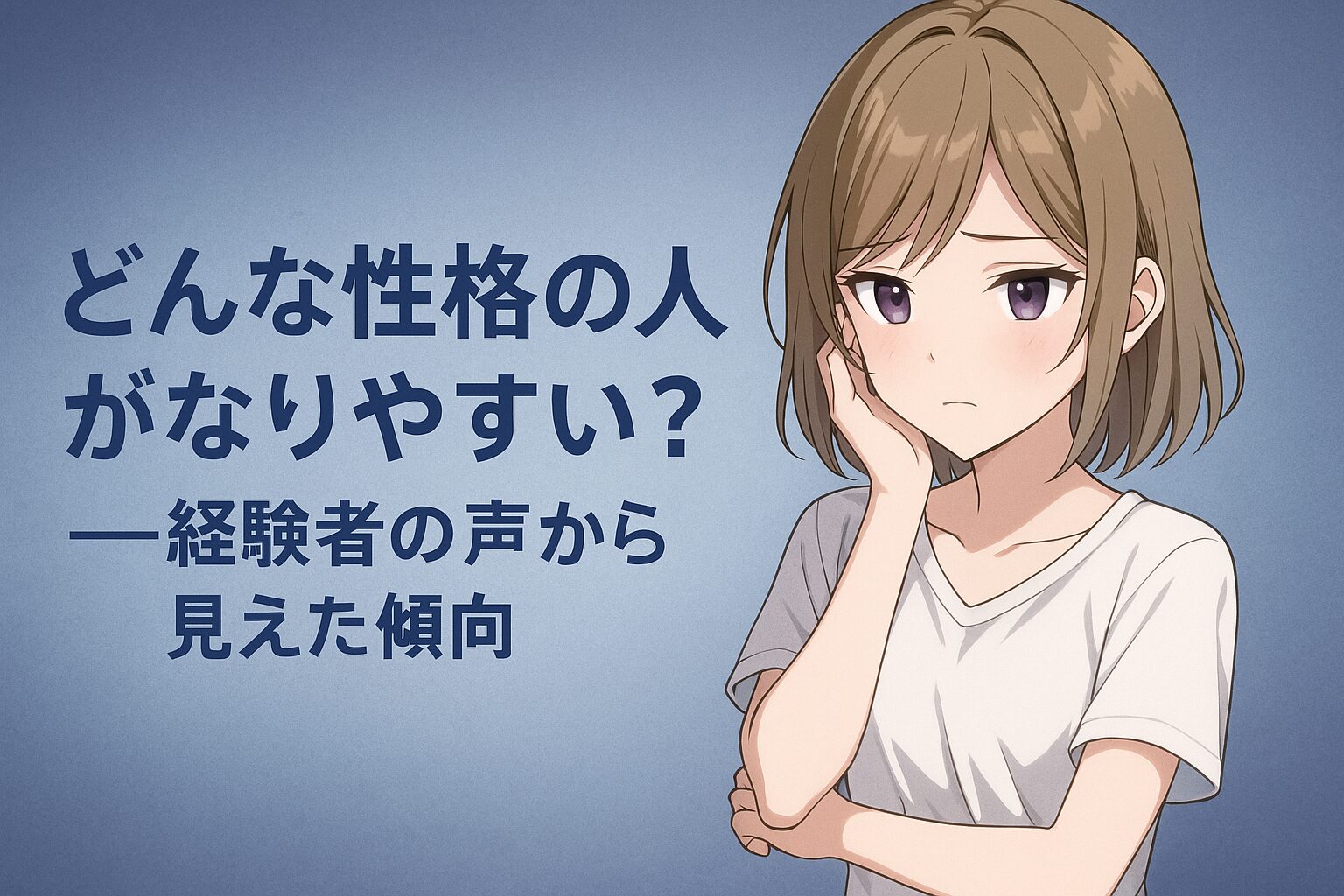
「双極性感情障害になりやすい人は、どんな性格なのか?」──これは、筆者自身がかつて疑問に思い、調べ続けてきたテーマです。そして、多くの経験者の声や医療関係者の見解を追う中で、いくつかの共通項が浮かび上がってきました。
まず第一に挙げられるのが、「真面目で几帳面な人」「責任感が強い人」。完璧主義の傾向がある方は、自分に過度な期待を抱きがちです。そのために無理を重ね、ストレスが蓄積していく中で、ある日突然“躁”のような異常なテンションを迎えることがあります。本人は「やっと自分が本来の力を取り戻した」と錯覚しがちですが、それは実は病のサインであることが多いのです。
また、「感受性が鋭く、人の感情に敏感すぎるタイプ」もリスクが高いとされています。周囲の評価や空気を過剰に意識しすぎて、自分の感情を置き去りにしてしまう──その結果、内側に抱えた負荷が限界を超えた時、一気に症状として現れてしまうことがあります。
そして意外なことに、「明るくて社交的に見える人」も例外ではありません。むしろ、躁状態の時に「魅力的に見える」ことすらあり、周囲はその人の異変に気づきにくくなります。筆者がかつて関わった知人も、常に笑顔で快活なタイプでした。しかし、ある日突然失踪し、後になって双極症と診断されていたことを知りました。表面の印象と内側のギャップの大きさは、決して無視できるものではありません。
こうした性格傾向はあくまで「なりやすい傾向」であり、決して「この性格の人だけがなる」というものではありません。大切なのは、「誰でもなりうる病気である」という前提に立ち、自己判断せず、気になる兆候があれば専門医に相談することです。
自分の性格に思い当たる節があるからこそ、筆者は今もなお生活と心のバランスを慎重に保つよう意識しています。病気を防ぐための第一歩は、自分自身を知り、許すことなのかもしれません。
広末涼子さんが公表した背景と、なぜ話題になっているのか
2025年5月2日、女優の広末涼子さんが「双極性感情障害」と「甲状腺機能亢進症」と診断されたことを明かし、すべての芸能活動を休止すると発表しました。この告白は瞬く間に多くのメディアで報じられ、SNSでも大きな反響を呼びました。
なぜここまで大きな話題になったのか──それは、単に“有名人の病気”というニュースバリューだけではなく、「病名を公表せざるを得なかった背景」が、あまりにも深刻だったからです。
広末さんは4月、交通事故を起こし、搬送先の病院で看護師への暴行容疑で逮捕されました。その後、危険運転の疑いなども加わり、本人の精神状態を疑問視する声があがる中、医療機関に入院し、最終的に今回の診断が下されたとされています。つまり、「事件を起こしたから病名を明かした」のではなく、事件の裏に精神疾患が関与していたことが、時間をかけて明らかになっていったのです。
この経緯に対して、一部では「病気を言い訳にしている」「責任逃れだ」といった批判的な声も見られました。しかし、事務所側は“今回の病名公表は責任回避ではなく、誠実な説明の一環である”という旨を明確に発信しています。
さらに複雑なのが、併発しているとされる「甲状腺機能亢進症(バセドウ病)」の存在です。この病気もまた、情緒不安定や攻撃性の増加といった精神的な症状を引き起こすことがあるため、今回の行動の背後には、精神疾患と身体疾患が複雑に絡み合った状態があった可能性が考えられます。
筆者はここに、“芸能人だからこそ公表を求められる苦しさ”を強く感じました。一般の方であれば、治療に専念する間、静かに回復を待たれるだけかもしれません。しかし、公人である広末さんの場合、騒動や批判の矢面に立たされながら、自分の不調を言葉にして説明しなければならなかったのです。
その告白が、結果的に同じような病を抱える人たちに勇気を与えたことは間違いありません。病気をさらけ出すことが「逃げ」ではなく、「立ち向かう姿勢」なのだと、多くの人に示してくれたのではないでしょうか。
精神疾患に対する社会のまなざしと、支援のあり方
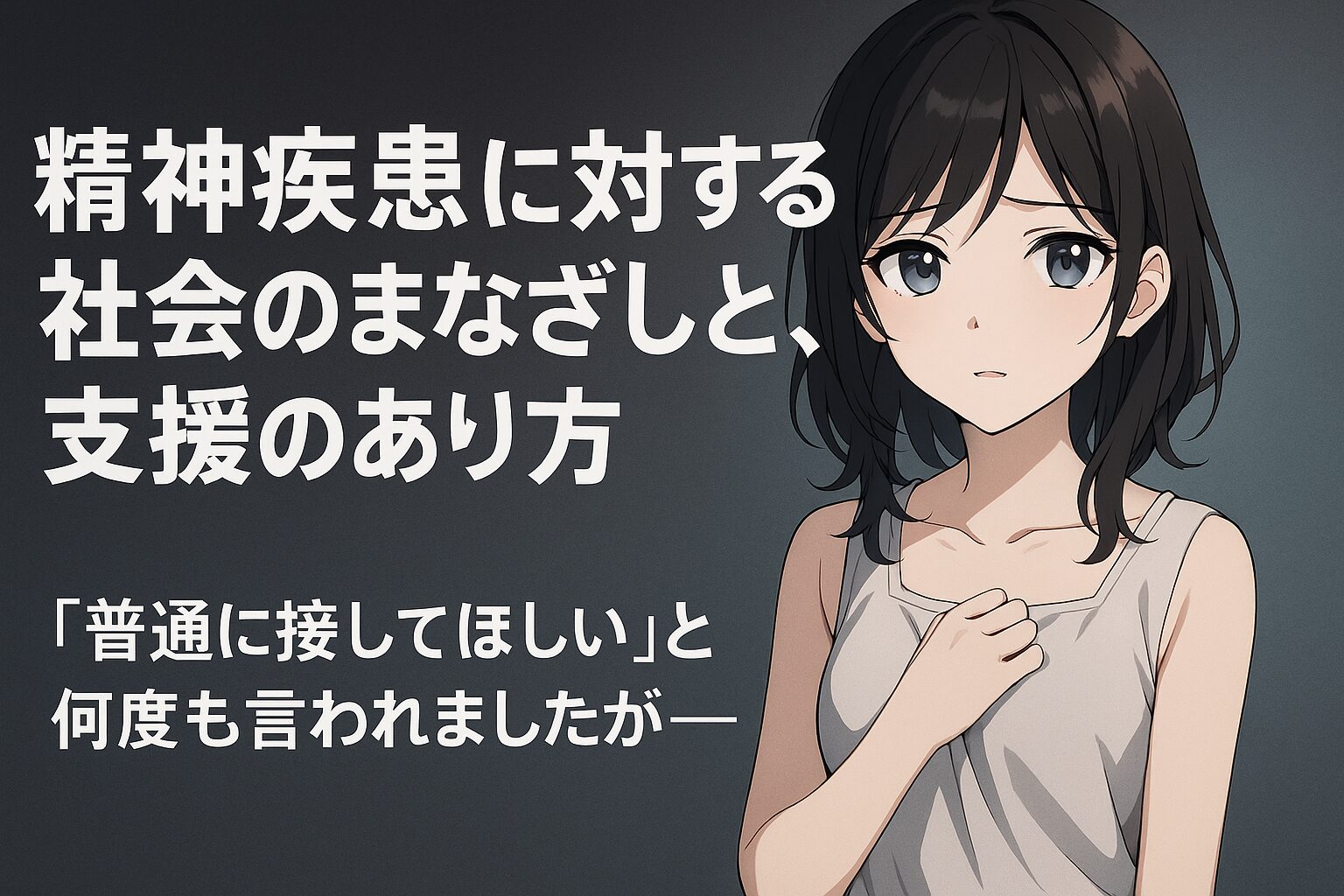
精神疾患、とくに双極性感情障害のような“見えにくい病気”に対する社会の認識は、依然として十分とは言えません。目に見える怪我や病とは異なり、「元気そうに見えるのに」「仕事もできていたじゃないか」といった無理解な反応が、患者本人を追い込む一因になってしまうのです。
実際、躁状態の際には本人が「自分は調子が良い」と感じるため、自覚症状が乏しくなるという特性があります。そのため、病気であることにすら気づかずに暴走してしまい、結果として人間関係や仕事での信頼を失ってしまう──そういった負の連鎖が多くの当事者を苦しめています。
さらに、周囲の人たちが「本人の責任」や「性格の問題」として片付けてしまうと、診断や治療の機会を逃すことになります。これは本人だけでなく、家族や職場、社会全体にとっても損失でしかありません。
広末涼子さんのような著名人が病名を公表したことで、多くの人がようやく「双極症とは何か?」を真剣に考えるきっかけを得ました。ですが、それと同時に、ネット上には「芸能人だからって病気を免罪符にするな」「被害者の方が気の毒」といった厳しい声も目立ちました。ここに、精神疾患を巡る“責任”の重さと、“支援”の曖昧さが浮かび上がります。
筆者はかつて、双極症のある知人が誤解や偏見にさらされる姿を間近で見てきました。彼女は「普通に接してほしい」と何度も言っていましたが、職場では腫れ物のように扱われ、結局孤立していきました。そのとき私は、「理解とは、特別扱いすることではなく、“普通に関わること”なんだ」と痛感したのです。
社会に求められるのは、病気の有無によって人を分けることではなく、それぞれが置かれた状況を尊重し、必要に応じて支える姿勢です。医療の充実や職場での配慮、学校教育における啓発──できることはまだまだあります。
私たちに今できる最初の一歩は、「知らないことを知ろうとすること」。そして、誰かの行動や言葉の裏に、苦しみや理由があるかもしれないと、少しでも想像してみることです。
世間の反応
多分だけど、本人も周りの関係者もわかってなかったと思う。変だって事はなんとなくかんじてたかもだけど…かなりきつかったんじゃないかな? 今はゆっくり休んで欲しい。
https://x.com/tfOFs1ECJ894309/status/1918293766680821841
沢山の人から色々と心ない事を言われて 応援している私たちも本当に辛かったです 広末さんと同じように 苦しんでる人達はたくさんいますよ 芸能界に戻ろうが 戻らまいがどうでも良いです 広末さんが毎日、笑顔で健康に 過ごせる様にずっと応援してますよ 今は、本当にゆっくり療養してください
https://x.com/kanazawakani/status/1918286536787017778
● 「やはりそうだったか」という納得の声 広末さんのこれまでの言動や報道を踏まえ、「双極性障害と聞いて納得した」という声が多く見られました。特に、以前から不安定な振る舞いや突発的な行動があったことを指摘し、「予想していた」という反応も一定数ありました。
● 本人と周囲の苦労を想像する声 「当人も周囲も、はっきりと病気に気づいていなかったのではないか」「かなり無理を重ねていたように見える」と、これまで気づかれずに頑張ってきた背景を思いやる投稿も多数あります。
● 治療と静養を願う応援コメント 「まずはしっかり治療して」「時間をかけてゆっくり休んで」という、温かく見守る声が多数を占めています。中には、同じ病気を経験した当事者からの励ましやアドバイスもあり、病気との向き合い方に理解を示す投稿が目立ちました。
● 双極性障害や甲状腺機能亢進症に対する理解の広がり 「双極性障害=昔でいう躁うつ病」「気分の波が激しく、周囲からはわかりにくい病気」という解説を含んだ投稿が見られ、情報共有や理解促進を図る動きも見受けられます。自殺リスクや禁酒の必要性を訴える声もあり、医療的な観点からのコメントも一定数存在しました。
● 事務所や報道への疑問・批判 「なぜもっと早く治療させなかったのか」「報道が行き過ぎでは?」という声もあり、特にマスコミの報道姿勢や、他の芸能人との扱いの違いに疑問を持つ人もいます。
● 病名を“言い訳”と見る冷ややかな意見も 一部では「病名を公表することで責任逃れでは?」という疑念や、「もう引退して地元で暮らしては」といった否定的な意見も見られます。ただし、こうした意見は全体の中では少数派でした。
● 芸能界や社会のプレッシャーの重さに共感する声 「完璧を求められる世界に疲れたのでは」「笑顔の裏で長年戦ってきたのだろう」という感情的な共感の声も寄せられており、広末さんの歩んできた人生を肯定的にとらえる傾向も強く見られました。
さいごに:誰でもなりうる“見えない病”を、他人事にしないために
双極性感情障害は、誰にでも起こりうる心の病です。どれだけ強く見える人であっても、どれだけ成功を収めている人であっても、その内側では想像もできないほどの葛藤と戦っていることがあります。
広末涼子さんが病名を公表したことは、彼女にとっても、支える人々にとっても、大きな決断だったはずです。そして、その行動がきっかけとなって、今まで声を上げられなかった当事者たちが、自分の経験を語り始めています。筆者自身も、過去に「もしかしたら自分も…」と感じながらも言葉にできなかったひとりでした。
双極症は、完治が難しい病ではありますが、適切な治療と理解のある環境があれば、安定して暮らすことは十分に可能です。必要なのは、「支える人」と「支えられる人」の間にある信頼関係、そして社会全体としての受容の姿勢です。
だからこそ、今後私たちがやるべきことは、「誰かを批判すること」ではなく、「その背景を知ろうとすること」です。精神疾患を持つ人を特別視するのでもなく、突き放すのでもなく、ただ“共に生きる”という意識を持つ──その積み重ねが、優しい社会をつくる第一歩になるのではないでしょうか。
騒動や病名にばかり目を向けるのではなく、その人がどう生き直そうとしているのかに、もう少し目を向けてみる。私たちにできる最大の支援は、静かに見守ることかもしれません。