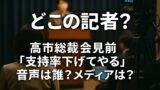静まり返った永田町の一室に、ふと漏れたひと言
「支持率下げてやる」
その瞬間、取材の空気がわずかに揺れ、やがてそれはマイクを通じて全国へと拡散しました。
発言の主は、時事通信社の映像センター写真部に所属する男性カメラマンだったそうです。
そして社は、その後「厳重注意」という処分を下しました。
この一件は、単なる軽口や冗談では済まされない波紋を呼びました。
報道に求められる中立性、公正さ、そして“現場の意識”のあり方が問われています。
実際に放映されてないものの、漏洩したわけでだから該当するTV局関係者を総務省に呼び出して厳重注意すべきだよね。 放送法4条に抵触ものだよ。
https://x.com/zomas_v1/status/1975791147160350772
なぜこのような発言が起き、なぜここまで大きな問題に発展したのか。
その背景には、報道機関が抱える構造的な疲弊と、組織文化の見えない歪みが隠れているのかもしれません。
この記事では、時系列で出来事を整理しながら、発言の意味、会社の対応、そして報道倫理の課題を掘り下げていきます。
この記事でわかること
- 「支持率下げてやる」発言がどのように広まったのか
- 時事通信社による「厳重注意」処分の経緯と背景
- 現場カメラマンが抱える取材環境と組織文化の課題
- 報道機関の信頼を取り戻すために必要な視点
- 今回の出来事が示す“報道倫理のこれから”
※この記事はSNS情報を中心に書かれていますが、意見や感じ方は人それぞれです。
推測の域を出ず、異なる意見や見解があることも理解しておりますので、どうかご了承ください。本記事を通じて、少しでも多くの方に伝えられれば幸いです。
✅ 簡易まとめ
・発言の主は「映像センター写真部所属」の男性カメラマン。
・時事通信社は「厳重注意」として処分を公表。
・事件は報道の中立性と現場文化を問う象徴となった。
発言の経緯と確認された事実

― 「厳重注意」で済ませていいのか、世論がざわついた理由 ―
2025年10月7日、永田町・自民党本部。
取材対応を待つ報道陣の列に、時事通信社のカメラマンがいました。
その待機中、何気ない雑談の最中に漏れた言葉が、思いがけず波紋を広げます。
「支持率下げてやる」
冗談とも皮肉ともつかない一言が、マイクに拾われ、ライブ配信を通じて全国へ。
SNSでは瞬く間に拡散し、「報道が支持率を操作しているのではないか」という不信感が広がりました。
やがて時事通信社は社内調査の結果を公表します。
発言者は映像センター写真部に所属する男性カメラマンであると確認され、「厳重注意」の処分が下されたそうですが・・・
発表の文面には、「雑談での発言とはいえ、公正性と中立性に疑念を抱かせた」という一文が添えられていました。
厳重注意程度で終わる話なのですか? 公平性、公正性の観点からこの様なメディア担当者を雇用する事は企業コンプライアンス違反にはならないですか? 本人、上司、関係役員、社長も含めて、厳罰、謝罪が必要。メディアという権力機関が、平気でコンプライアンス違反をするのは権力の濫用である。
https://x.com/MeronPa964337/status/1976116561070141688
しかし、この「厳重注意」という言葉こそが、次の炎上の火種になりました。
SNSでは「それだけで済むのか」「停職や配置転換が妥当では」といった投稿が相次ぎ、トレンド入り。
厳重注意で済むんだね。時事通信にとっては解雇までしなくてよい程度の問題だということだね。
https://x.com/nomarryman/status/1976128172447105153
支持率下げてやると発言した本社カメラマンに時事通信は厳重注意だけで済ましてて草
https://x.com/whiteiro200/status/1976112680072249759
もうニュースは見ないでSNS眺めて情報を取捨選択する時代かなぁ 日本の報道は前提がフェイクニュースだと思って見ないといけないし、それならSNSの情報と変わんないじゃんね。
https://x.com/whiteiro200/status/1976112680072249759
一方で、「軽口を切り取って過剰に叩くべきではない」という声もあり、世論は真っ二つに割れました。
結果として、事件の焦点は“発言そのもの”よりも、“処分の軽さ”と“組織の姿勢”へと移っていきます。
報道の信頼は、処分の重さではなく、説明の誠実さで守られるもの。
そう感じた人も少なくありませんでした。
✅ 簡易まとめ
・発言者は時事通信社の映像センター写真部に所属する男性カメラマン。
・社は「厳重注意」として処分を公表。
・SNSでは「それだけで済むのか」と疑問の声が急増し、トレンド化。
・問題は“発言の軽さ”よりも、“対応の軽さ”に移りつつある。
雑談では済まされない「軽口」|報道現場の倫理観と構造

「雑談の一言なのに、なぜここまで問題になるのか」
なかにはそう感じた人もいるのでしょうか・・?
けれども、今回の「支持率下げてやる」という言葉は、単なる軽口では済まされない性質を持っていました。
それは、報道機関が“世論に影響を与える力”を持っているという前提を前提にした発言だったからです。
今後時事通信の情報は偏った報道姿勢で配信されていることを加味して接するようにします。厳重注意処分とは政治家にだけ厳しく、自分たちは特別扱いなのですね。記者クラブの一員で居続ける資格があるとお思いですか。
https://x.com/L5vc2Z9w/status/1976117544974156192
つまり、冗談の形を取りながらも、「報道によって支持率を動かせる」という意識を内包しているのです。
この一言が重く受け止められた理由は、そこにあります。
報道は中立でなければならない。
どんな政治家であっても、どんな思想を持っていても、報道は公平であるべきだと、多くの人が信じています。
その信頼があるからこそ、報道機関の存在が社会で機能しているのです。
しかし、今回のような言葉が現場から出てくると、
「もしかして報道は意図的に印象を操作しているのでは」といった疑念が一気に広がります。
その疑念が、一度広まってしまえばもう止めることは難しい。
時事通信がすべきは単なる謝罪ではなく、これまで実際に恣意的な報道が行われていなかったか確かめるための第三者による調査です。
https://x.com/Dollar__G/status/1976118849729868275
報道の現場で交わされる“軽口”が、組織の姿勢やモラルを映す鏡のように扱われるのは、そのためです。
そしてこの発言が録音・配信の中で偶然拾われたという点にも、時代の変化が表れています。
かつての記者クラブや会見現場は“閉じた空間”でしたが、
今ではスマートフォン一つで音声が記録され、瞬時に世界へ広がります。
取材現場の何気ないやり取りも、もはや“外に漏れないもの”ではなくなりました。
報道の現場にいる者が常に問われるのは、発言の内容ではなく、その根底にある「意識」です。
つまり、冗談であっても“意識の方向”がずれていれば、それがそのまま信頼の揺らぎにつながる。
今回の事件は、まさにその典型例と言えるでしょう。
うわぁ… 共同通信に加え、時事通信も偏った報道内容を意図的に作り出してたということですよね? 報道内容を意図的に操作して、印象操作で支持率を下げるって世論操作ですよね? これまでもそうしてきたんじゃないですか?第三者機関が調査すべきでは? 公正でない時点で存在価値ないのでは?
https://x.com/realist1192/status/1976120286719234550
✅ 簡易まとめ
・「支持率下げてやる」という発言は、冗談に見えて“報道の力”を前提にしていた。
・そのため、発言自体が報道の中立性への不信を呼んだ。
・録音・配信によって“現場の声”がそのまま拡散される時代背景がある。
・報道の信頼は「意識の方向」で決まる。
時事通信社の対応と残された課題

― “厳重注意”という線引きは正しかったのか ―
時事通信社は、発言が確認された翌々日という早い段階で調査結果を公表しました。
このスピード感自体は、報道機関としての初動対応として評価できるものです。
社内調査により、発言者を映像センター写真部所属の男性カメラマンと特定し、
「厳重注意」の処分を下したと明言しました。
同時に、取締役編集局長の藤野清光さんがコメントを発表し、
「雑談での発言とはいえ、公正性と中立性に疑念を抱かせた」と謝罪の意を示しました。
しかし、この発表を見た多くの人は、素直に納得できなかったようです。
SNS上では「厳重注意は軽すぎる」「停職や異動はないのか」といった声が急増しました。
なぜなら、今回の発言は一個人の感情よりも、“報道機関全体の信用”に関わる問題だったからです。
厳重注意という処分は、社内的には“警告”の位置づけであり、
懲戒処分の中では比較的軽い段階にあたります。
つまり、実質的なペナルティはなく、今後の勤務に大きな制約は生じないということです。
それゆえに、「あれだけの波紋を呼んでおきながら、それで終わりなのか」と受け止められたのです。
一方で、社内関係者の中には「処分を重くしすぎれば“個人切り捨て”に見える」との意見もあるようです。
報道の現場では、緊張とストレスの中で軽口が交わされることは珍しくなく、
個人を過度に責めれば、現場の士気を下げかねないという判断も理解はできます。
しかし、それでも「厳重注意」で終わらせたという決定は、
結果的に“問題を小さく見せた”ように映ってしまいました。
本来ならば、同時に「再発防止策」「現場教育の強化」「外部検証の実施」など、
組織的な対策を具体的に示すべきでした。
実際、発表文の中にはそれらの記述がなく、
「社員を注意した」という一点にとどまっていたのです。
この点が、世論の不信感をさらに強めました。
報道機関が他者の責任を問う職業である以上、
自らの誤りに対しても同じ厳しさで臨む姿勢が求められます。
その意味で、今回の「厳重注意」は処分の内容よりも、
“説明の浅さ”こそが最大の問題だったのではないでしょうか。
本当に時事通信なのかも謎だけどね。 仮に事実ならカットする事も、何日も放置する事も無かっただろうし、厳重注意じゃなくて普通なら解雇だろうしねぇ… 日テレ含め隠蔽に関わってたメディアは一生怪しいわ。
https://x.com/whiteiro200/status/1976112680072249759
✅ 簡易まとめ
・時事通信社は早期に調査結果を公表し、「厳重注意」として処分。
・対応のスピードは評価できるが、内容は「軽い」との批判が集中。
・再発防止策や体制強化の説明が乏しく、信頼回復には至らなかった。
・問題は処分の重さよりも「説明責任の浅さ」にある。
さいごに
「支持率下げてやる」という一言は、
報道機関にとって何より重い警鐘となりました。
それは、誤解を招くような軽口が、
一瞬で組織全体の信用を左右する時代に私たちが生きているということでもあります。
報道の仕事は、ただニュースを届けるだけではありません。
どの角度から光を当て、どの言葉を選ぶかで、
人々の受け取り方も変わってしまいます。
だからこそ、記者もカメラマンも、
その一瞬の発言や判断に、常に自覚と責任を持たなければなりません。
今回の件は、ひとりの社員の失言として片づけることもできます。
しかし、それでは何も変わらない。
同じような環境や価値観のもとで、
次の“軽口”が生まれるだけです。
報道が社会の信頼を取り戻すには、
“何を報じるか”よりも、“どう報じるか”を問い直すことが欠かせません。
真に必要なのは処分の重さではなく、
発言が生まれた背景を見つめる誠実さです。
報道が再び信頼される日は、
その誠実さが日常の現場で積み重ねられたときに訪れるのだと思います。
参照サイト一覧
- https://www.jiji.co.jp/company/news/show/169
→ 時事通信社公式「お知らせ」ページ。発言の経緯と「厳重注意」処分を正式発表。 - https://www.jiji.com/jc/article?k=2025100900453&g=soc
→ 時事通信(社会面記事):「自民党取材中の発言、記者に厳重注意 報道の中立性に疑念招く」と題した本件報道。 - https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2510/09/news084.html
→ ITmedia NEWS:「時事通信社カメラマンが『支持率下げてやる』発言 厳重注意に」と報じるニュース。 - https://www.nikkansports.com/general/nikkan/news/202510090000528.html
→ 日刊スポーツ:「時事通信カメラマンが『支持率下げてやる』発言で厳重注意」と報道。 - https://news.livedoor.com/article/detail/29744426/
→ ライブドアニュース(共同通信配信):「時事通信社カメラマンを厳重注意」との速報記事。 - https://news.livedoor.com/article/detail/29744446/
→ ライブドアニュース(別系統転載):「発言はライブ配信で流出、ネット上で波紋」と報じる解説記事。 - https://www.bengo4.com/c_18/n_19471/
→ 弁護士ドットコムニュース:報道倫理・取材現場での発言リスクを法律的観点から解説。 - https://www.j-cast.com/2025/10/08508222.html
→ J-CASTニュース:「自民党側も『#支持率上げてやる』と反応」など、政治サイドの動きを含めた詳細報道。
※記事内画像は記事内容と関係ありません