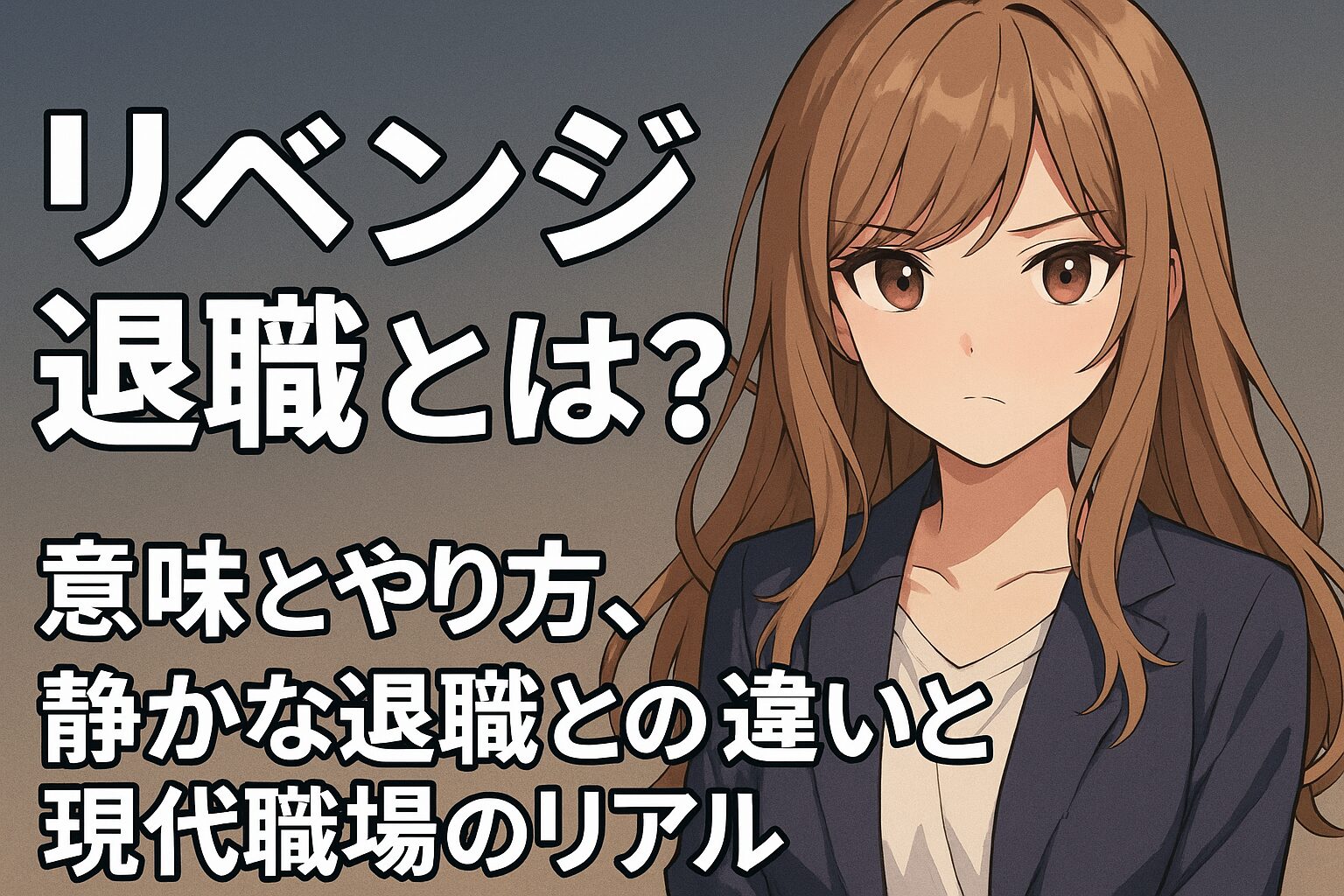働いて心が削れていく――
そんな経験をしたことがある人にとって、「リベンジ退職」という言葉は決して他人事ではないのかもしれません。
かつては“円満退職”が当たり前とされていた社会で、いま急速に広がりを見せるのが、退職という最後のタイミングで職場に「一矢報いる」選択肢です。
SNSでは、「もう限界だった」「静かに辞めろって、そもそも静かに働かせてくれなかった」といった声が後を絶ちません。一見過激にも見えるこの行動の裏側には、長年積もり積もった不満と、無力さに対する反発心があります。そしてその根底には、もうひとつのトレンドである「静かな退職(Quiet Quitting)」とも通じる、働き方そのものへの疑問があるのです。
この記事では、「リベンジ退職」とは何か、そのやり方や背景、そして「静かな退職」との違いについて詳しく解説します。
決して推奨されるべき行動とは言えないかもしれませんが、そうした選択に至るまでの過程を知ることで、私たちは働き方について見直すべき点を見つけることができるかもしれません。
この記事でわかること
・「リベンジ退職」とは何か、その具体的な意味
・よくあるリベンジ退職のやり方とリスク
・「静かな退職」との違いや共通点
・なぜ今こうした辞め方が増えているのか
・企業と個人、それぞれに求められる対処とは
※この記事はSNS情報を中心に書かれていますが、意見や感じ方は人それぞれです。推測の域を出ず、異なる意見や見解があることも理解しておりますので、どうかご了承ください。本記事を通じて、少しでも多くの方に伝えられれば幸いです。
リベンジ退職とは?意味と注目される理由
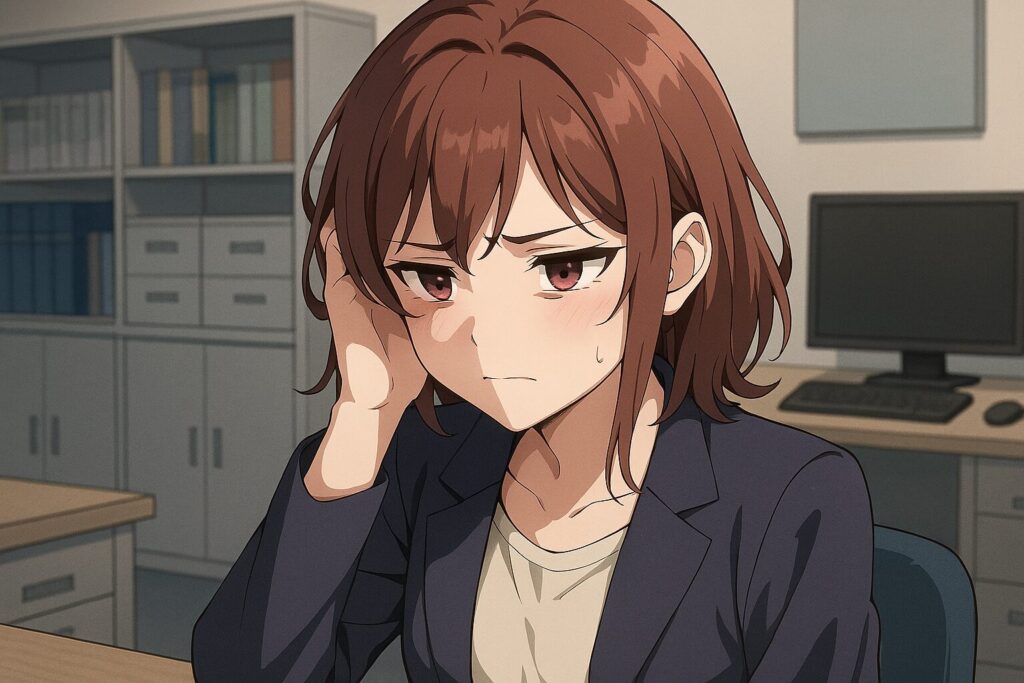
リベンジ退職の定義と背景
リベンジ退職とは、会社を辞める際に意図的にダメージを与えるような行動を取る退職の形です。
円満退職とは対極にあり、SNSでの情報暴露、業務の放棄、引き継ぎ拒否といった行為が典型例です。その背景には、長年にわたる過重労働やパワハラ、不当な扱いに対する怒りと失望が蓄積しています。
なぜ今「復讐的な退職」が注目されるのか
リベンジ退職されるような会社なんだから 被害受けてるとこはそういうとこなんだろ
https://x.com/shibatawdt/status/1922459732079464618
最近になってこの言葉が注目を集めているのは、単に『過激なひとが増えた』だけではないでしょう。
退職という行為自体が、個人と組織の関係性の「終着点」として可視化されてきたことが背景にあるのではないでしょうか。
誰もが転職を視野に入れる時代において、「辞めるときくらいは自分の意思を貫きたい」という気持ちが表面化しているのでしょう。
SNSで話題となったきっかけと実例紹介
SNSでは、実際にリベンジ退職を行ったという体験談が多くシェアされ、「数千万円規模の損害を出してやった」「業務を誰にも教えずに辞めた」などの投稿がバズを生みました。
一方で、そういった行動の裏には、「それでも黙っていれば使い捨てにされていた」という深い無力感が存在していることも見逃せません。
✅ リベンジ退職は、辞める際に会社へ意図的にダメージを与える行動
✅ SNSで「黙って辞められなかった人たち」の実例が共感を呼んだ
✅ 背景には積年の不満と、声が届かない環境への怒りがある
リベンジ退職のやり方と実態|どこまでが許される?

悪質な例では、社内チャットの履歴を公開したり、内部資料をSNSに投稿したりといった行為も報告されています。
そうした行動が結果的に企業の信用を大きく損なうこともあり、ただの退職では済まない事態へと発展する可能性をはらんでいます。
よくあるリベンジ退職の手口
リベンジ退職は、その名の通り「退職を手段として組織に報復する」行動です。
よくある方法としては、まず業務の引き継ぎ拒否が考えられるでしょう。自分しか把握していない業務を故意に説明せず、そのまま立ち去ることで組織に混乱を与えるケースです。
次に見られるのが、社内の不正や体質をSNSなどで暴露する行為です。これにより企業のイメージダウンを引き起こすことが目的とされます。
また、業務用アカウントやシステムのログイン情報を放置したまま退職することで、残された人たちが混乱する例も報告されています。
引き継ぎ拒否・情報暴露・社内破壊の実態
特に注目されるのが、業務をブラックボックス化したまま放置するケースです。
このような状態では、辞めた後も業務が進まず、クライアント対応やプロジェクトに支障が出る可能性があります。
また、内部告発に近い情報暴露を行う退職者も増えていますが、これは企業文化や内部統制の欠如が背景にあると考えられます。「最後に声を上げないと、何も変わらない」と感じた人が取る手段ともいえます。
✅ 引き継ぎ拒否・情報暴露・業務の放置などが典型的な手口
✅ 行き過ぎれば守秘義務違反や業務妨害として訴えられるリスクも
✅ キャリアへの影響や再就職時の評判悪化も大きなデメリット
「静かな退職」との違いはどこにあるのか?

静かな退職(Quiet Quitting)の定義と特徴
「静かな退職」は、物理的には辞めていないが、心理的には会社から距離を取っている状態を意味します。
これは、与えられた最低限の仕事しかしない・会議で発言しない・定時で帰るなど、従来の“熱意を持った働き方”とは距離を置く姿勢だそうで、元はアメリカで発信された言葉だそうですね。

定時で帰る姿勢は当たり前だろ・・・
背景には、「頑張っても報われなかった」という経験の蓄積があり、仕事に“やりがい”よりも“心の安全”を重視する若い世代を中心に広がっています。
リベンジ退職との共通点・相違点
どちらも職場に対する不信感から生まれる態度ですが、「静かな退職」は“静かに離れる”選択であるのに対し、「リベンジ退職」は“声なき怒りの爆発”とも言える行動です。
共通しているのは、会社に対する熱意や忠誠心をすでに失っている点です。
しかし、リベンジ退職は積もり積もった怒りを形にして表出させるものであり、組織に対して明確なメッセージを発信しようという強い意思が見て取れます。
✅ 静かな退職は“心だけ辞める”心理的離職、リベンジ退職は“行動”で抗議
✅ どちらも職場への失望から生まれるが、表現方法が異なる
✅ 「静かに辞めさせてくれなかった」ことが、怒りの爆発に変わる要因に
なぜリベンジ退職が生まれるのか|背景にある職場の闇

大切にされなかった経験が怒りに変わる構造
「リベンジ退職」という行為の裏には、単なる感情的な衝動ではなく、「何度も訴えても無視された」「理不尽な扱いが続いた」という積年の不満と諦めが蓄積しています。
本来、退職はもっと静かで前向きな選択であるはずです。しかし、軽視され、圧力を受け、限界まで追い詰められた末に、「せめて何かを残したい」と願った結果が、リベンジという形になるのです。これは、被害者の反撃であると同時に、声が届かなかった過去への訴えでもあります。
組織側の無自覚な搾取と属人化のリスク
リベンジ退職によって業務が回らなくなる企業の多くは、そもそも「その人がいないと成立しない仕事」=属人化の問題を抱えています。
ナレッジ共有の文化が乏しく、マニュアルも存在しない。結果として、辞めた人の責任にされる構図が生まれますが、本来は業務設計の失敗が露呈しているにすぎません。
また、「やりがい」や「熱意」を強要する風土も搾取の一種とされ、これが社員を疲弊させてきた原因とも言われています。
✅ 大切にされなかった実感が怒りや報復へと変化する
✅ 業務の属人化・情報共有不足が企業の脆弱性を露呈
✅ 働き方への誠実さを欠いた職場にこそ問題がある
世間の反応まとめ
◆擁護・共感的な声(リベンジ退職/静かな退職に肯定的)
✅ 「やられたらやり返すのは当然」
→ 過重労働やパワハラに苦しめられた経験を語り、退職時に何かしら抗議の意志を示すのは“当たり前”とする声が多い。
✅ 「会社にも非がある」
→ 一人に仕事を押しつけておいて辞められたら文句を言うのは筋違いとの批判が目立つ。
✅ 「最後の抗議手段としてのリベンジ退職」
→ 正攻法で声を上げても無視されたため、せめて辞めるときだけでも意思表示したかったという背景に共感する声も。
✅ 「静かに辞めるのでは伝わらない」
→ Quiet Quittingでは変わらないため、敢えて目立つ形で辞めて問題を可視化しようとする試みだと評価する意見。
✅ 「外資では当然の対策」
→ 退職即ロックアウトなど、むしろ日本の企業の無防備さのほうが問題だと指摘する冷静な視点も。
◆否定・警戒的な声(倫理的・法的なリスクを指摘)
✅ 「軽犯罪」「法的にアウト」
→ 情報漏洩や業務妨害は明確な違法行為。自己満足で済ませるべきではないという法的リスクの指摘。
✅ 「復讐は損しかない」
→ 怒りのまま行動しても、キャリアに傷がつくだけで何も得られないという損得勘定のリアリスト視点。
✅ 「転職に悪影響」
→ 特に同業界内では評判が回りやすく、次の職場にまで影響するリスクを懸念する声が多い。
✅ 「リベンジ退職を美談化するな」
→ 被害者意識の強調に過ぎず、過激な行動を正当化する風潮に警鐘を鳴らす意見。
◆中立・構造的な分析
✅ 「個別性が高すぎて一概には語れない」
→ リベンジ退職に至った理由は千差万別で、個人の性格も職場の体質も絡むため一括りにはできないという指摘。
✅ 「企業体質の甘さが根本原因」
→ 特定の社員に業務が集中している、情報共有が不十分など、辞めた社員ではなく“仕組み”が問題という視点。
✅ 「静かな退職も企業文化への復讐」
→ 見えにくいだけで、Quiet Quittingも本質的には企業に対する静かな反発だとする声も存在。
さいごに:リベンジ退職という“警告”にどう向き合うか
冷静な企業の対応と働き方改革の必要性
リベンジ退職が起こるたびに、企業は「困った社員がいた」と片付けがちですが、それでは問題の本質は見えません。むしろ問われるべきは、なぜそこまで社員が追い詰められたのかという根本原因です。
業務体制が属人化していなかったか、声を上げたときに真摯に耳を傾けていたか――そうした自己検証こそが、次のトラブルを防ぐための第一歩になるはずです。
社員は「暴徒」ではなく「声を上げる存在」
怒りを行動に変える人を「反乱者」として排除するのではなく、そこに現場のSOSがあったことを汲み取る視点が求められます。
「静かに辞めてくれ」と願うなら、「静かに働ける環境」を整えていたのか、企業自身も見直すべきでしょう。社員は企業にとってただの労働力ではなく、一人の人間です。尊重されなかった先に、静かな退職やリベンジ退職がある――それは企業に対する最後のフィードバックかもしれません。
✅ 問題視すべきは「辞め方」ではなく「働かせ方」
✅ 社員を一方的に加害者扱いせず、声として受け止める視点が必要
✅ 静かに辞める人が尊重される環境づくりこそ、真の対策になる