最近、「中国製スマホは使うな」という声がSNS上で急増しています。
その発端となったのが、2025年4月に報告されたマルウェア問題です。中国製の一部スマートフォンに、製造段階から暗号資産の送金先をすり替えるマルウェアが仕込まれていたことが判明し、多くのユーザーが驚きと不安を抱えました。
これらのスマホは、一見すると有名ブランドの上位機種を思わせる外観とスペックを備えていますが、実態は模倣品であり、中には信頼性に欠けるブランドが製造に関与していました。ユーザーの画像やチャット履歴、さらには暗号通貨ウォレットのリカバリーフレーズまでが、密かに抜き取られていたといいます。
「中国製スマホはすべて危険なのか?」「Androidだから危ないのか?」という議論も巻き起こる中、本記事では、実際に問題となったマルウェアの手口と被害の詳細、SNSでの反応、そして私たちが今すぐできる対策について詳しく解説していきます。
この記事でわかること
- 中国製スマホに仕込まれたマルウェアの実態とその手口
- 「使うな?」という声が広がった背景とSNSでの反応
- 情報漏洩のリスクと防止のための具体策
- 「中国製=危険」は本当なのか?見極めのポイント
※この記事はSNS情報を中心に書かれていますが、意見や感じ方は人それぞれです。推測の域を出ず、異なる意見や見解があることも理解しておりますので、どうかご了承ください。本記事を通じて、少しでも多くの方に伝えられれば幸いです。
中国製スマホに仕込まれたマルウェアの実態とは?

どんな端末で発覚したのか?
2025年4月、セキュリティ企業によって明るみに出たのは、ある種の「中華スマホ」に仕込まれたマルウェア問題でした。対象となったのは、「S23 Ultra」「Note 13 Pro」「P70 Ultra」といった、いずれも人気ブランドを模倣したような機種。スペック表記も外見も一見すると本物のように見えるこれらの端末は、実際には無名ブランドのSHOWJIなどが製造していた低価格スマホでした。
特に通販サイトやフリマアプリなどで「高性能・格安」として流通していたこれらの端末が、マルウェアを最初から内蔵していたというのです。
聞いたこともない怪しい系スマホの話だったわ
https://x.com/slotpoipoi/status/1913649133539524856
これ所謂wishみたいな中華通販で売られてる有名ブランドを模倣した偽スマホにプリインストールされてるって話だからね これだからAndroidはーとかiPhoneしか勝たんとか言ってる奴は読解力無さすぎる
https://x.com/wreckage_maruwa/status/1913785672953151881
マルウェアの手口:暗号資産すり替え・画像盗取など
このマルウェアは極めて悪質で、暗号資産の送金時に入力されたウォレットアドレスを、攻撃者のアドレスにすり替えるという「クリッピング型」の手法を用いています。しかもそれだけではありません。画像データを解析し、そこからウォレットのリカバリーフレーズを盗み出す機能まで備えており、個人の資産情報が筒抜けになる危険が指摘されています。
さらに、信頼性の高いはずのアプリまでが標的となっていました。改ざんされたアプリは約40種にのぼり、WhatsAppやTelegramといった有名な通信アプリの偽装バージョンが初期状態で端末にインストールされていたとのことです。
仕組まれた時期と手法:製造工程での埋め込み
最も驚かされたのは、このマルウェアが「出荷前の製造段階で仕込まれていた」と見られる点です。
つまり、ユーザーがアプリをインストールしたわけでも、何か怪しいリンクを踏んだわけでもなく、最初から端末自体が“仕掛けられていた”ということになります。
一部では、製造を請け負う下請け工場がコスト圧力の中で、「資金提供と引き換えに悪質なソフトを入れるよう持ちかけられたのではないか」との見方も出ており、スマホを作る現場自体が加担させられていた可能性も否定できません。
被害規模:資産被害・C2サーバー数の推移
この攻撃により、確認された被害額は100万ドル以上。攻撃者は30以上のドメインと60台を超えるC2(コマンド&コントロール)サーバーを運用し、広範囲に情報を抜き取っていたとされます。被害は主にロシア語圏で確認されましたが、過去の類似事例から、日本を含む他国での展開も想定されており、予断を許しません。
✅ 正規のブランドを装った格安スマホに、製造段階からマルウェアが仕込まれていた
✅ 被害内容は、暗号通貨アドレスのすり替え・画像からの秘密情報抽出など多岐にわたる
✅ 攻撃は製造工程で行われ、個人の操作では防げないケースも
✅ 被害総額は100万ドル超、C2サーバーは60台以上が稼働していたとされる
なぜ「使うな?」という声が広がったのか
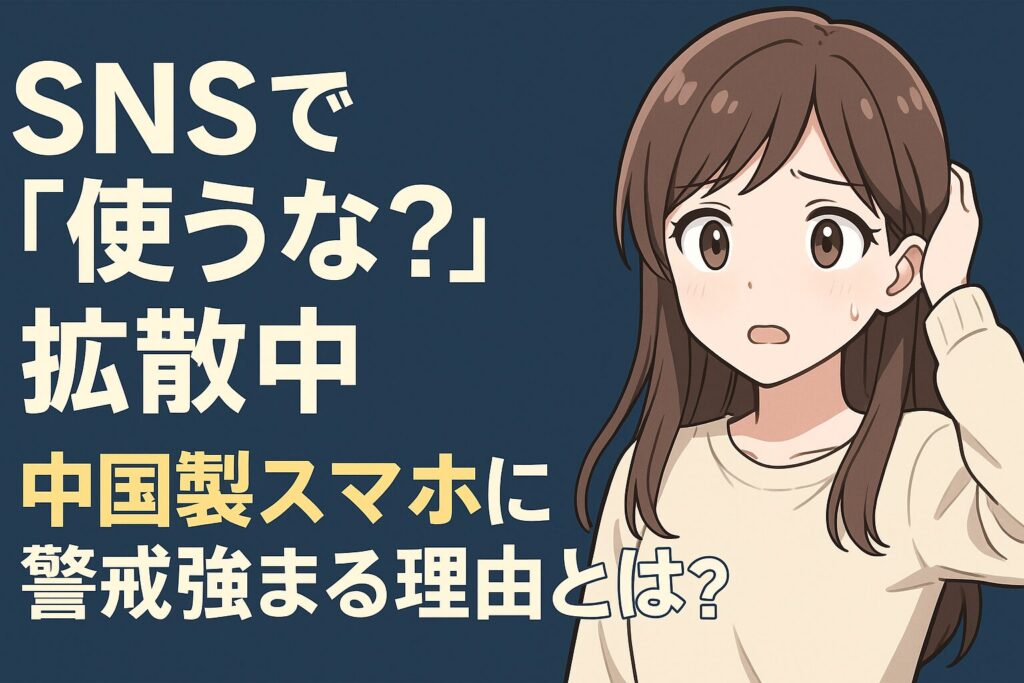
SNSでの拡散と反応の二極化
XiaomiとかOPPOとかじゃなくてAliとかで買えるパチモンスマホか Phonei15とかS23とかいろいろあるよねw
https://x.com/mimatanoyari/status/1913886519485665538
このマルウェア問題が報じられると、SNS上では即座に大きな波紋が広がりました。最も目立ったのは、「やっぱり中国製スマホは危ない」「だから最初からiPhoneにしておけばよかった」といった“拒絶”や“不安”の声です。「使うな?」というワードは、多くのユーザーの投稿でキーワード化され、警告や拡散の意図を込めて使われました。
一方で、「すべての中国製が危険というわけではない」「問題は模倣品に限られている」と、冷静に状況を分析しようとする声もあり、全体の反応は二極化していきました。情報の正確な理解が進む一方で、感情的な反発も強くなっていったのが特徴です。
「中国製=危険」という誤解と偏見
ネット上では以前から「中国製品は信用できない」という固定観念が一部に根強く存在しています。今回の件をきっかけに、それが一気に噴き出した形になりました。スマホだけでなく、パソコン・カメラ・EV車など、さまざまな中華製品に対しても、「裏で何をされているかわからない」といった警戒心が拡大しました。
しかし、今回問題となったのは、あくまで「正規ブランドを装った模倣品」であり、全ての中国メーカーの製品が同様に危険だというわけではありません。この点を見落としてしまうと、必要以上の偏見や差別的な視点に陥るリスクがあります。
iPhoneとAndroidの比較に見る心理的バイアス
「やっぱりiPhoneにしとけば安心だった」という言葉は、多くの投稿で繰り返されていました。この背景には、Apple製品に対する「閉じたエコシステムだから安全」という信頼感があります。Androidは自由度が高くカスタマイズしやすい反面、「悪意あるアプリが入り込みやすい」という先入観があるため、不安が増幅されやすいのです。
ただし、実際にはiPhoneであっても周辺機器やアプリ次第でリスクはゼロではなく、「どんな端末を使うか」以上に「どう使うか」「どこで買うか」が問われているのが現実です。
模倣品と正規品の違いが見分けにくい構造的問題
今回話題になった端末は、見た目やスペック表示が本物そっくりに作られていました。そのため、一般ユーザーが模倣品だと気づかずに購入してしまうケースが後を絶ちません。とくに「wish」や「AliExpress」など、海外通販サイトで売られている製品には要注意です。
こうした構造的な“見分けの難しさ”も、「中国製スマホは危険」という漠然とした不安を後押ししているのです。
✅ SNS上で「使うな?」という警告が一気に拡散され、不安が急拡大
✅ 問題の本質は模倣品にあるが、すべての中国製品への不信が広がる傾向も
✅ iPhoneとAndroidの比較から、心理的な安心感の差が影響している
✅ 模倣品と本物の区別がつきにくい販売構造も、警戒心を強める要因に
情報漏洩のリスクと、私たちが取るべき行動

実際に抜き取られる情報の内容とは?
今回のケースで特に注目されたのは、「スマホに保存された画像や文書データが盗まれる」だけでなく、「チャットの内容」や「暗号資産ウォレットのリカバリーフレーズ」までが標的になっていたという点です。多くの人がスマホを“第2の脳”のように使っている今、個人の思考や資産がそのまま抜き取られることは、もはや人生そのものの乗っ取りに近いと言っても過言ではありません。
加えて、盗まれた情報はその場で被害に直結しないことも多く、本人が気づいた時にはすでに手遅れという事態にもつながります。目に見えない情報漏洩だからこそ、より一層の警戒が必要とされるのです。
個人ユーザーが今すぐできる予防策
最も重要なのは、「どこでスマホを買うか」ということです。
安さだけを基準に海外通販やフリマアプリで端末を購入する行為は、非常に大きなリスクを伴います。例え有名ブランド名が記載されていても、それが本物かどうかを見分けるのは困難です。
また、スマホに保存する情報の選別も必要です。特に、資産管理に関する画像(ウォレットのスクショなど)や機密性の高いファイルは、クラウドや物理的な別媒体に保管するなどの工夫が求められます。
スマホ選びで失敗しないための見極めポイント
- 正規の家電量販店や通信キャリアで購入する
- メーカー名だけでなく、販売元の信頼性をチェックする
- 購入レビューや公式サイトの存在を確認する
- 異常なほど安い価格には警戒心を持つ
このように、購入前にしっかりと調べることが、自分の情報を守るための第一歩となります。
セキュリティ対策アプリは有効なのか?
セキュリティアプリの導入も一定の効果はあります。とくに、バックグラウンドで不審な通信を検知する機能や、改ざんアプリを識別する機能があるものは安心感につながります。ただし、製造段階から仕込まれたマルウェアを100%防ぐことは難しく、あくまで“補助的な防御”として考えた方が現実的です。
最終的には、「信頼できる端末を選ぶこと」こそが最大のセキュリティ対策であり、そこを誤れば後悔は取り返しがつきません。
✅ 画像・チャット・資産情報までが抜き取られる危険がある
✅ 個人ユーザーでも、購入経路と保存データを工夫すればリスクを下げられる
✅ 安さだけで判断せず、販売元やレビューを必ず確認
✅ セキュリティアプリは効果的だが、端末選びの重要性には代えられない
さいごに
製造下請け現場が抱える“やむを得なさ”という現実
今回のマルウェア問題には、単純な「悪意ある中国製品」では片付けられない背景も存在していると指摘されています。報道では、スマホの製造工程において下請け工場が圧倒的なコスト削減を求められ、「あるソフトを入れてくれれば資金支援する」といった取引があったのではないか、という憶測も飛び交っています。
つまり、“現場が加害者”というよりも、“加担させられてしまった”という構図がある可能性もあるのです。これが事実であれば、問題は製造国に限定された話ではなく、サプライチェーン全体の構造的課題と言えるでしょう。
安さに飛びついた結果、リスクを招くユーザー心理
もうひとつ見逃せないのが、ユーザー側の姿勢です。私たちは「性能が高そう」「見た目が本物っぽい」「価格が安い」という理由だけで、正体不明の端末に手を伸ばしてはいなかったでしょうか。
「安さは正義」とも言えるネット社会の中で、価格と性能だけで判断する行動は珍しいことではありません。しかし、セキュリティという観点から見れば、その選択は“未来の自分に対する裏切り”になる可能性があるのです。
「中国製だからダメ」ではなく「背景と経路」を見る視点
SNSでは「中国製スマホなんて全部危ない」と断言する投稿も見られますが、すべてを一括りにすることは危険です。実際に、同じ中国製でも世界的に信頼を得ているブランドは数多く存在しており、問題は「どこが作ったか」よりも「どこで、どう流通しているか」にあります。
模倣品、改ざん品、非正規販売など、“安くて得に見える道”には常に裏があるものです。その背景を見抜く力が、これからの時代に求められています。
情報リテラシーが求められる時代に必要な意識とは
安さや流行に流されず、自分の目で見て考える。何を買うか、どこから買うか、何をスマホに保存するか──それらすべてが、自分の個人情報を守る行為です。
テクノロジーが進歩しても、私たちの意識が追いついていなければ、その便利さは毒にもなり得ます。中国製スマホを通じて問われているのは、「どの端末が危険か」ではなく、「どんな選択が危険を招くのか」という、本質的な問いなのかもしれません。
✅ 製造現場にも“加害者であると同時に被害者”という構造がある可能性
✅ 安さに飛びつく心理が、自分自身の情報を危険に晒しているケースも
✅ 「中国製=危険」と一括りにせず、背景や流通経路を見極めることが重要
✅ 最終的に情報を守れるのは、自分の判断とリテラシーにかかっている


