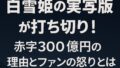↑話題の歌詞シーンはこちら↑
2025年5月、宇多田ヒカルさんが発表した新曲『Mine or Yours』が、ある一節をきっかけに大きな波紋を呼びました。
「令和何年になったらこの国で夫婦別姓が認められるのだろう」
――その言葉は、静かに、けれど確かに、社会の深層にある問題を照らし出しました。
夫婦別姓を望む声は、以前から確かに存在していました。
しかし、いまだに日本では制度として認められていません。選択的夫婦別姓が議論されるたびに、「なぜこだわるのか?」「名前が違うと何が困るのか?」といった声とともに、「くだらない」「どうでもいい」「うざい」といった反発や無関心も根強く見られます。
いつも思うんだけど、企業もタレントや歌をCMにする時は、ちゃんと精査しないと。 夫婦別姓は国民の7割が反対していて、かつ、子供の権利を蹂躙すると問題になっている案件なのに。 そんな危険な思想を宣伝している会社のお茶なんて、売れるのか? 自社の商品に、色つけてどうするんだよ。 日本コカ・コーラ株式会社、次の株式総会荒れるよ。
https://x.com/basilspicy79/status/1918853634412183688
それでも、こだわらざるを得ない人がいるのです。
仕事の場面で旧姓を使い続けたい人、結婚しても名前を変えたくない人、家族の在り方を自由に選びたい人――彼らが抱えるジレンマや不便は、当事者でなければ想像しにくいものです。
この記事では、こうした声や背景を整理しながら、
- 夫婦別姓に「なぜこだわる人がいるのか」
- 制度としての狙いやメリットは何なのか
- 日本ではなぜ進まないのか
- そして、なぜいまだに反対が根強いのか
といった点を、丁寧に解きほぐしていきます。
SNSの声や政治的動き、そして日常生活で感じる不便さまで、多角的な視点からこの問題を考えてみましょう。
この記事でわかること
✅ 夫婦別姓になぜこだわる人がいるのか、その背景
✅ 夫婦別姓の制度的な目的と実現による変化
✅ 日本における議論の歴史と制度化が進まない理由
✅ 反対派の主張とその根拠、世間のリアルな声
✅ 私たちの暮らしにどのように関係してくるのか
※この記事はSNS情報を中心に書かれていますが、意見や感じ方は人それぞれです。推測の域を出ず、異なる意見や見解があることも理解しておりますので、どうかご了承ください。本記事を通じて、少しでも多くの方に伝えられれば幸いです。
夫婦別姓とは何か?制度の基本と「なぜこだわるのか」

「夫婦別姓」と聞いて、どれほどの人が正確にその意味を理解しているでしょうか。
特に「選択的夫婦別姓」は、誤解されがちな制度の一つです。
現在の日本では、法律婚をする場合、夫婦はどちらかの姓に統一する必要があります。つまり、結婚=どちらかの名前を放棄することが前提です。
これに対し、選択的夫婦別姓とは「結婚後もお互いが自分の姓を名乗る自由を選べる制度」を指します。強制ではなく“選択”できる点が特徴です。
しかし、SNSや知恵袋のような場では、「なぜそんなに名前にこだわるの?」「くだらない」「どうでもいい」「うざい」などといった厳しい言葉が飛び交っています。
けれど、その“こだわり”の裏側には、切実な事情が隠れているのです。
たとえば仕事で旧姓を使ってキャリアを築いてきた人にとっては、姓が変わることが「別人扱い」されるほどの影響があります。行政書類や銀行口座、医療情報の名義変更も、現実にはかなりの手間がかかります。
また、「名前」は単なる記号ではなく、長年のアイデンティティそのものだという人も多く、特に女性側が一方的に姓を変える文化に違和感を抱く人も増えています。
一見すると「こだわりが強い人」と見られがちな夫婦別姓の主張ですが、実際は「変えたくない理由」がしっかりと存在し、それは日々の暮らしに直結する非常に現実的な問題なのです。
✅ 夫婦別姓の基本は「強制」ではなく「選択」の自由
✅ 仕事や書類上の不便、アイデンティティの分断が「こだわり」の背景
✅ 「どうでもいい」と切り捨てられない、現実に根差した声がある
夫婦別姓の狙いは何か?実現で得られるメリットとは
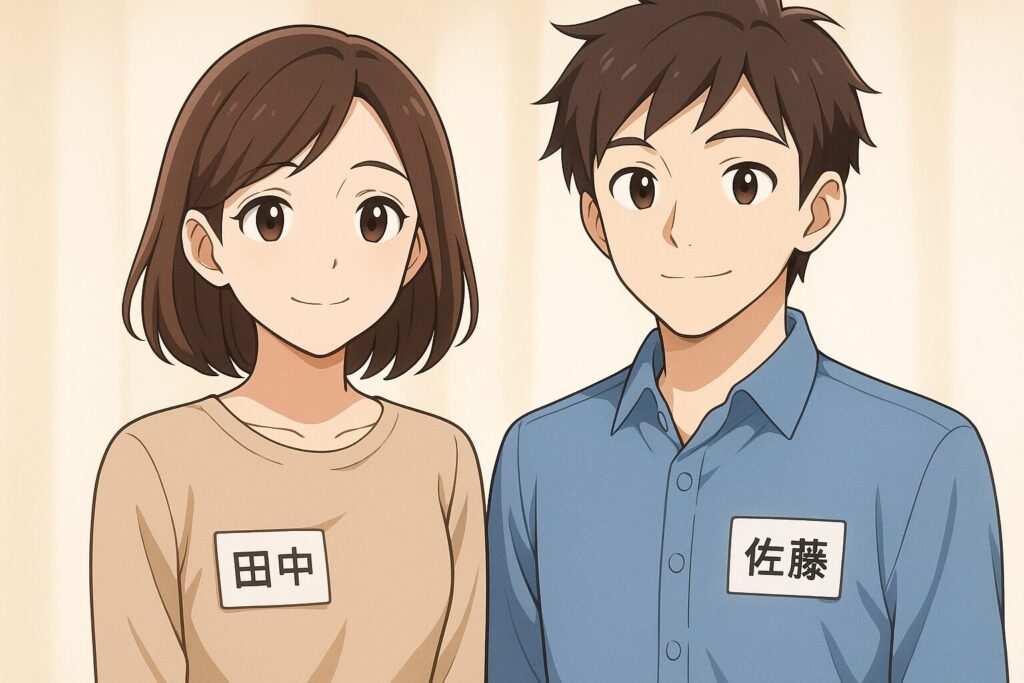
「夫婦別姓にこだわる理由は何か?」という問いは、裏を返せば「夫婦同姓に縛られることで、何を失っているのか」という問題でもあります。
夫婦別姓の狙いは、ただ名前を変えたくないという感情論ではなく、「人生の選択肢の確保」と「多様な家族観への対応」に根ざした制度設計にあります。
まず注目すべきは、自己決定権です。結婚しても自分の名前を名乗り続けられることは、個人の尊厳に関わります。特に長年にわたって旧姓でキャリアを築いてきた人にとっては、姓を変えることは実質的な「職業上の断絶」にもなりかねません。
また、夫婦同姓というルールのもとで「やむを得ず事実婚を選ぶ」カップルも少なくありません。実際に制度上の不便を覚悟しながら、姓を変えないために法律婚を避ける選択をしている人たちもいます。
さらに、多様な家族のあり方を認める社会への転換も大きな目的です。
「家族=ひとつの姓」という価値観は、時代とともに見直されつつあります。姓が同じであることが家族の証明ではなく、互いの信頼や尊重が家族の本質だと考える人が増えているのです。
なお、海外では別姓・同姓を選べる国が多数派であり、日本のように「強制同姓」を法律で定めている国は極めて少数です。選択肢を用意するだけで、実際には大半の人が「同姓」を選ぶとしても、制度の有無は大きな意味を持ちます。
✅ 夫婦別姓の狙いは「選択の自由」「尊厳の保持」「家族観の多様化」
✅ 姓を変えることで生じる社会的不利益や自己喪失を回避
✅ 日本だけが選択肢すら与えない制度である現実に目を向けるべき
なぜ日本では夫婦別姓が実現しないのか?制度上の壁と議論の経緯

日本で夫婦別姓が議論され始めたのは、実は1980年代後半から1990年代初頭にかけてです。法務省の審議会では1996年に「選択的夫婦別姓制度を導入すべき」とする答申も出されましたが、法制化には至っていません。
それから約30年、なぜ制度は動かないままなのでしょうか。
大きな壁となっているのが、「戸籍制度」と「家制度の名残」です。
日本の戸籍は“家”を単位として管理されており、夫婦は同一戸籍に入り、姓を一つにすることが前提です。これは明治時代に整えられた制度の影響で、「家の名前(=姓)」を守ることが、個人よりも優先されてきた歴史があります。
また、2015年の最高裁判決では「夫婦同姓は合憲」と判断されました。理由としては「通称使用も可能」「法律上の問題ではない」といった点が挙げられています。しかし、これは逆に制度の見直しを国会に委ねるという意味でもありました。
さらに、国会内での対立も根深く、与党内では慎重派が多く、制度導入に消極的な議員が主導権を握る状況が続いています。一方で野党(立憲民主党、共産党、れいわ新選組など)は法案提出に積極的であり、公明党も前向きな姿勢を見せていますが、国会全体としての合意形成には至っていません。
最新の世論調査では、「旧姓の通称使用でよい」という意見も一定数あり、実際に「夫婦別姓までは望まないが姓を変えたくない」というグレーゾーンのニーズが浮き彫りになっています。
✅ 制度が進まない背景には戸籍制度・家制度の構造的問題あり
✅ 最高裁判断は「合憲」だが、制度改革を否定したわけではない
✅ 与党内の慎重姿勢と世論の分断が、前進を妨げている
夫婦別姓に反対する人の理由と、その主張の中身

夫婦別姓の制度を望む声がある一方で、反対意見も根強く存在しています。
その多くは、家族観や社会制度、子どもへの影響を懸念するものであり、決して一方的に「非論理的」と切り捨てられるものではありません。
代表的な主張のひとつが、**「家族の一体感が損なわれるのではないか」**という懸念です。
同じ姓を名乗ることで心理的な連帯感が生まれるという価値観は、戦後の家制度から現在にかけて根強く残っています。特に年配層を中心に、「家族は一つの名字でまとまるべきだ」という意識が強くあります。
また、「子どもが混乱するのでは?」という意見もよく見られます。
両親が別姓だと、学校や医療機関などの場で、手続きや説明の手間が増えるのではないか、という現実的な心配です。これには一理ある面もあり、制度設計として「どちらの姓を子に与えるか」を明確にする必要性が出てきます。
他にも、「旧姓を通称として使えばよいのでは?」という意見も多く、これに関しては一定の法的整備も進んでいます。ただし、通称使用では公的な場では認められないケースも多く、根本的な解決にはなっていないという反論もあります。
SNSや知恵袋などでは、感情的な表現も多く見られます。
「うざい」「くだらない」「めんどくさい」「制度を変えるほどの問題ではない」といった投稿は、制度そのものへの関心の低さや、社会的変化に対する抵抗感を映し出しています。
✅ 反対意見の多くは「家族のかたち」に関する価値観に根差している
✅ 子どもへの影響や姓の管理コストを懸念する声も現実的
✅ 感情的な反発の裏には「変化への不安」や「制度への無関心」も存在する
さいごに:制度は誰のためにあるのか?問い直される家族のかたち
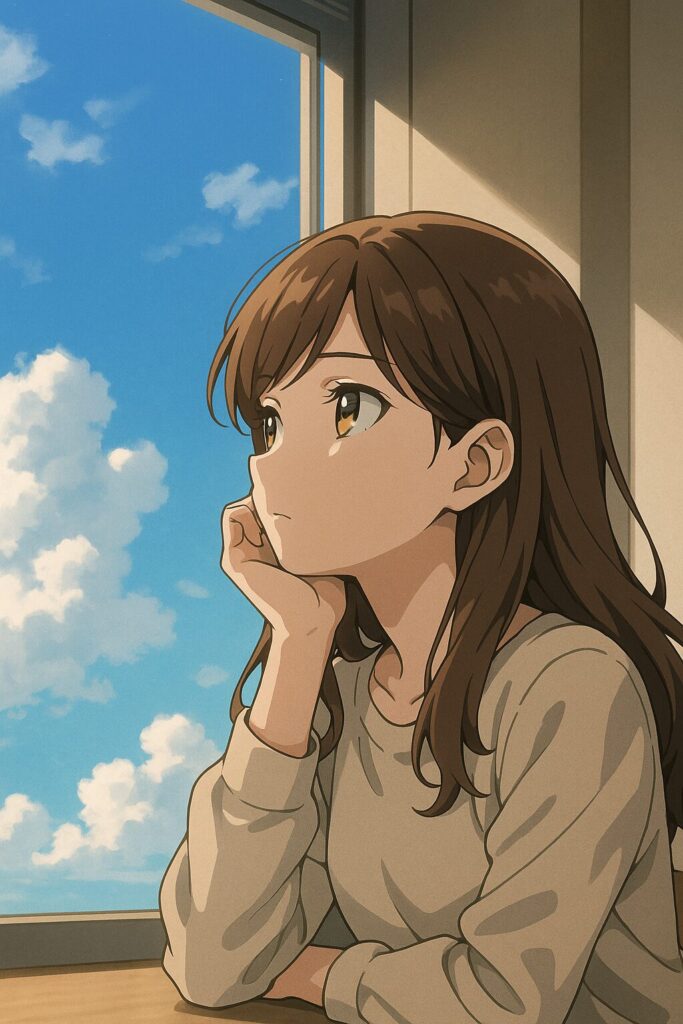
宇多田ヒカルさんの一節――
「令和何年になったらこの国で夫婦別姓が認められるのだろう」
この言葉がここまで注目されたのは、それが単なる歌詞ではなく、社会に根づく「不均衡」や「沈黙」に切り込んだからではないでしょうか。
結婚して姓を変えることに何の違和感も覚えなかった人がいる一方で、名前を変えたことで自分を見失いそうになった人もいます。
「そんなのこだわりすぎ」と言われても、当事者にとっては毎日のこと。免許証、保険証、銀行、職場…あらゆる場面で「旧姓のままでは通じない」現実があります。
夫婦別姓の議論は、「伝統」や「文化」を守るか、「個人の自由」を拡張するか、という単純な二項対立ではありません。
むしろ、制度とは誰のために、何のために存在しているのか――という根本的な問いを私たちに突きつけているのです。
「選択肢がある社会」は、必ずしも全員が別姓を選ぶことを求めているわけではありません。
ただ、“選べる自由”があるだけで、多くの人の暮らしが楽になる。
それは、制度によって「救われる人がいる」ということに、もっと目を向けていいのではないでしょうか。
今、ようやく国会では関連法案の提出が相次ぎ、議論も進み始めています。
制度の賛否を問う前に、まずはその「こだわり」に耳を傾けることから始めてみてはいかがでしょうか。
✅ 制度は一部の人の「生きづらさ」を軽減するために存在する
✅ 夫婦別姓は“押し付け”ではなく“選択肢”の話
✅ 宇多田ヒカルさんの発信が問いかけたのは、社会の無関心への違和感だった