選挙が近づくと、SNS上では候補者や政党による投稿、応援メッセージが溢れかえります。
そんな中、「未成年だけど、いいねを押したりリポストしても大丈夫なの?」という不安を抱く人は少なくありません。
SNSは自由な空間という意識がありながら、法律との線引きが見えにくいことで余計に戸惑うのです。
「意見を表明する自由」と「選挙運動の禁止」というルールの間で、どこまでがセーフでどこからがアウトなのか。
この疑問を解きほぐすことが、この記事の目的です。
過去に悩み、調べ尽くした経験をもとに、できるだけわかりやすく解説していきます。
この記事でわかること
・未成年がSNSでしてはいけない選挙関連行為
・「いいね」「リポスト」はどこまでOKかの判断基準
・SNS時代に必要なリテラシーと思考法
・今の法律が抱える課題と見直しの議論
※この記事はSNS情報を中心に書かれていますが、意見や感じ方は人それぞれです。推測の域を出ず、異なる意見や見解があることも理解しておりますので、どうかご了承ください。本記事を通じて、少しでも多くの方に伝えられれば幸いです。
未成年とSNS選挙活動の「大前提」を知る

未成年者に適用される公職選挙法のルール
SNSが生活に溶け込む現代、未成年であっても簡単に「いいね」や「リポスト」で選挙関連の投稿に触れることができます。しかし、公職選挙法では18歳未満の未成年者による「選挙運動」は全面的に禁止されています。
ここでいう選挙運動とは「特定候補者の当選を目的として有利な行為をすること」。意見を持つことは自由ですが、それを「誰かを勝たせる目的に変換する行動」は未成年者には認められていません。SNSの場でもこのルールがそのまま適用されるのです。
SNSでありがちな誤解と注意すべき行為
「SNSは自由な空間だから大丈夫だろう」と感じてしまうかもしれませんが、これは誤解です。候補者の投稿に「いいね」を押したり、応援メッセージ付きでリポストしたりする行為は、「意図」や「文脈」によって選挙運動と見なされることがあります。
たとえ軽い気持ちだったとしても、第三者が見て「応援目的」と解釈されればリスクが生じます。この「誰かの目線から見た解釈」こそ、SNS時代の新たな難しさと言えるでしょう。
意外と見落とす「いいね」やリポストのグレーゾーン
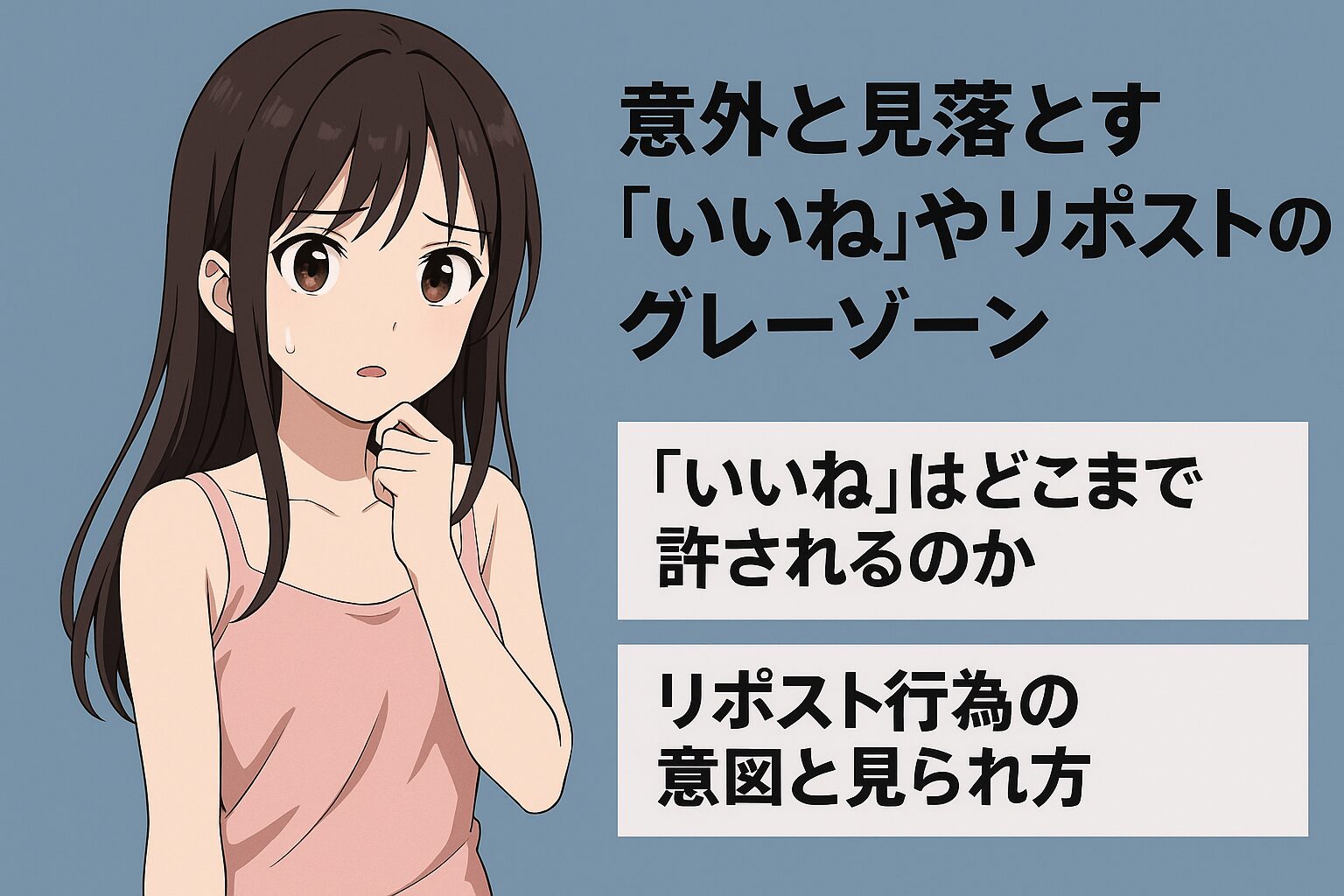
「いいね」はどこまで許されるのか
SNSでは何気ない「いいね」一つが、選挙運動とみなされる可能性があります。
例えば、特定候補者の選挙演説動画に「素晴らしい!」という意図をもって「いいね」をした場合、それが第三者から「応援」と解釈されれば、選挙運動と見なされるリスクはゼロではありません。
特に未成年の場合、この線引きがあいまいだからこそ注意が必要です。意見を持つ自由がある一方、選挙期間中の「いいね」にも慎重さが求められる時代になっています。
リポスト行為の意図と見られ方
リポストはより積極的な情報拡散手段とされます。候補者の投稿や支持メッセージをリポストする行為は、その行為自体が「応援意図あり」と見なされる場合が多く、未成年が行えば選挙運動として違法と判断される恐れがあります。
「ただ共有しただけ」という言い訳が通用しないことがあるのは、SNSの特性として「誰かの意思を広める力を持つ」ためです。未成年にとって、SNS上での拡散行為が「選挙運動」と解釈される境界は、非常にグレーでリスクを内包しています。
SNS時代に必要な知識と冷静な判断力

情報リテラシー教育の重要性
SNSでは膨大な情報が流れ、未成年者も日常的に触れる機会があります。しかし、この自由な空間だからこそ「情報をどう見極め、どのように行動するか」が重要です。
たとえば、候補者を紹介する投稿が拡散されていても、それがどのような意図で発信されているのか、信頼できる情報かどうかを冷静に判断するリテラシーが求められます。
未成年者は特に、自分がどんな意図で「いいね」や「リポスト」をするのかを自覚することが重要です。
「誰かの意見をうのみにせず、公式情報や一次情報にあたる」。こうした態度こそがSNS時代を生きるうえでの基本的なスキルと言えるでしょう。
制度の不備とこれからの課題
現行の公職選挙法はSNSが普及する以前のルールを基準に設計されています。そのため、メール転送はNGだがSNSメッセージならOKといった分かりづらい規定が残っています。
こうした不合理は、未成年者にとって「何が正しくて、何が危ないのか」をよりわかりづらくしています。
この状況を改善するには、単なる注意喚起だけではなく制度そのものの見直しが不可欠です。これからの時代に即した、わかりやすいルールづくりが急務だと言えるでしょう。
さいごに
未成年も「関心」と「慎重さ」を両立させよう
SNSは私たちが気軽に意見を共有できる場ですが、未成年には「選挙運動」という法律上の制約があります。
「いいね」やリポストすらも文脈次第では違反と見なされる可能性がある現状は、未成年にとって厳しい側面かもしれません。
しかし、政治への関心を持つこと自体は悪いことではありません。大切なのは、現行ルールを知り、その枠内で正しく関わることです。公式情報に目を通し、周囲と冷静に議論することは大いに歓迎される行動でしょう。
また、今の制度が時代遅れだという批判があるのも事実です。だからこそ、こうしたルールについて理解を深めた上で「改善が必要だ」と声をあげることこそ、未来を変える第一歩になるはずです。
公職選挙法の関連条文(引用)
公職選挙法第137条の2(未成年者の選挙運動の禁止)
何人も、年齢満十八年未満の者をして選挙運動をさせ、又は選挙運動のためにこれを利用してはならない。
年齢満十八年未満の者は、選挙運動をすることができない。
公職選挙法第142条の2(インターネット等を利用する選挙運動)
選挙運動においては、インターネット等の情報通信の技術を利用することができる。
ただし、公職選挙法その他の法令の規定に違反しない限りにおいて行うものとする。
公職選挙法第129条(選挙期日の公示又は告示前後における文書図画の頒布等の制限)
投票日当日において、いかなる者も選挙運動をすることができない。
(出典:公職選挙法)
※本引用は主要な要点を抜粋したものであり、詳細については必ず公職選挙法(e-Gov法令検索等)でご確認ください。https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100


