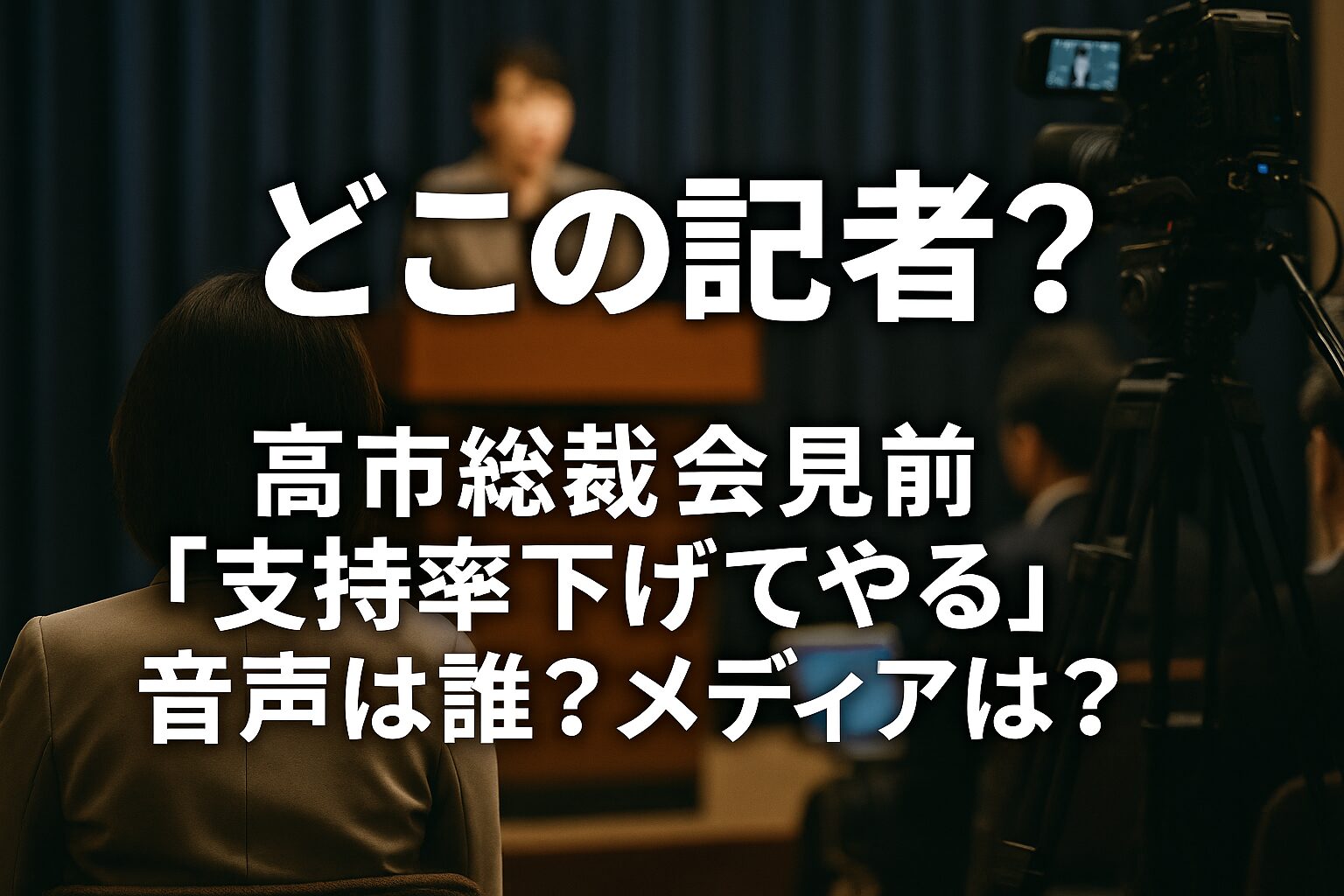※画像はイメージです
※問題のシーンへ飛びます(現在はカットされているようですね)
2025年10月7日
自民党の高市早苗さんが新総裁として初めての会見に臨む直前、記者席の一角から、
「支持率下げてやる」
「支持率下げることしか書かないぞ」
という声が入ったとされる動画が拡散されています。
この映像はSNS上で急速に広がり、
「どこの記者なのか」
「どこのメディアが発した言葉なのか」
と多くの人々の関心を集めています。
一方で、SNSで広まっている動画の出所や真偽については不明な点が多く、放送中の映像の一部が切り取られたものではないかとの指摘もあります。
SNS上では、「報道機関の本音が出たのでは」と怒る声がある一方で、
「冗談や雑談が誤解されたのでは」
「AI生成音声の可能性もある」
とする冷静な見方もあり、議論は真っ二つに割れています。
この記事では、
・この動画がどのように拡散したのか
・発言したのは誰なのか、どこの記者なのか
・映像と音声の検証で分かっていること、不明な点
・報道倫理と放送法の観点から見た問題点
これらを整理しながら、現時点で分かる限りの状況を解説していきます。
※この記事はSNS上で共有された情報を中心に構成しています。
内容には推測を含む部分があり、異なる見解が存在する可能性もあります。
さまざまな意見を尊重しつつ、読者の判断に資する情報提供を目的としています。
高市総裁会見前に広がった“記者音声”の噂とは

10月7日午後に拡散されたこの動画・・・
高市早苗さんが新たに自民党総裁として登壇する直前、会見場の空気は静まり返っていました。
その直後、待機中の記者席から
「支持率下げてやる」
「支持率下げることしか書かないぞ」
という声が拾われたとする動画がSNSに投稿されます。
最初に話題となったのは、X(旧Twitter)上での拡散でした。
投稿は数十分のうちに数十万回再生され、「どこの記者?」「放送中にこれが聞こえた」といった反応が相次ぎます。
動画の一部には「日テレの生中継映像では」とされる情報も添えられていましたが、どの番組の録画なのかを特定できる明確な証拠はありません。
SNSでは、当該発言の存在を取り上げる投稿が次々と掲載され、瞬く間にトレンド入りしました。
一方で、いずれの記事も「発言が確認された」としながらも、その音声が本物かどうかを検証したわけではありません。
サキガケさん、いい加減にしたらどうだい 音声がAI生成のフェイクである可能性を指摘するコメントが存在するのに、無視して本物扱いするのは論理的誤りで、検証不足の浅はかさを露呈。
https://x.com/WxpvxabXLp6M/status/1975546218638901607
この広がりの背景には、
「マスコミは信用できるのか」という長年の疑念があります。
とくに政治報道では、報じる側の姿勢が“公平かどうか”という視点で厳しく見られてきました。
今回の音声が事実なら、報道機関への信頼が大きく揺らぐことになります。
ここ数年でのマスメディアの害悪さがあまりにも目に余る 外国人問題とか減税とかよりまずこっちをなんとかしてほしい
https://x.com/okome_o_/status/1975543648503947593
しかし、SNSに投稿された動画は部分的で、会見前後の文脈が切り取られている可能性もあります。
単なる冗談や待機中の雑談が、緊張感のある場面と重なったことで誤解されたのかもしれません。
そのため、現時点で「誰が言ったのか」を断定することはできません。
動画の拡散と同時に、「この声は編集されているのでは」「音の重なり方がおかしい」と分析するユーザーも現れました。
音声解析を試みる投稿者もいますが、専門的な検証結果は出ていません。
つまり、今わかっているのは「そう聞こえる音声が拡散された」という事実のみ。

本物か偽物かを判断するには、放送局側の映像データと照合する以外に方法がないのです。
✅ まとめ
・「支持率下げてやる」「支持率下げることしか書かないぞ」という声が聞こえる動画が拡散。
・SNS上で急速に広まり、「どこの記者か」と注目を集めた。
・出典が不明で、映像の真偽は確認されていない。
・断定よりも、慎重な検証が必要な段階。
“どこの記者なのか”という疑問と現時点の検証状況

動画が拡散されるにつれ、もっとも多く寄せられたのが「どこの記者なのか?」という問いでした。
投稿のコメント欄には、
「放送局の中継音声ではないか」
「報道各社のマイクが拾ったのでは」
といった推測が相次ぎました。
しかし、現時点でその根拠は明確ではありません。
SNSで広まった映像の多くは、元の放送を直接録画したものではなく、他の投稿者が再編集した“切り抜き動画”の形式を取っています。
ノーカット版はこちら(Youtube)
※問題のシーンへ飛びます
映像の解像度や音声の波形も低く、どこの誰か特定するのは困難です。
また、報道現場では複数社のマイクが並び、どの音声がどの機材で拾われたかを把握するのは容易ではありません。
各社のマイクには社名ロゴが入っているものの、今回拡散された映像では画面が粗く、判別できる情報は確認されていません。
さらに、記者クラブでは取材席の位置が概ね固定されており、「あの角度なら〇〇社の担当ではないか」といった推測もありますが、これも裏づけのある情報ではありません。
いずれにせよ、どの担当記者が現場にいたのかという記録が公表されない限り、個人や企業を特定することはできません。
ネット上では「声紋分析すればわかる」「記者の声を照合できる」といった意見も見られますが、実際には個人の声紋を扱うには法的・倫理的な制約があります。
そのため、SNS上の“特定班”が発信する憶測の多くは、裏付けの取れない範囲にとどまっています。
また、当該とされる記者クラブから、公式なコメントや調査発表は現時点で確認されていません。もし本当にその場での発言であったとしても、雑談や冗談の切り取りである可能性も指摘されています。
つまり、“どこの記者か”という問いは多くの人の関心を集めつつも、確証を持てる情報はまだ一つもないのです。
✅ まとめ
・動画は切り抜きや再編集の可能性も?
・記者席やマイク配置からの特定は難しい。
・報道各社は沈黙を保っており、断定は現時点で不可能。
SNSの反応:“どこの社?”をめぐる憶測と怒り
この動画が拡散されてから数時間のうちに、SNS上ではさまざまな反応が噴出しました。
「どこの社だ?」
「本音が漏れたのか」
と憤る声が圧倒的に多く、政治報道への不信が改めて浮き彫りになりました。
特に、
「報道機関が公平ではない」
「最初から印象操作をしているのでは」
という書き込みが相次ぎ、いわゆる“偏向報道”という言葉が再び注目を集めました。
これが本当ならばこいつらのやってることは取材ではなく、自分が支持率を下げるための活動。てか、どこのオールドメディアだよ。おまえらが支持率下げられるくらいの影響力があると思ってるのか?
https://x.com/aiai0510/status/1975536222392201586
中には
「報道倫理に反する」
「事実なら重大な放送法違反だ」
として、BPO(放送倫理・番組向上機構)による調査を求める意見もありました。
(国内放送等の放送番組の編集等)
参照:放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)
第四条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
2 放送事業者は、テレビジョン放送による国内放送等の放送番組の編集に当たつては、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を視覚障害者に対して説明するための音声その他の音響を聴くことができる放送番組及び音声その他の音響を聴覚障害者に対して説明するための文字又は図形を見ることができる放送番組をできる限り多く設けるようにしなければならない。
これ実際かなりヤバイ案件だと思うんだけど 他のオールドメディア絶対にとりあげないだろうし SNSでじゃんじゃん拡散するしかないよね
https://x.com/human_ver2/status/1975538026504933683
SNSでは、動画を引用しながら
「これは放送事故ではない」
「もうメディアを信用できない」
という投稿が共有され、いわば“怒りの連鎖”が生まれていきました。
一方で、こうした急速な拡散に警鐘を鳴らすユーザーも少なくありません。
「編集された音声かもしれない」
「冗談や雑談を切り取った可能性もある」
と冷静な意見を述べる人たちもおり、反応は明確に二極化していました。
特に、AIによる音声生成の進化を踏まえ、「こうした短い動画だけで本物かどうかを判断するのは危険だ」という意見は増えています。
フェイク音声の可能性や、切り抜き編集による誤解など、情報の信頼性をめぐる議論はかつてないほど活発になりました。
このように、SNS空間では「信じる側」と「疑う側」が激しく対立しています。
前者は報道への不信を爆発させ、後者はデジタル時代の情報拡散に冷静さを求めている。
まるで鏡のように、現代の社会不信と情報疲弊が同時に映し出された出来事だったといえます。
SNSの特性として、怒りや不信の言葉は拡散されやすく、冷静な分析は埋もれがちです。
その結果、「どこの記者か」という問いが感情的な糾弾へとすり替わり、検証よりも“敵探し”のムードが強まってしまう傾向が見られました。
✅ まとめ
・SNSでは「どこの社か」をめぐる憶測が爆発的に拡散。
・報道の公平性に対する不信感が再燃。
・冷静派は「AI音声や編集の可能性もある」と指摘。
・世論は二極化し、“怒り”と“慎重さ”がせめぎ合っている。
報道機関の対応と放送倫理の観点から見た問題点
今回の音声をめぐる騒動は、単なる“放送事故”の範囲を超えて、報道の在り方そのものを問うものとなりました。
現時点で、放送各社や記者クラブから公式なコメントは出ていません。
どの社も沈黙を続けるなか、視聴者の間では「説明責任を果たすべきではないか」という声が高まっています。
報道機関は、社会の出来事を公平に伝える立場にあります。
日本の放送法第4条では、放送事業者が番組を編集する際に「政治的に公平であること」「報道は事実をまげないですること」などの原則が定められています。
つまり、放送局には“中立的であること”が法律で求められているのです。
このため、もし記者の発言が実際にあったとしても、それが取材意図ではなく個人の冗談や雑談であったとしても、放送内に混入した時点で「報道の信頼を損ねる行為」と見なされる可能性があります。
それは、報道が事実に基づくという前提を揺るがすからです。
一方で、新聞やネットメディア、個人発信のSNSには、放送法のような厳密な「公平性義務」は課されていません。
そのため、「報道」という言葉の中でも、法律上の立場には大きな差があります。
今回のように“映像がネット上で独り歩きする”ケースでは、どの法規制の対象になるのかが非常にあいまいになります。
この構造的なズレが、国民の“報道への不信感”を増幅させています。
視聴者から見れば、「誰が本当のことを伝えているのか」が分からなくなってしまう。
情報が氾濫する時代だからこそ、メディア自身の透明性が一層求められています。
信頼を取り戻すためには、報道機関自らが検証結果を公表し、誤解があれば正す姿勢を見せることが不可欠です。
沈黙を続けることは、誤解や不信をさらに広げるだけになりかねません。
✅ まとめ
・放送法第4条では「政治的公平性」「事実報道」が定められている。
・SNSやネットメディアは同法の対象外。
・報道の信頼を守るには、説明責任と検証公開が不可欠。
・沈黙は信頼回復の障害になる可能性がある。
まとめ:どこの記者かは不明、だが問われているのは“報道の姿勢”
拡散された動画をめぐる一連の騒動は、今なお真相がはっきりしていません。
「支持率下げてやる」「支持率下げることしか書かないぞ」という声が、実際に記者席から発せられたのか。
あるいは編集や加工によって作られたものなのか。
その判断を下すための確かな証拠は、現時点で公開されていません。
「どこの記者か」「どこのメディアか」という問いは、SNSで広く共有され、多くの人が真実を知ろうとしています。
しかし、現段階では特定に至るような公式情報も、報道機関からの説明もありません。
この状況で最も重要なのは、怒りや感情よりも“検証”の姿勢です。
SNSの投稿は瞬時に広がりますが、その中には誤情報や誇張された内容も混じります。
見出しや短い動画だけで判断することは、結果として誰かを傷つけることにつながりかねません。
報道に対して厳しい目が向けられている今だからこそ、私たち受け手もまた、情報を見極める冷静さを持つ必要があります。
報道機関が透明性と説明責任を果たす一方で、社会全体が「正確さを確かめようとする姿勢」を取り戻すことが求められています。
今回の件は、単に“どこの記者が発言したか”という話ではありません。
それ以上に、情報をどう扱うか、どう信じるかという、私たち一人ひとりの課題を浮き彫りにしました。
真実を急ぐよりも、事実を丁寧に確かめる。
その積み重ねが、報道の信頼を再び取り戻す唯一の道なのかもしれません。
✅ まとめ
・音声の真偽は確認されておらず、特定には至っていない。
・報道の透明性と説明責任が改めて問われている。
・SNSの時代には「疑うより、確かめる」姿勢が大切。
・私たち受け手にも、冷静な検証意識が求められる。