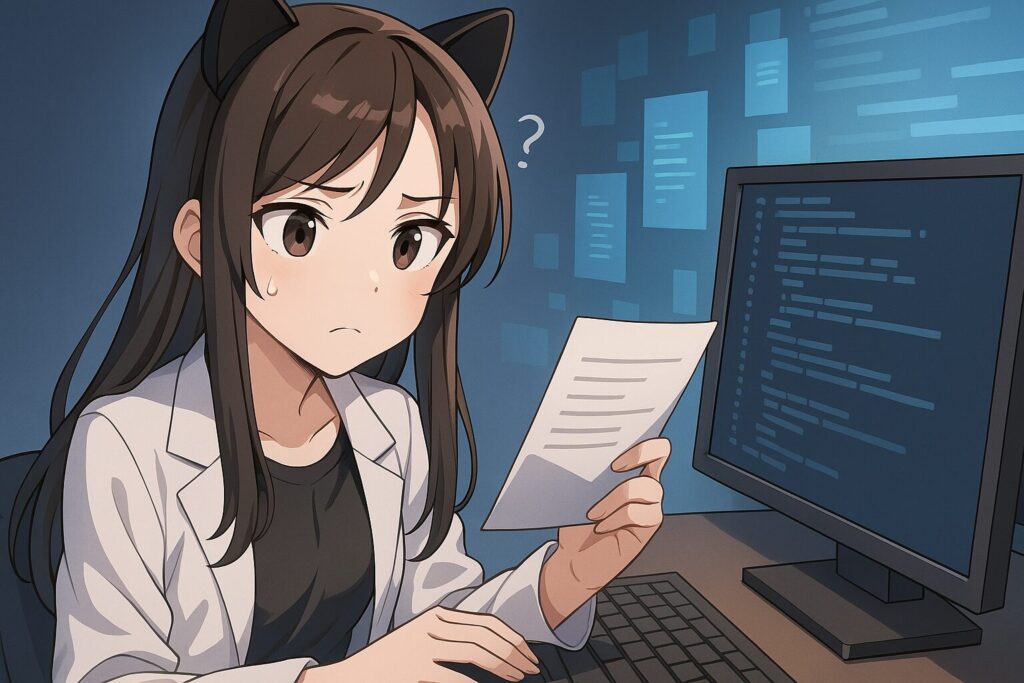
生成AIとDLSS、あなたは違いを説明できますか?
私がこの問題に関心を持つようになったのは、ある日突然「イラストがAIに学習された」とSNSで見かけることが増えてきたことがきっかけでした。
何の許可もなく、誰にも相談されず、ただネットに投稿しただけの画像が“素材”として扱われていた、というのです。信じられない思いと同時に、「これが未来なのか」と言い聞かせようとした自分もいました。
ですが、2025年4月、経済産業省が発信した「AIに愛を」という言葉には、正直なところ背筋が凍りました。
同じタイミングで、声優さんの声を無断で学習する行為は「不正競争防止法上、違法になり得る」との発表があったからです。
山田太郎参議院議員は4月2日、声優の声を無断で学習した生成AIの問題について、場合によって不正競争防止法(不競法)違反になるとの見解を、経済産業省から引き出したと明かした。声そのものの権利を守ることに特化した法律はないが、経産省は現行の不競法の考え方を整理し、対処できる事例があると示したという。
https://www.itmedia.co.jp/aiplus/articles/2504/03/news140.html
山田議員によると、経産省は俳優・声優の肖像や声が不競法における「商品等表示」に当たると認めたという。商品等表示は、どのような人物がその商品や業務を提供しているのか分かる表示を指す。今回経産省は、この商品等表示に照らし、声優の声を無断で学習した生成AIの利用が問題になるケースがあると明示したという。
https://www.itmedia.co.jp/aiplus/articles/2504/03/news140.html
「一体どちらを信じればいいのか」——
私と同じように困惑した方は少なくないはずです。
さらに、話題は任天堂Switch2に搭載されると噂の「DLSS(Deep Learning Super Sampling)」にまで波及しました。これもAIを使った技術である以上、「無断学習ではないのか?」という疑念が噴き出し、SNSでは炎上状態に。経済産業省、任天堂、NVIDIA、それぞれへの疑念と擁護が錯綜するなか、議論は激しさを増すばかりです。
この記事では、生成AIとDLSSの違いや類似点、なぜクリエイターが怒っているのか、そしてこの問題の本質はどこにあるのかを、私自身の失敗や体験も交えてお話していきます。専門用語をなるべく使わずに、誰にでも理解できるように書いています。どうか、一緒にこの問題の深層を見つめてみてください。
この記事でわかること
- 経産省のAI政策に見られる矛盾点とその社会的波紋
- DLSSと生成AIの技術的な違いと、議論の混乱ポイント
- 「無断学習」がなぜ問題とされているのか
- クリエイターたちの現場感と、経済的損失の実態
- 今後のAI技術と社会の関わりに必要な視点とは?
※この記事はSNS情報を中心に書かれていますが、意見や感じ方は人それぞれです。推測の域を出ず、異なる意見や見解があることも理解しておりますので、どうかご了承ください。本記事を通じて、少しでも多くの方に伝えられれば幸いです。
声優の無断学習を違法と認めたのに?経産省のAI推進政策が物議を醸した理由

私が初めて「声優の声がAIに勝手に学習された」というニュースを見たとき、正直、何が問題なのか理解しきれていませんでした。しかし、『自分の創作物が知らぬ間に“素材”にされた』と想像するだけでも、それがどれほど傷つくことか痛いほど分かります。あれは、人格そのものを盗まれたような感覚なのかもしれません。
そんな中で、国会議員である山田太郎さんが、経産省に「声優の声を無断で使う生成AIは、法律に違反しうる」と認めさせた、という報告が飛び込んできました。
これは、クリエイターの権利を守る上で大きな一歩でした。「ようやく国が、現場の苦しみに気づいてくれた」と、多くの仲間が胸をなでおろした瞬間だったと思います。
ところが、その数日後、経産省の公式アカウントが発信したのは、真逆とも思えるキャンペーンでした。「AIに愛を」というテーマで、サイバーエージェントが開発した、AIによってタレントや広告素材を自動生成するサービスを、好意的に紹介したのです。
この投稿を見たとき、私は画面を二度見しました。「あれだけ“無断学習は問題だ”と言っていたのに、今度はAIが作るタレントを推すの?」と。SNSでも同じような戸惑いや怒りの声が相次ぎました。「ダブルスタンダードだ」「人権を軽視している」との批判が飛び交い、結果的にこのキャンペーンは大炎上することになります。
政策と実態がこんなにも乖離してしまう背景には、AI技術に対する認識のズレがあるのだと思います。現場の人間は、日々「無断で模倣される恐怖」と向き合っているのに、制度を設計する側は「効率」や「経済性」だけを見ている——そんな印象を強く持たざるを得ませんでした。
そして、この混乱の中で話題になったのが、任天堂Switch2に搭載されるとされる技術「DLSS」だったのです。
✅「声優の無断学習」を違法とした直後の“生成AI礼賛”に矛盾の声
✅ 国の方針に「誰を守るつもりなのか」との疑問と批判
✅ クリエイター現場と政策担当者の認識のギャップが露呈
DLSSは本当に無断学習なのか?技術的な違いとすれ違う認識

「生成AI」と聞くと、多くの方が「イラストを勝手に模倣された」「声が無断で使われた」といった被害体験を思い浮かべるかもしれません。知らぬ間に“学習素材”とされていた、という経験をした人も増えてきたのではないでしょうか。そのため、「AIに学ばせる」という言葉に、敏感にならざるを得ませんよね。
そんな中、「DLSS(Deep Learning Super Sampling)」もAIの技術だと聞いて、私は強い警戒心を抱きました。「また誰かの創作物を無断で使ってるのでは?」と疑ってしまったのです。けれど、調べていく中で、DLSSと生成AIは構造がまるで異なることを知りました。
DLSSとは、ざっくり言えば「低い解像度の映像を、AIで高解像度に補完する技術」です。
その学習に使われるのは、企業が自社でシミュレーション生成した映像データであると説明されています。つまり、ネット上の画像や他人の著作物を勝手に収集して学習する、という生成AIのやり方とは明確に一線を画しているのです。
実際、DLSSは任天堂や多くのゲーム会社から正式なライセンス契約を得て活用されている技術です。「あくまで処理補助技術であって、著作物を出力するわけではない」という立場も多く見られました。これには納得できる部分もあります。
ただし、問題となっているのは、その「学習データ」が一般公開されていない点です。
「生成AIは非公開のデータを使っているから不透明」と批判していたのに、DLSSに関しては「任天堂やNVIDIAだから信用できる」と言うのでは、たしかにダブルスタンダードと受け取られても仕方がないのかもしれません。
私自身、クリエイターという立場で疑心暗鬼になる気持ちは痛いほど分かります。でも、だからこそ冷静に、技術の仕組みやデータの出所について事実ベースで見ていく必要があると感じています。
✅ DLSSは「自社データを使った補間技術」で、生成AIとは仕組みが異なる
✅ ただし、データセット非公開の点で疑念を持つ声も多い
✅ 技術的な違いを理解せず「一括りにAI」として議論するのは危険
クリエイターたちの怒りと、生成AIによる仕事喪失の現実

この数年、SNSでは何人ものクリエイターが「AIにやられた」と肩を落とす姿を見てきました。特に印象的だったのは、ある声優さんが、「自分の声を勝手に合成され、まるで自分が何かをしゃべったように使われていた」と苦しそうにSNSで打ち明けていたときのことです。
クリエイターの仕事は、単なる“素材の提供”ではありません。
声も、絵も、文章も、その人の感性と経験、努力の結晶です。それが無断で吸い取られ、さらに生成された“まがいもの”に仕事を奪われていく——こんな状況が、今現実に起きているのです。
近年では、広告業界やエンタメ業界で「AIタレント」「自動生成キャラクター」が次々と登場しています。私はこれに対し、技術そのものへの否定ではなく、「雇用の切り捨て」が起きていることに強く問題意識を持っています。なぜなら、AIによる“置き換え”は、コストカットの名のもとに、人を切り捨てることと表裏一体だからです。
さらに深刻なのが、性被害につながるディープフェイクの存在です。
SNSでは「卒業アルバムを悪用したフェイクポルノ」が拡大しているとの報道もありましたが、これもまた、生成AI技術の裏の顔といえるでしょう。人の顔や体を、本人の許可なく合成して流通させることが、現実に起きているのです。
クリエイターの多くは、単に「技術に嫉妬している」のではありません。生身の人間の尊厳や生活、安心感を守るために、「これは超えてはいけない」と声を上げているのです。
✅ 生成AIによって、声優・イラストレーター・役者などの仕事が奪われ始めている
✅ 人の姿や声を無断使用し、倫理を踏みにじるディープフェイクが増加
✅ 「技術の進歩」よりも「人間の尊厳」を守るべきという声が広がる
DLSSと生成AIを巡る分断、あなたはどちらの立場ですか?
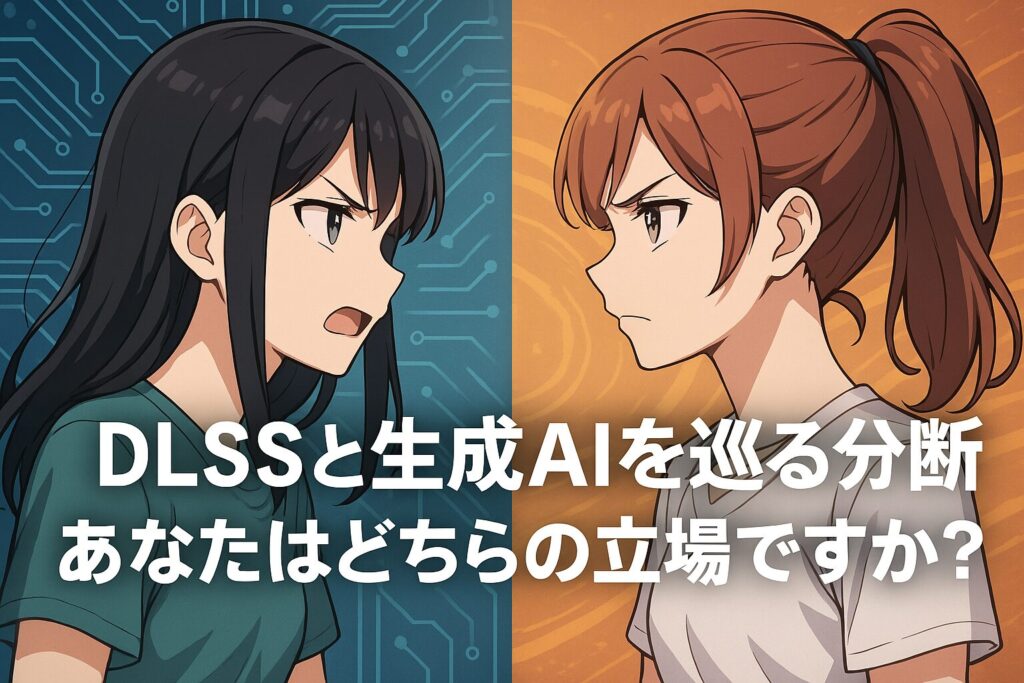
私がこの話題をSNSで追い続けている中で、もっとも心が痛んだのは、「反AI」「推進派」といった単純なラベルでお互いを攻撃し合っている姿でした。
「DLSSは合法だから文句を言うな」「生成AIは全部同じに見える」「任天堂やNVIDIAを信じないのは陰謀論者」——そんな極論が飛び交う中で、落ち着いた議論はどこかへ消えてしまったように感じます。
私は、AI技術そのものを全面的に否定するつもりはありません。実際にAIによって便利になった部分もあり、未来の可能性もあると感じています。ただ、「無断で人の創作や人格を模倣する」ことに対しては、どうしても受け入れられないのです。
一方で、「DLSSは生成じゃない」「ただの補完技術に過ぎない」という意見にも一理あります。けれども、それを一方的に擁護しすぎると、「じゃあ、生成AIも補完って言い張ればOKなの?」という疑念も生まれてしまうのです。
【肯定・推進派の反応】
◆ DLSSは合法、生成AIと混同すべきでない
✅「DLSSはゲーム会社と正式契約を結び、内部データを使って学習している。無断クローリングとは仕組みが違う」
✅「DLSSは自社シミュレーションデータで構成されており、著作物を使う生成AIとは根本的に異なる」
✅「任天堂やNVIDIAが法的リスクを取ってまで違法な無断学習に手を染めるはずがない」
◆ 無断学習の線引きには無理がある
✅「AI技術の多くはもはやデータ補間や変換の恩恵で成り立っている。DLSSを含めて否定するのは現実的でない」
✅「今の社会では多くの技術が学習や解析に基づいている。『無断』かどうかだけで議論するのは本質を外している」
【否定・規制派の反応】
◆ DLSSにも無断学習の懸念がある
✅「DLSSのデータセットは非公開。生成AIと同様に学習元の開示がなければ信用できない」
✅「生成AIは批判されてDLSSは免除というのはダブルスタンダード。任天堂だからって信じるのは感情論」
✅「学習データが非公開なら“クリーン”の証明はできない。企業だから信頼できるというのは甘い」
◆ 経産省の姿勢に強い不信感
✅「声優の無断学習は違法だと発表しておきながら、経産省がサイバーエージェントの生成AI広告を称賛するのは矛盾」
✅「“AIに愛を”というキャッチコピーは、クリエイターの実害を無視しており不誠実」
✅「パブコメを募集しても読んでいないのでは?国民不在の政策決定に怒りの声」
【中立・調整派の意見】
◆ 分断ではなくガイドラインが必要
✅「AI自体を否定するのではなく、出力内容や使い方を基に規制すべき」
✅「DLSSも生成AIも一律で否定するのではなく、合法かどうかを具体的に検証すべき」
✅「“無断学習”というワードに囚われず、今後はクリエイターとの共存を考えたルール作りが求められる」
◆ 誤解と混同を正すべき
✅「DLSSはあくまでアップスケーリング技術。生成AIと構造が異なる点を理解すべき」
✅「画像生成AIや音声生成AIの無断学習と、DLSSのような補間型AIでは倫理・法的リスクの次元が違う」
✅「技術的な背景が複雑なため、レッテル張りで議論するべきではない」
✅まとめ
- ✅ 肯定派は「DLSSは合法で生成AIと異なる」として擁護
- ✅ 否定派は「DLSSも非公開データなら疑わしい」として警戒
- ✅ 中立派は「分断よりもルール整備を優先すべき」と主張
- ✅ 経産省のダブルスタンダードと情報発信の一貫性への疑問が炎上の背景に
技術の違い、使い方の違い、そして目的の違い——それを正しく伝える仕組みがないことが、この分断を加速させているように思えてなりません。
何より重要なのは、「どこまでが許され、どこからがアウトなのか」というルール作りです。そしてそれは、技術開発者だけでなく、私たち表現者や利用者自身も参加していくべき議論ではないでしょうか。
✅ 「反AI」「推進派」という二元論では語れない現実
✅ 技術の違いと倫理観の線引きが混乱の原因に
✅ 対立ではなく“共存”を目指すための対話が必要
さいごに:正しさを決めるのは、熱狂ではなく誠実な対話
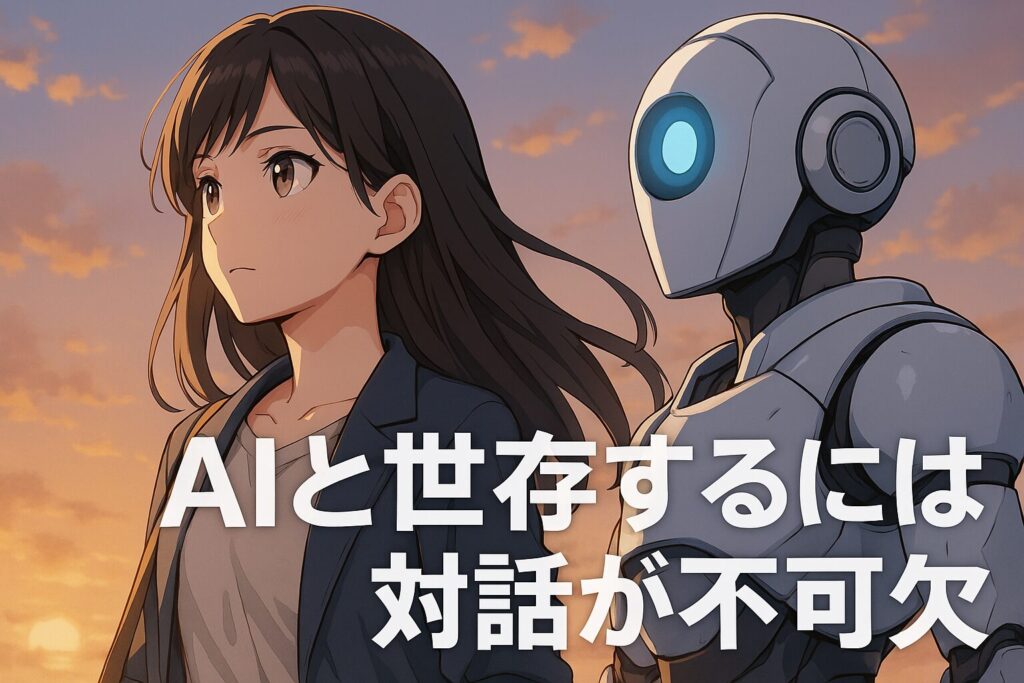
私がこの記事を書いたのは、「AI技術をすべて否定したいから」ではありません。むしろ、どんな技術であれ、それが人を幸せにするなら、きっと意味があると信じています。
しかし、今の生成AIやDLSSを巡る議論の多くは、感情やレッテルに支配されてしまっています。「AIを使う人間は敵だ」「反AIは進歩の邪魔者だ」——そんな言葉が飛び交うたびに、本当に大切な論点が置き去りにされていると感じるのです。
技術は中立です。問題は、それをどう使い、どう守るかです。
無断学習、仕事の喪失、尊厳の侵害。これらは誰にでも起こり得る問題であり、たとえ今は“関係ない”と思っていても、いつか自分の作品や声が使われている側になるかもしれません。
だからこそ、私たちは今こそ問わなければならないのです。「どこまでを許容するのか」「誰の権利を守るのか」「どうやって共存するのか」を。
経済や効率だけでは語れない、人間としての“尊さ”が、技術の進歩の中でどう扱われるべきか——その視点を失わずに、議論を続けていきたいと強く思います。
もし、あなたがAI技術に希望を感じているなら、それは素晴らしいことです。でも、その一方で、声を失ったクリエイターがいることも、どうか心に留めてください。
そしていつか、この分断が対立ではなく「対話」へと変わることを、私は本気で願っています。
✅ 技術の正しさは、対話と理解からしか生まれない
✅ AIの進歩と人間の尊厳は両立できると信じたい
✅ 大切なのは「排除」ではなく「共存」を前提とした議論


