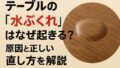ある日、ラジオから流れてきたあいみょんさんの「マリーゴールド」。
そのサビに差しかかる瞬間、ふと懐かしさを覚えた人がいました。
「このメロディ、どこかで聴いたことがある」。
そう感じた多くの耳がたどり着いたのは、1999年発売のゲーム『メダロット2』のBGMでした。
指摘の中心は、サビの冒頭のわずか数秒。
上昇する旋律と抑揚のニュアンスが、メダロット2の一部BGMの出だしと重なって聞こえる――
そんな声がSNSや動画サイトを中心に広がっていきました。
比較動画が拡散されるうちに、「本当に似ているのか?」という検証が始まり、
次第に“部分的な共鳴”という現象が浮かび上がります。
確かに耳が引っかかる瞬間はある。
けれど曲全体を聴くと、構造もリズムも異なる。
それでも、20年以上の時を越えて同じ記憶を呼び起こすその一瞬が、
多くの人の胸に「懐かしい」という灯をともしたのです。
これは“パクリ”という単語だけでは捉えきれない。
音楽という記憶装置の中で、時代と世代が重なり合ったひとつの出来事でした。
この記事でわかること
・どの部分が「似ている」と指摘されているのか
・音楽的に見る“部分一致と全体非一致”の違い
・法的に「パクリ」と判断されるための条件
・世代が感じた“懐かしさ”の構造
・「マリーゴールド」がメダロット世代に響いた理由
※この記事は公開情報および音楽実務の解説をもとに筆者の見解として再構成しています。
感じ方には個人差があり、意図や真偽を断定するものではありません。異なる解釈が存在することを前提にお読みください。本記事は、あいみょんさんおよび関係者への誹謗中傷を目的とするものではなく、音楽表現の背景と文化的共鳴を考察するための内容です。私は「マリーゴールド」が大好きです
「マリーゴールド」は、あいみょんのメジャー5枚目のシングル。ワーナーミュージック・ジャパン内のレーベル「unBORDE」から2018年8月8日に発売された。『第69回NHK紅白歌合戦』歌唱曲[4]。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』マリーゴールド (あいみょんの曲)
メダロット弐CORE
当初は『コミックボンボン』誌上でのカブトバージョン限定通販(ボンボンバージョン)のみの販売だった。その後、クワガタバージョンを追加して2003年4月18日に市販される。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』メダロット (ゲーム イッキ編)
似ていると言われた“あの部分”とは

「マリーゴールド」と「メダロットBGM」の“似ている”という指摘が出たのは、サビの冒頭部分でした。
「麦わらの〜」と歌い出す直前の、わずか数秒の旋律です。
上昇するメロディラインとテンポ感、そして抑揚の付け方が、メダロット2の一部BGMと重なるように聞こえるのです。
サビ頭の短い共鳴点
SNSでは、両曲を同じキーやテンポに合わせて比較する動画が相次いで投稿されました。
聴き比べると、確かに“耳が引っかかる”瞬間があります。
旋律の動き方が似ているため、一瞬の既聴感を覚える人が多いのです。
ただし、そこから先の展開を追っていくと、コード進行もリズム構造も異なっています。
つまり、部分的な一致はあるが、全体構造はまったく別の楽曲設計ということです。
“部分一致・全体非一致”という見立て
音楽的な視点では、このような現象を「部分一致・全体非一致」と呼びます。
短い旋律の近似があっても、曲全体の形式や和声が違えば、それは“別作品”と見なされます。
さらに、90年代ポップスには共通したテンポ帯やコード進行が多く、
「偶然似て聞こえる」ケースが頻発する背景がありました。
そのため、「マリーゴールド」がメダロットBGMに似て聞こえるのは、
コピーではなく“時代の共有”による共鳴現象だと考えられます。
懐かしさの正体
この“共鳴”は、聴く人の記憶の中にある90年代の音楽語彙を刺激します。
ゲームボーイの電子音で育った世代が、現代のアコースティックポップの中に似た抑揚を感じる。
それが「懐かしい」という感情の源なのです。
つまり、この話題が広がった背景には、**音そのものよりも“記憶の重なり”**がありました。
✅ まとめ
・似ているのはサビ頭の短いフレーズ。
・比較動画では、一瞬の共鳴が強調されやすい。
・音楽的には部分一致にとどまり、全体構造は異なる。
・90年代的なコード進行やテンポが「懐かしさ」を呼び起こした。
音楽的に見る「似ている/違う」の境界線
“似ている”という言葉の裏には、感覚ではなく音の構造が潜んでいます。
感情ではなく、音楽的な観点から両曲を照らし合わせてみると、
共鳴と独立のラインがくっきりと分かれて見えてきます。
旋律(メロディ)での比較
まず旋律。
「マリーゴールド」のサビ冒頭は、上行から滑らかに下降していくメロディラインを描きます。
一方、「メダロット2」のBGMは、短いモチーフをループさせる設計で、
最初の数音だけが似た“跳ねるような動き”を持っています。
つまり、出だしの一瞬に共通点があっても、その後のメロディの展開は全く別方向へ進むのです。
旋律は、音楽の“顔”にあたる部分です。
この段階で構造が異なれば、音楽的には“別人”と見なされます。
和声(コード進行)での比較
次に和声。
「マリーゴールド」はI–V–vi–IV(王道進行)と呼ばれる安定したコードを用いています。
この進行は90年代以降、世界中のポップスで頻繁に使われてきた定型です。
一方、メダロット2のBGMでは、短いコードの循環の中にテンションコードを混ぜ、
電子音特有の緊張感を保っています。
つまり、根本的なコード設計が違うため、和声レベルでは“似ていない”のです。
リズムとテンポの違い
リズム面でも、両者は性格が異なります。
「マリーゴールド」は3連符のようなゆらぎを持つフォーク寄りのリズムで、
人の呼吸に合わせた自然なテンポを感じさせます。
一方、メダロットのBGMは機械的で正確な8ビート。
プレイヤーの操作にテンポを合わせるため、一定の速さを保つ設計です。
この違いにより、似ているようで似ていない“グルーヴの質”が生まれています。
形式(構造)の対比
形式的にも明確な差があります。
ポップスである「マリーゴールド」はAメロ、Bメロ、サビという三段構成。
対してメダロットのBGMはループ形式で、一定の時間内にメロディが収束します。
構造そのものが異なるため、音楽理論的には「独立した設計」と見なされます。
総合的見解
こうして見ると、“似ている”のはほんの入口だけ。
旋律・和声・リズム・形式の四要素を総合すると、
両者は「別々の音楽として成立している」と判断できます。
それでも聴き手が懐かしさを感じたのは、
コード進行やテンポが90年代特有の“安心感”を持っているからです。
つまり、「似ている」という感覚は、構造の一致ではなく“時代の記憶の重なり”によって生まれたものなのです。
✅ まとめ
・旋律はサビ頭で一瞬重なるが、展開は全く異なる。
・和声(コード進行)はポップスとゲーム音楽で別設計。
・リズムの質と構造の違いにより、全体では一致していない。
・聴き手の“懐かしさ”が類似感を増幅させた。
ネットが生んだ“懐かしさの共有現象”
SNSで話題になった「マリーゴールド」と「メダロットBGM」の“似ている”指摘は、
炎上ではなく、むしろ温かい共鳴の輪として広がっていきました。
懐かしさでつながるコメントたち
投稿欄をのぞくと、「懐かしい」「ゲームの記憶がよみがえる」といった声が多く並びました。
「やっぱり似てる」という反応も確かにありましたが、
多くは“批判”よりも“共感”のトーンです。
「もし意図的なら胸が熱い」「メダロット世代なら納得」といった発言も多く、
この現象を“偶然の奇跡”として楽しむ人が目立ちました。
ゲームのBGMを懐かしむ声も相次ぎ、
「GB音源なのに完成度が高かった」「繰り返し部分のカク付きが好きだった」と、
原曲そのものへの愛着も再燃しました。
世代を超えるリンク
特に印象的だったのは、「世代的なリンク」という反応です。
あいみょんさんがメダロット世代である可能性に触れ、
「自分たちの青春が現代のポップスで蘇った」と感じた人が多かったのです。
つまり、“似ている”という感覚が、
時代をまたいで共有されるノスタルジーを引き出したのです。
そこには、「ゲーム音楽とポップス」というジャンルの境界を越えて、
同じ文化圏の記憶が響き合うような感情がありました。
“似ている”ではなく“響き合う”へ
この現象を支えたのは、ネット特有の“集団聴覚”でした。
ひとりのリスナーが投稿した気づきが、数千人の「わかる!」を生み、
やがて“パクリ”という硬い言葉を越えて、“懐かしい”という優しい共感に変わっていきました。
つまり、これは批判の炎上ではなく、記憶を共有する文化的現象だったのです。
SNSのコメント欄はまるで同窓会のようで、
ゲームと音楽を通じて時代の空気が再び呼吸を始めたようでした。
✅ まとめ
・ネットでは「似てる」より「懐かしい」という反応が中心。
・“パクリ論争”ではなく“共感と再評価”の流れ。
・メダロット世代の記憶と現代ポップスが結びついた。
・炎上ではなく、文化的ノスタルジーとして受け止められた。
さいごに:懐かしさが生んだ文化の交差点
「マリーゴールド」と「メダロットBGM」が似ている――そんな噂から始まった小さな話題は、
最終的に“懐かしさ”という言葉に回収されました。
音がつなぐ記憶
サビ頭の短い旋律が重なった偶然は、
20年以上前のゲーム音楽と現代のポップスを静かに結びつけました。
それは模倣でも盗用でもなく、時代を超えて共鳴した記憶の断片です。
メロディは、人の心の奥に眠る体験を呼び覚ます力を持っています。
「似ている」と感じた瞬間、聴き手は音ではなく“自分の過去”を思い出していたのかもしれません。
ネット時代の“懐かしさ共有”
SNSが普及した今、懐かしさは一人で味わうものではなく、
みんなで“再生”する感情になりました。
誰かが「これ、あの曲に似てる」と言えば、
そこから一斉に“あの頃”の記憶が呼び戻される。
メダロットのBGMが再評価され、
「マリーゴールド」が世代の境界を越えて聴かれるようになったのは、
そんなネット時代ならではの共感の連鎖です。
音楽が残したもの
結局のところ、“パクリ”という線引きよりも、
音楽が人の感情をつなぐ力の方が、はるかに大きな意味を持っていました。
偶然が重なって生まれたこの小さな議論は、
ポップスとゲーム音楽が同じ文化の土壌で育ってきたことを教えてくれます。
「似ている」という一言の中には、
かつての自分の青春、そして時代の音が静かに息づいていたのです。
✅ まとめ
・サビ頭の共鳴は“記憶の偶然”として生まれた。
・ネット時代では懐かしさが共有され、文化として再生する。
・“パクリ”よりも“響き合い”が焦点となった。
・音楽は、世代を越えて人の心をつなぐメディアである。
※本記事は、公に確認可能な情報や一次資料(公式データベース・法務解説・著作権関連文献等)をもとに、筆者独自の見解として再構成した内容です。
※各種見解や感じ方には個人差があり、あいみょんさん、山下絹代さん、その他関係者への誹謗中傷を目的とするものではありません。
※本記事は音楽文化の考察を目的としており、法的判断・断定的評価を行うものではありません。
参照情報(出典整理)
MEDAROT CLASSICS+ SOUNDTRACK:クレジット(VGMdb)
音楽著作物の類似性判断の枠組み(Innoventier 公式)
依拠性・実質的類似の基本整理(コット法律事務所)