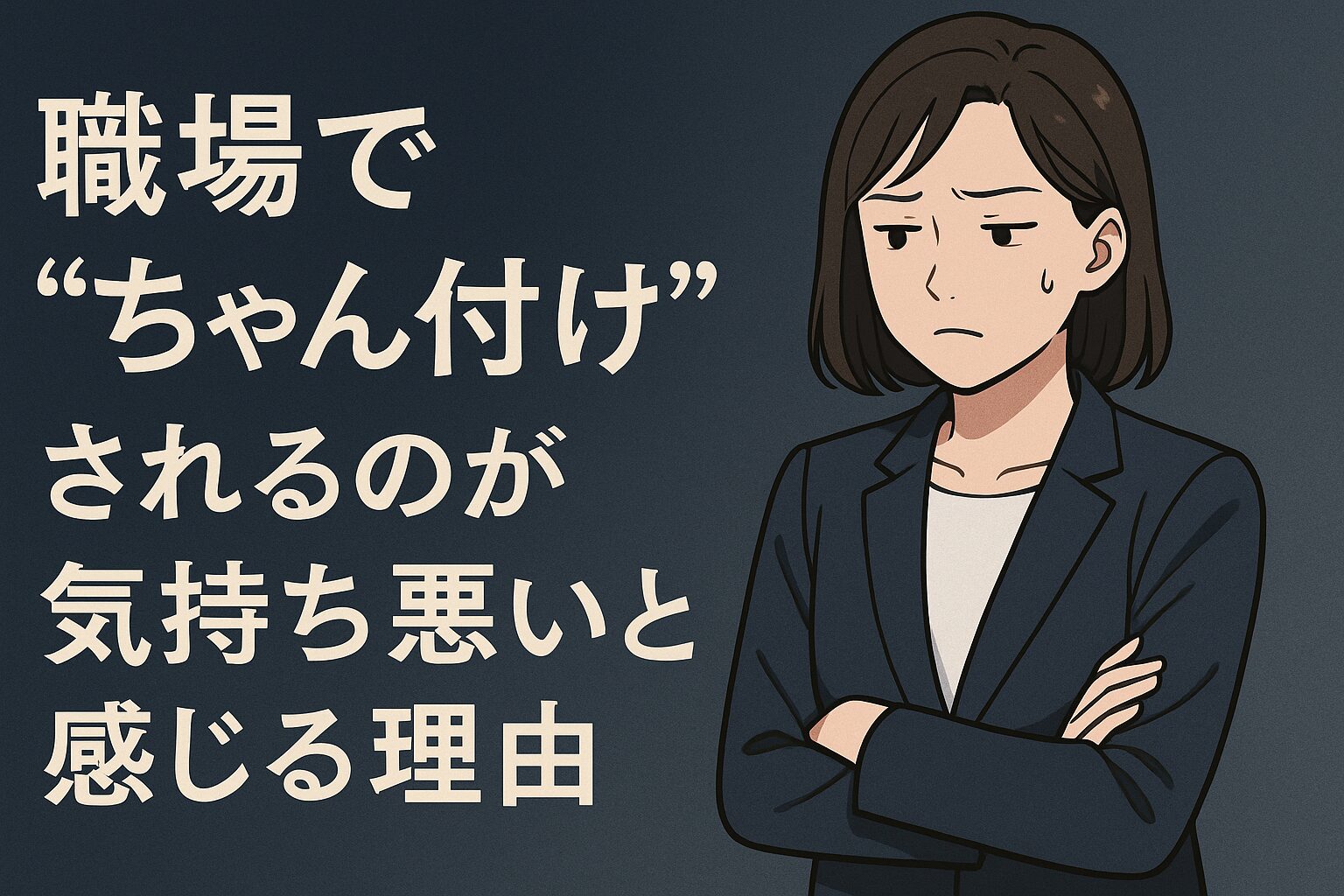朝のオフィス。
パソコンを立ち上げたその瞬間、隣の席から何気ない声が飛んできました。
「○○ちゃん、昨日の資料ありがとう!」
——その一言に、なぜか心がザワッとする。
呼ばれた本人も、周囲の人も、たぶん笑って済ませている。
けれど、胸の奥では「仕事の場なのに、なんで“ちゃん”なの?」という小さな違和感が消えない。
親や友人なら当たり前の呼び方でも、職場ではなぜか不快に感じてしまう。
この感覚、あなたにも覚えがありませんか。
いま、“ちゃん付け”という何気ない呼称が、職場のハラスメント問題のひとつとして注目されています。
2025年10月、東京地裁が下した判決。
「○○ちゃん」と呼び続けた男性に、22万円の支払いを命じた——。
このニュースは、「言葉づかい」に潜む力関係の問題を、社会全体に突きつける出来事となりました。
本記事では、
・なぜ“ちゃん付け”が「気持ち悪い」と感じられるのか。
・どこからがハラスメントと判断されるのか。
・そして、どう向き合えばいいのか。
心理と法の両面から、じっくりと紐解いていきます。
✅ この記事を読めば、「職場での呼び方」がもたらす影響と、安心して働くための距離感の保ち方の参考になるかもしれませんので、ぜひ最後まで読んでくださると嬉しいです。
ちゃんづけはなぜ、あんなにも気持ち悪く響くのか

ある日、いつものようにデスクで仕事仕事仕事。
コーヒーを片手にPC画面を見つめていると、背後からふわりと呼びかけられる。
「○○ちゃん」
声のトーンは柔らかく、言葉そのものも悪意などなさそうです。
でも――なぜか、心の奥にほんの少し“ざらつき”が残る。
これが、“ちゃん付け”という呼称が持つ厄介な力です。
“ちゃん”は音としては優しく聞こえます。
でもその音は、私たちが子どもだったころの空気と結びついていることがあります。
家庭の居間、近所の公園、幼なじみとの笑い声。
その優しい記憶と、無機質な蛍光灯が照らす職場の空気が衝突したとき、違和感が生まれるのです。
呼称は“音”ではなく“距離感”を測る定規
呼び方というのは、実は「音」以上に「距離」を伝えるものです。
“さん”には一定の安全距離がある。
“くん”は一歩踏み込んだ距離感。
“ちゃん”は――靴を脱いで座敷に上がり込むような近さを示します。
呼ぶ側が「親しみ」を込めていても、呼ばれる側には「境界を踏まれた」と感じられる場合があります。
呼称は、発した瞬間に相手の心の中で距離を測られる。
「近い」と感じるか、「侵入された」と感じるか――その判断は、呼ぶ側ではなく呼ばれる側の手の中にあるのです。
この感覚は個人差が大きく、そして一度違和感が生まれると、職場の空気は静かに変わっていきます。
法廷が踏み込んできた日──“呼び方”が裁かれる時代
2025年10月、東京地方裁判所が一つの判決を言い渡しました。
営業所に勤務していた女性が、年上の元同僚から“ちゃん付け”で呼ばれ続けたうえ、「かわいい」「体形が良い」といった発言を受けたと訴えた裁判です。
裁判所は、この行為を「許容される限度を超えた違法なハラスメント」と認定し、男性に22万円の支払いを命じました。
金額は決して高額ではありません。
けれども、この判決の本質は金額ではなく、「呼称」という日常的な行為が法的な線引きの対象になったという点にあります。
判決では、裁判官がこう指摘しました。
「“ちゃん付け”は幼い子どもに向けた呼称であり、業務上用いる必要はない」
業務に必要性のない呼称は、たとえ悪意がなくても、職場環境を損なうものとしてハラスメントに発展し得る――その境界線が明確にされたのです。
さらに容姿への言及も重なったことで、発言全体が「職場環境を害する行為」と判断されました。
呼称の話が、ついに“職場の空気”から“法の世界”に踏み込んだ瞬間です。
信頼関係と“ちゃん”のグレーゾーン
ここで重要なのは、「“ちゃん付け”がすべて違法になる」という話ではないという点です。
信頼関係の中で自然に交わされる“ちゃん”には、あたたかさがある場合もあります。
しかし、それは二人の間に“共有された文脈”がある場合に限られます。
第三者がいる場では、その文脈が伝わらず、周囲に不公平感や緊張感を生むことがあります。
「親しみ」のつもりが、「線引きを壊す行為」に変わる瞬間は、呼ぶ側が思っているよりずっと静かで、そして早いのです。
禁止ではなく、呼称を“設計する”時代へ
最近では、企業の対応にも変化が見え始めています。
昔のように「まあまあ」で済ませるのではなく、呼称の扱いをルールとして明文化する企業が増えています。
・呼称ルールの共有
・違和感を伝えられる相談体制
・「無意識」の親しさを削る取り組み
これらは派手さのない地味な対策ですが、呼称によるトラブルを防ぐうえで確実に効果があります。
いま求められているのは、「禁止」ではなく、「どう設計するか」という視点です。
最後に──呼び方ひとつで、空気は変わる
“ちゃん”というたった二文字に、幼い頃の記憶と、大人の社会の構造が同居しています。
それは優しさでもあり、境界線でもあり、時に法廷の材料にもなる。
だからこそ、呼び方は“なんとなく”ではなく、“意識的に”選ぶ時代になっています。
呼称は、相手をどう見るかの鏡です。
敬意のない呼び方は、静かに信頼を削り、場合によっては法律の領域にまで踏み込みます。
空気をつくるのは言葉です。
そして、その空気を壊すのもまた――言葉なのです。
✅ まとめ
・“ちゃん付け”は職場において心理的距離を乱すトリガーになり得る。
・呼称は意図よりも受け手の感覚によって評価される。
・2025年の東京地裁判決は、呼称が法的リスクになる可能性を示した。
・信頼関係の有無や第三者の存在で、意味が大きく変わる。
・禁止ではなく、ルール設計と敬意が鍵になる。
免責事項
本記事の内容は、2025年10月23日時点の判例や公的情報、一般的なハラスメント防止の考え方に基づいて執筆したものです。記載内容はあくまで一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の状況に対する法的助言や専門家による判断を代替するものではありません。実際のトラブルや法的対応が必要な場合には、労働問題に詳しい弁護士や専門の相談機関へのご相談を強くおすすめします。なお、情報の正確性については細心の注意を払っていますが、判例や法制度は今後変更される可能性があります。最新情報のご確認をお願いいたします。
本記事の参照情報(出典整理)URL一覧
- 東京地裁判決報道(Yahoo!)
https://news.yahoo.co.jp/articles/645789555e59f7e3c9d07a244c787f48ef3886b1 - 厚生労働省|職場におけるハラスメント対策
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html - 厚生労働省|セクシュアルハラスメント対策の指針
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/index.html - 内閣府 男女共同参画局|職場のハラスメントに関する情報
https://www.gender.go.jp - 日本労働組合総連合会|ハラスメント防止に関する調査・提言
https://www.jtuc-rengo.or.jp/column/column007.html