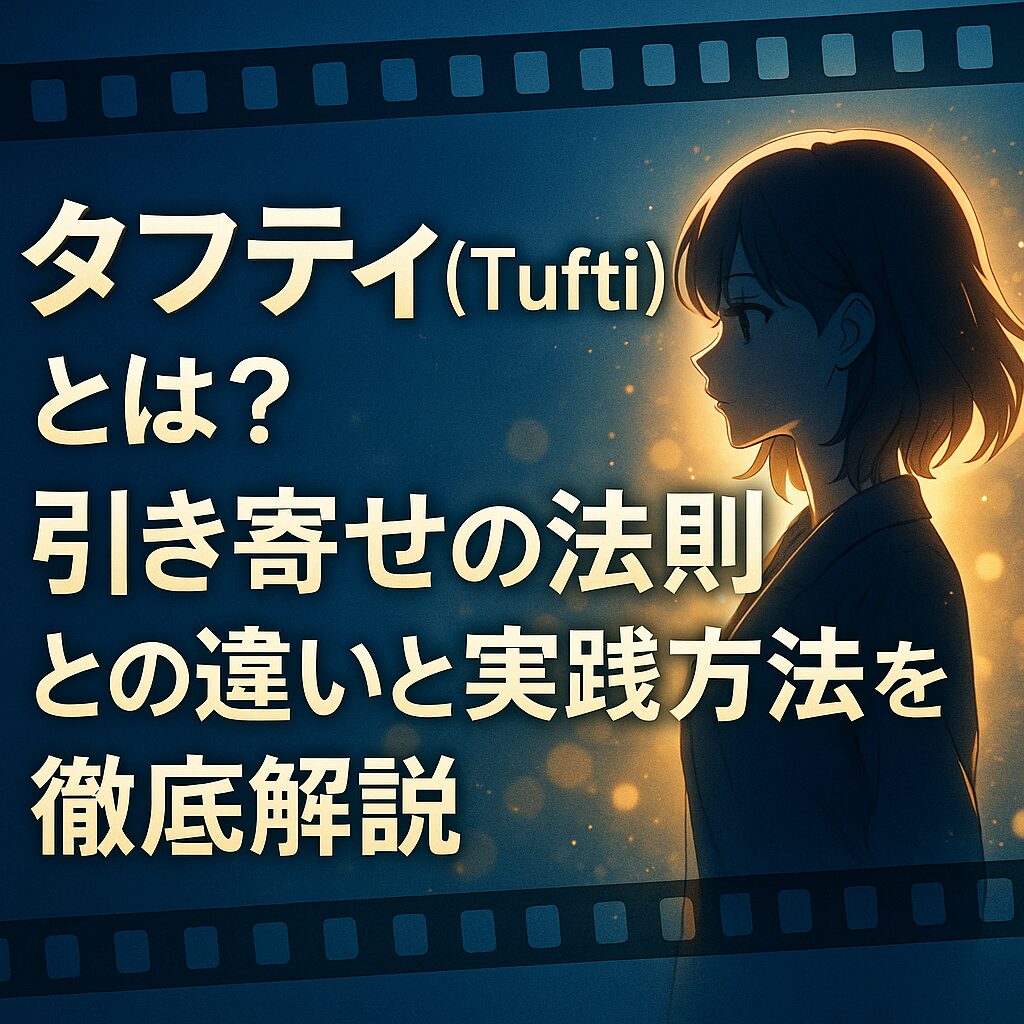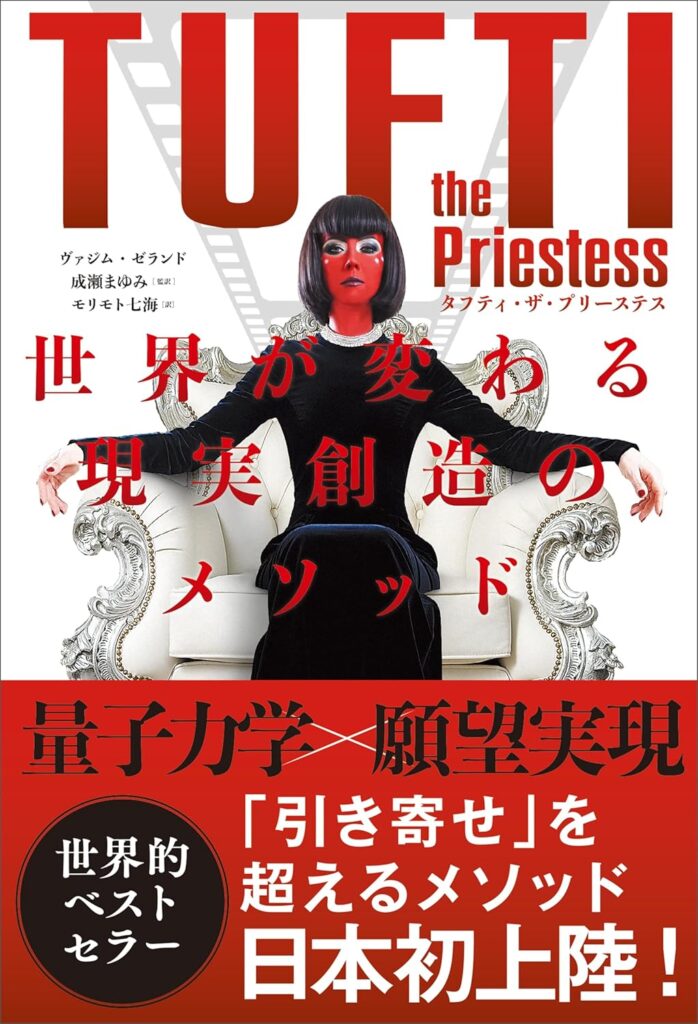今日も一日が重たそうだ・・・
朝の満員電車でそう感じた途端、
気分が沈み、そのまま仕事のリズムまで崩れてしまう。
こうした経験は、多くの人が一度は味わったことがあるのではないでしょうか。
しかし、同じ状況でも
「一日の終わりには落ち着いてコーヒーを飲んでいる自分」
を先に思い描くことで、不思議と気持ちが軽くなり、行動も変わる場合があります。
このように「現実をどう切り取るか」をテーマにした考え方として注目されているのが、ロシアの作家ゼランドさんが提示した
**タフティ(Tufti)**です。
引き寄せの法則が「思考や感情によって現実を引き寄せる」ことを中心に据えるのに対し、
タフティは「人生を映画のように編集する」という能動的な姿勢を強調する点が特徴だとされています。
この記事では、タフティの基本概念や実践方法を日常の場面に落とし込みながら、引き寄せの法則との違いをわかりやすくまとめていきます。

この記事は「言葉の意味」が気になる方向けに、
タフティとは?をまとめたものです。
※決して推奨しているわけではありません

こういうのもあるのか〜
程度に読んでいただけると幸いです
この記事でわかること
- タフティ(Tufti)とは何か、その基本構造
- 引き寄せの法則との明確な違い
- 通勤や職場などで応用できるタフティの実践例
- 注意点や限界を踏まえた現実的な取り入れ方
※この記事はSNS情報を中心に書かれていますが、意見や感じ方は人それぞれです。推測の域を出ず、異なる意見や見解があることも理解しておりますので、どうかご了承ください。本記事を通じて、少しでも多くの方に伝えられれば幸いです。
タフティ(Tufti)とは?現実創造メソッドの概要

朝、満員電車に揺られているとき
「今日は絶対に疲れる一日になりそうだ」
と思ったら、
本当にその予感通りの流れになった――
そんな経験はないでしょうか。
これは、外の出来事に意識を奪われて、自分自身の“脚本”を編集できない状態といえます。
ここで登場するのが、ここで登場するのが、ロシアの作家ヴァジム・ゼランドさんが提示した
**タフティ(Tufti)**
という考え方です。
彼は「人生は映画」「自分は監督であり編集者」と捉え、注意と意図をうまく扱えば、シーンの進み方を変えられると説明しました。
つまり「流される人生」から「編集する人生」への転換です。
さらに上に紹介した『タフティ・ザ・プリーステス』では、単なる理論にとどまらず、イシス神殿の巫女タフティという象徴的キャラクターを通して、現実創造の仕組みが語られます。
これは単なるおとぎ話ではなく、「現実は巨大な鏡のように自分を映す」という発想を読者に体感させるための仕掛けでもあるそうですね。
タフティの基本概念
タフティではいくつかの重要なキーワードが提示されています。
難しそうに聞こえるかもしれませんが、日常のたとえにすると意外と理解しやすいのです。
| 概念 | 説明 | 日常でのたとえ |
|---|---|---|
| 二つのスクリーン | 内側スクリーン=思考やイメージ、外側スクリーン=現実の出来事 | 頭の中で考えていること(内側)と、目の前で起きていること(外側)の二重スクリーンを映画館の映写とスクリーンに例える |
| センター・スクリーン | 「私は自分を見ている」と確認する観察者の位置 | ゲーム実況者が自分のプレイを客観的に解説するように、自分の行動を少し引いた視点で眺める |
| 意図の三つ編み | 背中にあるとされる“操作点”に注意を置く象徴的イメージ | スマホを操作するとき、電源ボタンを押さなければ画面が動かないのと同じ“起動スイッチ” |
なぜ注目されているのか?
引き寄せの法則が
「ポジティブな気持ちを保てば現実が変わる」
といった“受け身”の姿勢に重きを置くのに対し、
タフティは
「現実の流れを能動的に選び直す」ことを強調します。
そのため「思うだけでは変わらない」と感じてきた人にとって、新しい切り口として支持を集めているようです。
「もっと詳しくタフティのメソッドを知りたい方は、ゼランドさんの著書
『タフティ・ザ・プリーステス 世界が変わる現実創造のメソッド』 を直接読むのがおすすめです。
具体的なレッスン形式で“二つのスクリーン”や“意図の三つ編み”といった概念が解説されているので、この記事の内容をより深く実践につなげられると思います。
昨日、友達に「『タフティ』という本を読んでくれ!そして俺に要約して教えてくれ!」と言われたので読んでみた。 たぶんだけど、この本の中で言ってるのは原理的には 【自分を変性意識状態にして、理想の未来を思い描いたら脳(潜在意識)が勝手にその未来への行き方を教えてくれるよ!あとはそれに従って行動したら良いよ!】 って事なんじゃないかしら。
https://x.com/tomozounew/status/1953718469759053991
変性意識状態(へんせいいしきじょうたい、英: altered state of consciousness, ASC)とは、目覚めてはいるが、日常的な意識状態とは異なった意識状態のこと。 「altered state of mind」や「altered state of awareness」ともいう。
~~中略~~
変性意識状態となるのは、たとえば精神や肉体が極限まで追い込まれた場合、瞑想を行っている時、薬物を使用している時などがあるとされる。また、催眠状態、催眠などによって非常にリラックスした状態も心理学では変性意識状態の一種と分類する。
変性意識状態は「宇宙との一体感」「全知全能感」「強い至福感」などを伴うことがあり、この体験(変性意識体験)は時に人の世界観を一変させるほどの強烈なものも含まれる、といわれる。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』変性意識状態
引き寄せの法則との違い

「願えば叶う」とよく耳にするのが、いわゆる引き寄せの法則です。
ポジティブな気持ちや理想の未来を信じることで、似たような現実を引き寄せる――シンプルでわかりやすい考え方です。
ただ、実際には「願っているのにうまくいかない」「思い込みにしか感じられない」という声も少なくありません。
一方で**タフティ(Tufti)**は、ただ願うのではなく「人生の脚本を自分で編集する」という立ち位置を取ります。
つまり「待つ」のではなく「選ぶ・操作する」イメージです。
日常での違いを例えると…
- 引き寄せ:
仕事帰りに「今日はラーメンを食べたいな」とずっと考えていると、たまたま道すがらラーメン屋の割引チラシを見つける。まるで“引き寄せられた”ように感じる。 - タフティ:
同じ状況で、「今夜はラーメンを食べて満足している自分」という“未来の一枚絵”を先に設定しておく。すると自然にラーメン屋を選んで歩き、現実がその絵に滑り込む。
どちらも「ラーメンにたどり着く」点は同じですが、スタンスが大きく違います。
比較表で整理すると
| 観点 | 引き寄せの法則 | タフティ(Tufti) |
|---|---|---|
| 基本の姿勢 | 願いを信じて待つ | 現実を編集して選ぶ |
| 行動のイメージ | 受動的(波動が合うのを待つ) | 能動的(未来のフレームに合わせる) |
| 具体的な手法 | アファメーション、ポジティブ思考 | センター・スクリーン、意図の三つ編み、エンドフレーム |
| 体感の違い | 「偶然引き寄せられた」感覚 | 「自分でシナリオを操作した」感覚 |
読者へのヒント
「願うだけでは何も変わらない」と感じていた人にとって、タフティの“脚本編集”という発想は現実的に試してみる価値があるかもしれません。
たとえば「今週を乗り切って金曜の夜に笑顔で乾杯している自分」を先に思い描くだけでも、日々の小さな選択が自然とそのフレームに導かれていくのです。
タフティの実践ステップ

タフティの魅力は「ただ信じる」だけではなく、日常生活に落とし込める具体的な手順があることだそうですね。
ここでは代表的な流れを、実際のシーンを例にしながら紹介します。
ステップ1:センター・スクリーンに立つ
まずは「私は自分を見ている」と心の中で宣言し、自分の存在を少し客観視します。
たとえば満員電車の中。
周りの雑音や人の圧に巻き込まれそうになった時、あえて
「私は今、混雑の中で立っている自分を見ている」
とつぶやくと、不思議と心が一歩引いた位置に立ち直せます。
ステップ2:意図の三つ編みを起動
次に注意を“背中の中心”に置くイメージを持ちます。ここを操作点だと仮定し、「スイッチが入った」と思うだけで大丈夫です。
職場で上司に急に声をかけられて動揺する場面でも、この「背中スイッチ」を思い出すだけで、自分の意識が外に持っていかれず、落ち着きを取り戻せます。
ステップ3:エンドフレームを描く
その日のゴールを“一枚の静止画”で思い描きます。
たとえば「夕方、デスクで仕事を片づけてホッと笑顔になっている自分」という場面です。
この一コマを“映画のラストシーン”のように設定すると、途中の小さな出来事も自然にそこへつながっていきます。
ステップ4:解放し、最小行動を選ぶ
最後に「今やる一歩」だけを決めます。
例えば
「まずメールを整理する」
「今日は朝礼で一言だけ笑顔で挨拶する」
といったシンプルな行動で十分です。
ラストシーンに近づく道筋は、その一歩から自然に展開していきます。
実践のポイント
| ステップ | 具体的なコツ | 日常の例 |
|---|---|---|
| センター・スクリーン | 「私は自分を見ている」と宣言 | 満員電車でストレスに飲まれない |
| 意図の三つ編み | 背中に注意を置く | 上司の声かけで動揺しない |
| エンドフレーム | “終わりの一枚”を思い描く | 夕方の達成感ある自分を想像 |
| 最小行動 | 直近の一歩に集中 | メールを一通整理する |
この流れを毎日5分ほどで繰り返すだけでも、気分がブレにくくなり「自分が編集している映画」に戻れる感覚が得られるそうです。
留意点と限界
タフティは「人生を映画のように編集する」というユニークな発想が注目を集めていますが、万能の魔法ではないようです。
ここでは冷静に見ておきたい注意点を整理します。
科学的な根拠は乏しい
引き寄せの法則と同じく、
タフティも科学的に実証されたメソッドではありません。
脳科学や心理学で完全に裏づけられているわけではなく、むしろ「比喩的なフレーム」として活するのが現実的です。
たとえば「背中の三つ編みを起動する」といっても、医学的にそのような器官が存在するわけではなく、注意を切り替えるための“仮想ボタン”のようなイメージと考えるのが妥当でしょう。
行動を伴わなければ変化は起きにくい
「イメージするだけで人生が変わる」
と誤解してしまうと、期待外れに終わってしまいます。
実際には、最後のステップである「最小行動」を積み重ねることが重要です。
たとえば「昇進した自分」を思い描くのは良いのですが、そこから「上司に一つ報告を丁寧にする」などの行動につなげなければ、現実のシナリオは動きません。
心理的なリスクにも注意
「思った通りにいかない=自分のせいだ」と考え込みすぎると、逆にストレスを強めてしまう可能性があります。
これは引き寄せの法則でもよく指摘される問題で、「自己責任論」に偏りやすい点には注意が必要です。
あくまで気持ちを切り替えるための“ツール”くらいの距離感で使うのが安全です。
まとめ表
| ポイント | 注意点 | 現実的な活用法 |
|---|---|---|
| 科学的根拠 | 実証は乏しい | 「比喩的フレーム」として使う |
| 行動の必要性 | イメージだけでは変わらない | 「最小行動」を必ず紐づける |
| 心理的リスク | うまくいかないと自己責任化 | ツール感覚でライトに試す |
つまり、タフティを取り入れるなら「スピリチュアル信仰」として重く考えるより、「日常の気分を編集する工夫」として軽やかに使うほうが現実的なのでしょう。
さいごに

タフティ(Tufti)は「人生を映画に見立て、自分を編集者として扱う」というユニークなメソッドです。
引き寄せの法則が「思考や感情を信じ続ける」ことに重きを置くのに対し、
タフティは「注意と意図を使って脚本を編集する」能動的なアプローチが特徴といえます。
もちろん科学的に立証されているわけではなく、万能の方法ではありません。
ですが、
「観察者の視点に立つ」
「未来の一枚絵を先に描く」
「小さな行動に結びつける」
という流れは、セルフコーチングや目標管理に近く、日常の中でも取り入れやすい工夫でしょう。
たとえば今日からできるのは、こんなシンプルなことです。
- 満員電車で「私は自分を見ている」と心でつぶやく
- 職場で背中を意識して呼吸を整える
- 一日の終わりに「落ち着いた自分」のイメージを一枚だけ描く
- そのうえで「最初の一歩」を決めて実行する
こうした小さな積み重ねを続けることで、「気づいたら自分が望んでいたシーンに滑り込んでいた」という感覚を味わえるかもしれませんね。
「願っても叶わない」と思っていた人にこそ、
タフティを“現実を動かすもう一つの視点”として___
気になる方は是非書籍も試してみてはいかがでしょうか。